執筆者・監修者:薬剤師
「予防接種はどのように機能するの?」
「予防接種は受けたほうがよい?」
「どのような予防接種があるの?」
上記のような疑問を持つ方も多いでしょう。
予防接種は、ウイルスや細菌への免疫をあらかじめつけ、重症化や流行を防ぐ重要な手段です。当記事では、定期接種と任意接種の違い、年齢別スケジュール、近年の制度変更までまとめています。
最後まで読むことで、家族全員が安心して健康を守るための予防接種の基礎と最新情報を理解できるでしょう。
予防接種とは?ワクチンが病気を防ぐ仕組み
予防接種とは、ウイルスや細菌による感染症にかからないように、あらかじめ体に病気のもとに似たものであるワクチンを入れて免疫を作る方法です。ワクチンを受けると、体の中で病気に対する守りの仕組みとなる抗体が作られ、次に同じ病気が入ってきても、すぐに追い出せるようになります。
ワクチンを受けておけば、病気にかかっても軽くすむことが多く、発症後に起こる重い症状を防げるのが特徴です。副反応として、注射した場所の腫れや発熱などの症状が出ることがありますが、多くは短期間でおさまります。
なぜ予防接種は必要?ワクチンで防げる病気(VPD)と重要性
予防接種は、感染症を未然に防ぐ効果的な手段のひとつです。ワクチンを通じて免疫を得ることで、命を守るだけでなく、流行の拡大を防ぐ社会的な役割も果たします。ここでは、予防接種で防げる病気と重要性について、詳しく見ていきましょう。
子どもの命を守る予防接種「VPD」とは?
予防接種は、重い感染症から子どもの命を守るために欠かせない医療行為です。
VPDとは「Vaccine Preventable Diseases」の略で、ワクチン接種によって発症や重症化を防げる感染症を指します。代表的なVPDには以下があります。
● 麻疹
● 風疹
● ジフテリア
● 百日せき
● 破傷風
● ポリオ
● 日本脳炎
● 季節性インフルエンザ
感染すると脳炎や肺炎など重い合併症を起こすことがあり、後遺症や命の危険につながります。予防接種で免疫をつけておくことが、子どもを守る効果的な方法です。
自分だけじゃない!社会全体を感染症から守る役割
予防接種の拡大は、社会全体を守る重要な手段です。十分な人数が予防接種を受けると、感染症の拡大が起こりにくくなり、免疫をつくれない方を守れるメカニズムが働きます。また、感染症流行のリスクが低くなることで医療への負荷も軽減され、社会の安定にもつながるでしょう。
さらに、個人がワクチンを受けることで得られる保護に加えて、周囲の人々の健康を支える効果も生まれます。予防接種は、上記のように社会的意義も大きいといえます。
予防接種の種類|定期接種と任意接種の違い
 予防接種には、国の制度として実施されるものと、希望によって受けるものがあります。どちらも感染症から体を守る大切な手段であり、年齢や生活環境にあわせた判断が必要です。ここでは、予防接種の種類と特徴について、詳しく解説していきます。
予防接種には、国の制度として実施されるものと、希望によって受けるものがあります。どちらも感染症から体を守る大切な手段であり、年齢や生活環境にあわせた判断が必要です。ここでは、予防接種の種類と特徴について、詳しく解説していきます。
法律で定められた「定期接種」と対象ワクチン
予防接種法に基づいて実施される定期接種は、疫学的に重大な感染症を対象とし、国民の集団免疫を確保するために制度化されたものです。
具体的には以下のようなワクチンが含まれます。
● 5種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib感染症)
● BCGワクチン(結核)
● MRワクチン(麻疹・風疹)
● 日本脳炎ワクチン
● 水痘ワクチン
● B型肝炎ワクチン など
上記のワクチンは、原則として公費(自治体負担)で受けられ、接種対象年齢が政令で定められています。結果として、定期接種制度を通じて個人の健康を守るだけでなく、地域社会全体の予防水準を維持する役割も果たしています。
受けておきたい任意接種のワクチン
任意で受ける予防接種には、費用を自己負担するものの、感染すると重症化や合併症のリスクが高い病気を予防する意味が強いです。
たとえば、以下のようなワクチンが含まれます。
● 三種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風)
● おたふくかぜワクチン
● インフルエンザワクチン
上記のワクチンは、定期接種の対象には含まれていないものの、子どもの発育や健康を守るために推奨されています。結果として、任意接種を受けることで個人の防御力を高めつつ、他者への感染リスクを低減する社会的な効果も期待できます。
【年齢別】予防接種のスケジュールと受け方のポイント
予防接種は、年齢や体の発達にあわせて受ける時期が決まっており、いつから始めるかを理解することが大切です。赤ちゃんから高齢者まで、それぞれの年代で必要なワクチンがあります。ここでは、年齢別の予防接種スケジュールと受け方のポイントを見ていきましょう。
0歳から始める赤ちゃんの予防接種スケジュール
以下は、0歳から始める赤ちゃんの予防接種スケジュールの目安です。
| 月齢・年齢 | 主な予防接種の種類 |
| 生後2か月~4か月 | 以下の1回目~3回目(種類によって回数に違いあり) ・B型肝炎 ・ロタウィルス ・肺炎球菌 ・5種混合・4種混合 ・Hib(ヒブ) |
| 生後5か月~ | BCG【1回目】 |
| 生後7か月~ | B型肝炎【3回目】 |
| 生後12か月~ | ・肺炎球菌【4回目】 ・5種混合・4種混合【4回目】 ・Hib(ヒブ)【4回目】 ・MR(麻疹・風疹混合)【1回目】 ・水痘【1回目】 |
| 生後18か月~ | 水痘【2回目】 |
| 3歳~ | 日本脳炎【1回目・2回目】 |
| 4歳~ | 日本脳炎【3回目】 |
| 5歳~ | MR(麻疹・風疹混合)【2回目】 |
生後2か月から複数のワクチン接種が始まり、適切な間隔で2回目・3回目の追加接種をおこなうことが大切です。感染症の重症化を防ぐため、医療機関でスケジュールを確認しながら計画的に進めましょう。
大人・高齢者に推奨される予防接種の種類とタイミング
加齢に伴い免疫力は低下し、肺炎球菌や帯状疱疹などの感染症にかかりやすくなります。そのため、大人や高齢者でも予防接種を計画的におこなうことが大切です。
主なワクチンとして、以下が推奨されています。
● 肺炎球菌ワクチン:65歳以上で定期接種対象。再接種は5年以上あけて検討
● 帯状疱疹ワクチン:50歳以上で発症予防に有効。2回接種で長期的な免疫維持
● インフルエンザワクチン:毎年秋に1回接種し、重症化を予防
● 破傷風トキソイド:最終接種から10年以上経過している場合に追加接種を推奨
予防接種を年齢や健康状態にあわせて実施することで、感染症の重症化を防ぎ、健康寿命の延伸につながります。
同時接種は安全?知っておきたいメリットと注意点
同時接種とは、複数のワクチンを同じ日に別の部位へ打つ方法であり、安全性は多くの研究で確認されています。世界保健機関(WHO)や日本小児科学会も有効な接種方法として推奨しています。
同時接種の主なメリットを、以下にまとめました。
● 通院回数の削減
● 接種の打ち漏れ防止
● 早期に免疫を獲得できる
一方で、注射部位の腫れや発熱などの一時的な副反応が出るといったデメリットもあります。接種前に医師と相談し、体調やスケジュールにあわせて安全に進めることが大切です。
コロナ禍を経て変わった予防接種のポイント
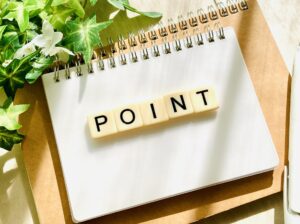 コロナ禍をきっかけに、予防接種の制度やスケジュールにも新たな変化が生まれました。感染症対策の重要性が再認識され、より効率的で受けやすい仕組みが整備されています。ここでは、最近の制度改正による主な変更点について確認していきましょう。
コロナ禍をきっかけに、予防接種の制度やスケジュールにも新たな変化が生まれました。感染症対策の重要性が再認識され、より効率的で受けやすい仕組みが整備されています。ここでは、最近の制度改正による主な変更点について確認していきましょう。
新型コロナワクチンの定期接種化
2024年4月1日から、新型コロナワクチンは定期接種の枠組みに移行しました。主に65歳以上の高齢者および60〜64歳で心臓・腎臓・呼吸器機能に重度の障害がある方などが対象です。接種は自治体ごとに秋冬シーズンに実施され、標準的な自己負担額は約7,000円程度と設定されています。
対象年齢外の方が接種を希望する場合は任意接種となり、費用は全額自己負担です。そのため、予防接種を受ける時期や対象となる条件、費用の有無などを事前に確認しておくことが重要です。
5種混合ワクチン開始により接種負担が減少
2024年4月から、4種混合ワクチンとヒブワクチンを一体化した5種混合ワクチンが定期接種に導入されました。接種回数が従来より少なくなったため通院機会が減少し、1つの注射で5つの病気(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)を予防可能になりました。
これにより、保護者と医療現場双方の負担軽減が期待できます。実施対象年齢は生後2か月から7歳5か月までで、接種の完了には3回+追加1回が標準と定められています。子どもの健康を守る観点から、予防接種スケジュールの見直しをしてみてください。
まとめ
予防接種は、個人の健康を守るだけでなく、社会全体の感染症拡大を防ぐ重要な手段です。年齢や体調にあわせたワクチンの接種スケジュールを把握し、適切な時期に接種を進めることで重症化を防げます。
また、5種混合ワクチンの導入や新型コロナワクチンの定期接種化など、制度の変化にも注目することが必要です。当記事を参考に、家族全員が安心して暮らせるよう、予防接種を上手に活用して健康維持に役立ててください。
予防接種とともにお薬も服用するなら、LINEの「つながる薬局」のサービスが便利です。つながる薬局を友だち登録後にかかりつけ薬局としてお好きな薬局を登録すれば、薬局薬剤師にLINEで相談ができます。
LINEがあれば、新しいアプリをインストールすることなく簡単に利用できるサービスため、ぜひ「つながる薬局」をご利用ください。
つながる薬局は、薬局への処方箋送信から健康・お薬相談、お薬手帳までLINEひとつでご利用いただけるサービスです!
つながる薬局を利用できる薬局はこちら!




