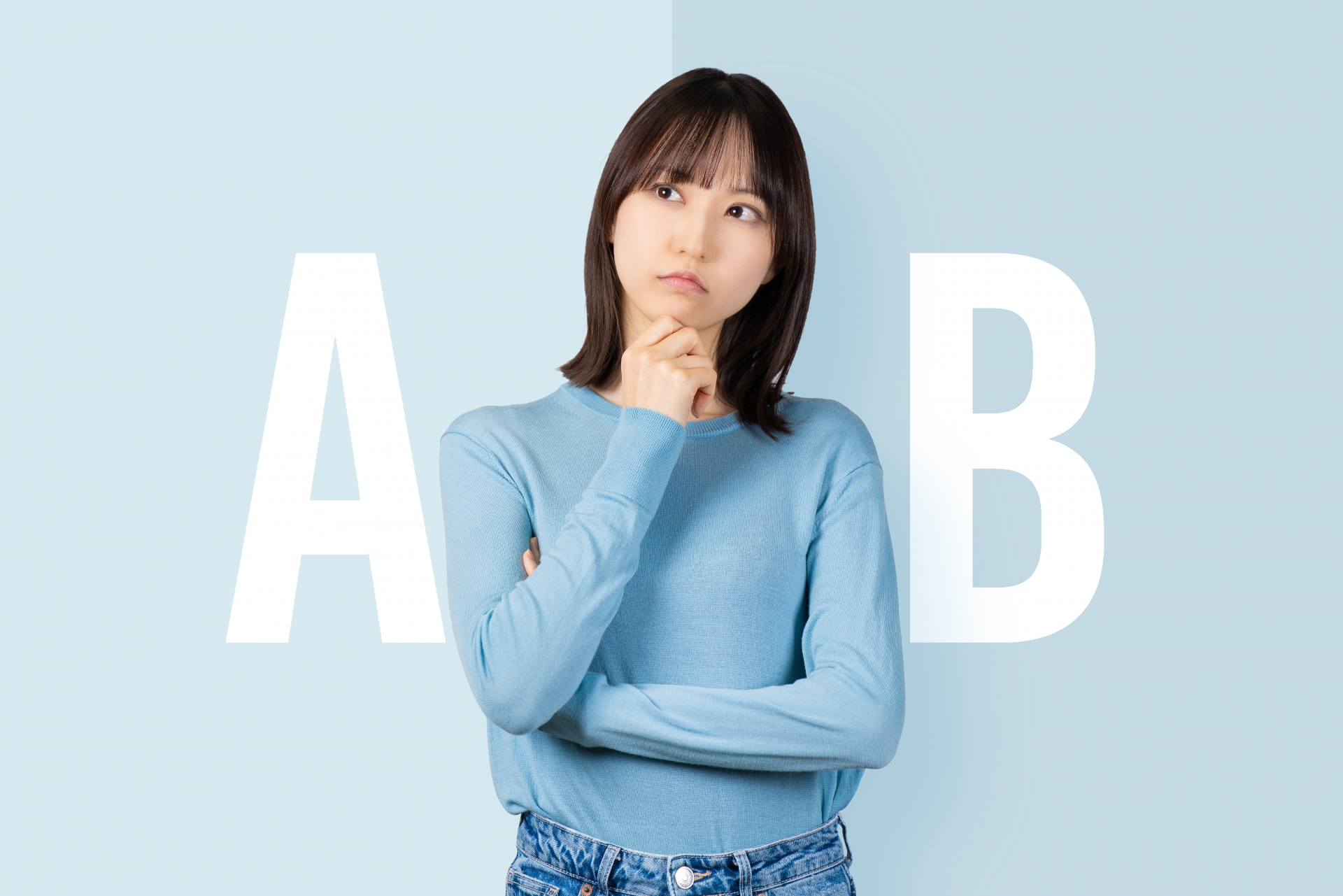執筆者・監修者:薬剤師
「暑い日が続いて体がだるい」
「頭痛や発熱の症状があるけど、熱中症なのか新型コロナなどの感染症なのか分からない」
といった悩みはありませんか?
熱中症と感染症は初期症状が似ているため、判断を誤ると適切な対処ができず症状が悪化してしまう恐れがあり、大変ですよね。この記事では、熱中症と感染症の違いや見分け方のポイント、それぞれに効果的な予防法や対処法を詳しくご紹介しています。正しい知識を身につけてご自身や大切な方の健康を守るために、ぜひご参考にしてください。
熱中症と感染症の違い
熱中症と夏風邪などの感染症には以下のような違いがあります。
| 熱中症 | 感染症 | |
| 原因 | 高温多湿の環境による体温調節の乱れ | ウイルス感染(コロナウイルス、エンテロウイルス・アデノウイルスなど) |
| 症状 | 頭痛、倦怠感、手足がつる、めまい、吐き気、発汗異常、皮膚の乾燥、発熱(重症時) | 頭痛、倦怠感、のどの痛み、鼻水、咳、発熱 |
| 発熱 | 体温が異常に上昇する(40℃を超えることも) | 微熱~38℃程度(高熱が出る場合もあり) |
| 喉の痛み・咳 | 無 | 有 |
熱中症は高温環境での活動後に現れることが多く、症状はその環境から離れると徐々に改善することがあります。「手足がつる」「めまい」「皮膚の乾燥」「意識障害」などが特徴的です。また、喉の痛みや咳などの呼吸器症状がほとんど見られないことも大きな特徴です。
これに対し、夏風邪などのウイルス感染による症状は熱中症と異なり、喉の痛み、鼻水、咳などの呼吸器症状が現れます。また、エアコンの効いた室内でも症状が現れ、改善しないことが特徴です。同居の家族や周囲の人に同様の症状がみられる場合は、感染症の可能性が高くなります。
適切な対応のためには、これらの症状の違いをしっかりと認識し、医療機関での診察を迷わず受けることが重要です。特に高齢者や基礎疾患のある方は症状が重症化しやすいため、早めの対応を心がけましょう。
熱中症の予防・回復法
 暑い季節になると特に注意したいのが熱中症です。体温調節機能が乱れることで起こるこの症状は、適切な予防と早急な対応で回避することができます。熱中症は悪化すると命に関わる危険な状態となるため、日頃の予防が何よりも大切です。ここでは薬剤師の視点から、効果的な熱中症対策をご紹介します。
暑い季節になると特に注意したいのが熱中症です。体温調節機能が乱れることで起こるこの症状は、適切な予防と早急な対応で回避することができます。熱中症は悪化すると命に関わる危険な状態となるため、日頃の予防が何よりも大切です。ここでは薬剤師の視点から、効果的な熱中症対策をご紹介します。
水分補給に加えて塩分・ミネラル補給
熱中症予防の基本は、適切な水分と電解質(ミネラル)の補給です。汗をかくと体内の水分だけでなく、ナトリウムやカリウムなどのミネラルも失われます。
● 水分とミネラル補給のタイミング:のどが渇く前に、こまめに水分を摂取しましょう
● 飲む量の目安:運動時は15〜20分ごとに150〜250ml程度が目安です
● おすすめの飲み物:経口補水液、スポーツドリンク(塩分1〜2g/L、糖分4〜8%程度が理想)、麦茶に少量の塩を加えたものなど
アルコールやカフェインを多く含む飲料は利尿作用があり、かえって脱水を悪化させる可能性があるため避けましょう。また、高齢者は喉の渇きを感じにくいため、意識的に水分摂取するよう気をつけてください。
屋外では直射日光を避け、涼しい場所でこまめに休憩
外出時は熱中症のリスクが高まります。以下のような適切な対策を心掛けましょう。
● 日傘や帽子を活用し、直射日光を避ける
● 通気性の良い、吸湿・速乾素材の衣服を着用する
● 30分〜1時間ごとに涼しい場所で休憩をとる
● 首筋や脇の下など太い血管が通る場所を冷やす
特に高齢者や小さなお子さん、持病のある方は注意が必要です。また、血圧の薬や利尿剤などを服用している方は熱中症のリスクが高まるため、屋外活動の際は特に注意してください。
屋内ではエアコンを効果的に活用
室内でも熱中症は起こります。以下のような適切な室温管理を心がけましょう。
● 室温は28℃以下、湿度は60%以下を目安に管理
● 扇風機やサーキュレーターを併用して空気を循環させる
● カーテンやブラインドで直射日光を遮る
● 特に就寝時はエアコンの活用を検討(タイマー機能の利用も有効)
熱中症の症状がある場合、解熱鎮痛剤(ロキソプロフェンなど)の自己判断での服用は避けてください。これらの薬は体温調節機能を抑制し、熱中症を悪化させる可能性があります。また、発汗を抑制する抗コリン作用のある薬(風邪薬や花粉症の薬に含まれることが多い)も熱中症リスクを高めるため注意が必要です。
感染症の予防・回復法
 夏場に多い夏風邪などの感染症は、適切な予防と対策で症状を回避・軽減できます。特にコロナウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどが原因となることが多く、周囲への感染拡大を防ぐためにも正しい知識を持ちましょう。
夏場に多い夏風邪などの感染症は、適切な予防と対策で症状を回避・軽減できます。特にコロナウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどが原因となることが多く、周囲への感染拡大を防ぐためにも正しい知識を持ちましょう。
手洗い・うがい
感染症予防の基本は手洗い・うがいです。特に外出後や食事前には必ず行いましょう。
● 手洗いのポイント:せっけんを使い、指の間や手首まで丁寧に30秒以上
● うがいの効果的な方法:水でのうがいで口腔内の雑菌を洗い流した後、薄めたうがい薬でうがいする二段階方式
● マスク着用:飛沫感染予防に効果的
手指消毒用アルコールは、アルコール濃度70%以上のものが効果的です。ただし、ノロウイルスなどには効果が低いため、せっけんでの手洗いを基本としましょう。
バランスの取れた食事
免疫力を高めるためには、栄養バランスの取れた食事が重要です。以下のような食事をとることを意識してください。
● タンパク質(肉、魚、大豆製品など)を十分に摂取
●ビタミンC(柑橘類、キウイ、パプリカなど)の摂取
● ビタミンA(ニンジン、ホウレンソウなど)の摂取
● 発酵食品(ヨーグルト、納豆など)を摂取し腸内環境を整える
食欲不振時には消化の良いおかゆや温かいスープなどを少量ずつ摂りましょう。水分をしっかり摂ることも回復に重要です。サプリメントに頼り過ぎず、できるだけ食事から栄養を摂るよう心がけましょう。
十分な休息と睡眠
感染症からの回復には、以下のようなことをに意識しつつ十分な休息と質の高い睡眠が不可欠です。
● 発熱や倦怠感がある時は無理をせず休養する
● 快適な睡眠環境を整える(適切な室温、湿度、遮光)
● 就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を控える
● 規則正しい生活リズムを保つ
睡眠の質向上のために、カフェインを含む飲料の摂取は午後以降は控えめにしましょう。また、睡眠改善薬の長期連用は依存性の問題があるため、医師や薬剤師に相談しながら使用することをお勧めします。
症状によっては必要に応じた服薬
感染症の症状緩和には、以下のような適切な薬の使用が効果的な場合があります。
● 発熱時:解熱鎮痛剤(アセトアミノフェン製剤が一般的に安全)
● 喉の痛み:トローチ、うがい薬
● 鼻づまり:点鼻薬(長期連用は避ける)
● 咳:去痰薬、鎮咳薬
ただし、市販薬での自己治療で症状が改善しない場合は、医療機関を受診してください。複数の薬を併用する際は、成分の重複に気を配らなければなりません。特に総合感冒薬(かぜ薬)は多くの成分を含むため、他の薬との併用に注意が必要です。購入時に薬剤師へ相談するようにしてください。
お困りごとは薬剤師に相談
熱中症か感染症か、どちらに当てはまるか判断がつかない時や気になる症状がある場合はすぐに医師や薬剤師に相談をしましょう。特に以下のような症状がある場合は、早めの相談が重要です。
● 38℃以上の高熱が続く
● 激しい頭痛や意識がもうろうとする
● 呼吸が苦しい、息切れがする
● 水分が十分に摂れない
以上のような症状があったり、症状が改善しない場合は医療機関を受診するようにしてください。
薬剤師に気軽に相談する方法の一つとして、LINEの「つながる薬局」のサービスを活用してみませんか。熱中症や感染症の疑いがありどちらか判断が難しい場合や、受診するべきかどうかなどを知りたいとき、このサービスを利用して気軽に薬局の薬剤師に相談することができます。
「つながる薬局」は、LINEで友だち登録をするだけで簡単に利用開始できるサービスです。お好きな薬局をかかりつけ薬局として登録すると、熱中症対策や感染予防の相談など、薬局の薬剤師に直接チャットを通じて質問ができる機能を備えています。
また、「つながる薬局」は処方箋送信機能やオンライン服薬指導などの便利な機能もあります。これらのサービスを活用することで、安心して薬剤師に相談することができます。ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。
つながる薬局は、薬局への処方箋送信から健康・お薬相談、お薬手帳までLINEひとつでご利用いただけるサービスです!
つながる薬局を利用できる薬局はこちら!