執筆者・監修者:薬剤師
「専門の病院にかかってお薬が増えたけど、他のお薬との相性は?」
「薬局を使い分けているけど、何か問題ある?」
そんな不安を感じたことはありませんか?実はそれ、お薬の飲み合わせリスクにつながる可能性があります。今回は、薬剤師の視点から飲み合わせリスクと、予防のポイントをわかりやすく紹介します。
よくある飲み合わせトラブル
お薬の飲み合わせによるトラブルにはさまざまなものがありますが、大きく分けると相互作用により作用が強く出てしまうケースと、思ったような効果が出ないケースがあります。まずは、お薬の飲み合わせによって起こるトラブルについて解説します。
成分が重なり副作用が強く出る
複数の薬を服用していると、同じような作用をもつ成分が重複して含まれていることがあります。たとえば、普段から腰痛でアセトアミノフェンを含む痛み止めを服用されている方が、風邪をひいてアセトアミノフェンを含む風邪薬を服用してしまうと、アセトアミノフェンの過剰摂取となり、肝臓に負担がかかってしまいます。
一般的に解熱鎮痛薬やアレルギーに使う抗ヒスタミン薬などは、市販の風邪薬によく含まれている成分です。持病があって普段から薬を服用されている方が風邪薬を服用する場合は、自己判断で服用せずに、医師や薬剤師に確認するようにしましょう。
お薬の副作用については、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方は参考にしてみてください。
お薬の副作用とは?知っておくべき基本と対応するうえでのポイント
効果が弱まる、強く出すぎる
お薬の飲み合わせによっては、効果が弱まったり、強く出すぎたりすることがあります。たとえば、便秘薬である酸化マグネシウム製剤と鉄剤を同時に服用すると、鉄剤の吸収が妨げられ、効果が十分に得られないこともあるでしょう。また、片方のお薬の成分がもう一方のお薬の分解を阻害することで、血中濃度が上がり、副作用が出ることもあります。
めまい・眠気・胃の不調などが起こる
お薬の飲み合わせによって、ふらつきや強い眠気、胃のムカムカや痛みなどが起こることがあります。たとえば、風邪薬やアレルギー薬の中には、眠気を引き起こす成分が含まれており、睡眠導入剤やお酒と一緒に飲むと、眠気が強まりすぎて日中の活動に支障が出ることもあります。
お薬の飲み合わせによる影響は、人によって出方が異なります。同じお薬を飲んでも、体質や年齢、持病の有無、そのときの体調によって副作用が出やすい場合があります。お薬を服用したあとに「合わないかも」と感じたら、自己判断で服用を中止せずに、まずは医師や薬剤師に相談することが大切です。
飲み合わせトラブルが起こる理由
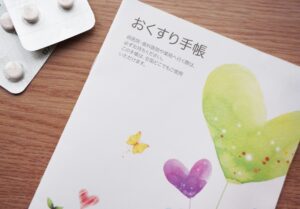 お薬の飲み合わせに関するトラブルは、医師や薬剤師が患者さんが飲んでいるお薬の情報を十分に把握できていないために起こります。ここからは飲み合わせトラブルが起こってしまう理由について解説します。
お薬の飲み合わせに関するトラブルは、医師や薬剤師が患者さんが飲んでいるお薬の情報を十分に把握できていないために起こります。ここからは飲み合わせトラブルが起こってしまう理由について解説します。
受診する医療機関や薬局が分散している
複数の病院や薬局を利用していると、処方されたお薬が重なったり、飲み合わせのリスクに気づけなかったりすることがあります。病院では紹介状などがない場合、他の病院への通院状況については患者さんやご家族からの聞き取りやお薬手帳の内容から把握しています。
マイナンバーカードの保険証を使うことで、他の医療機関の情報もある程度確認できるようになりましたが、情報の反映には1ヶ月程度タイムラグがあるため、最新の情報は確認できません。そのため、他の病院で同じ内容のお薬が処方されていることに気づかずに処方してしまうケースもあります。
お薬手帳の管理が不十分
お薬手帳を持っていても、記録が不完全だったり、持参し忘れたりすると、医師や薬剤師が正確な情報を把握できません。お薬手帳はすべての医療機関で同じものを使用するのが原則ですが、中には「医療機関ごとにお薬手帳は分けるもの」と勘違いされている方もいらっしゃいます。
お薬手帳を適切に活用できていないと、薬の重複や相互作用に気づかずに薬が処方されることがあります。お薬手帳はすべての医療機関の分を1冊にまとめ、常に最新の情報を記録することが大切です。
安心してお薬を飲むためにできること
お薬の飲み合わせによるトラブルを避けるためには、処方されたお薬だけでなく、市販薬やサプリメントなども含めて、いつも服用しているお薬の情報を整理しておくことが大切です。ここからは安心してお薬を飲むためにできることを紹介します。
お薬の情報はすべて医師・薬剤師に伝える
病院で処方されたお薬はもちろん、市販薬、サプリメントを含めて、現在服用しているものはすべて医師・薬剤師に伝えるようにしましょう。市販薬やサプリメントは気軽にドラッグストアなどで購入できる一方で、飲み合わせのリスクに気づきにくいという注意点があります。サプリメントや市販薬の情報は伝え忘れやすいため、メモにまとめておくと安心です。
通院先・薬局はなるべくまとめる
かかりつけの病院や薬局を1か所にまとめておくことで、服用している薬の管理がしやすくなります。病院は症状によってかかるべき診療科が変わってきますが、薬局は基本的に全国すべての医療機関の処方箋を受け付けているので、複数の病院にかかる場合でもお薬はかかりつけの薬局でもらうのがおすすめです。かかりつけ薬局を決めておくと、薬剤師が今飲んでいるお薬をすべて把握でき、必要に応じて処方医に情報提供するため、飲み合わせリスクの軽減にもつながります。
お薬手帳は一冊にまとめて毎回提示
お薬手帳は一冊にまとめ、すべてのお薬の履歴を記録しましょう。受診やお薬の受け取りの際には必ず提示することで、医療者が正確な判断をしやすくなります。紙のお薬手帳を忘れやすい方は、スマートフォンで管理できる電子お薬手帳を使うのもおすすめです。医療機関にかかる際は、必ずお薬手帳を持参するようにしましょう。
なお、電子お薬手帳ならLINEの「つながる薬局」のサービスがおすすめです。LINEのアプリがあれば新しいアプリをインストールする必要がなく、すぐにサービスを利用開始できます。「つながる薬局」の電子お薬手帳は、ご自身のお薬の履歴を管理することに加え、ご家族のお薬の履歴も共有・管理することができます。ご自身とお子さん、または離れて暮らすご家族がいる場合などでも、スマートフォン一つでまとめて管理ができるのでとても便利です。LINEで友だち登録後に、お好きな薬局をかかりつけ薬局として登録するとこの電子お薬手帳の機能を使えますし、さらに薬局での待ち時間を短縮できる処方箋送信の機能も備えているサービスです。ぜひご利用を検討してみてください。
つながる薬局は、薬局への処方箋送信から健康・お薬相談、お薬手帳までLINEひとつでご利用いただけるサービスです!
つながる薬局を利用できる薬局はこちら!
不安や疑問があれば、薬剤師に相談を
 服用中のお薬について、不安や疑問があれば薬剤師に相談してみましょう。お薬を飲み始めたあとに「いつもと違う」「体調がおかしい」と感じた場合は、我慢せずすぐに医師や薬剤師に相談してください。飲み合わせが原因で思わぬ副作用が出ている可能性があります。
服用中のお薬について、不安や疑問があれば薬剤師に相談してみましょう。お薬を飲み始めたあとに「いつもと違う」「体調がおかしい」と感じた場合は、我慢せずすぐに医師や薬剤師に相談してください。飲み合わせが原因で思わぬ副作用が出ている可能性があります。
体調の変化を見逃さず、早めに対応することが安全にお薬を使うための大切なポイントです。多くの方は「薬剤師に相談=処方箋がないとダメ」「忙しそうで聞きにくい」と感じてしまいがちですが、薬剤師はお薬のプロとして、患者さんが安心してお薬を服用できるようサポートしています。お薬のことを少しでも不安に感じたときこそ、気軽に薬剤師に相談してみましょう。
処方箋がなくても相談OK
薬局では、処方箋がなくてもお薬についての相談を受け付けています。市販薬やサプリメントの飲み合わせについての相談も可能です。相談は無料で受けられる場合が多いため、気になることがあれば積極的に話してみましょう。
飲み合わせや副作用の確認も可能
薬剤師は飲み合わせや副作用の確認もしています。「この薬とこの薬、併用して大丈夫?」「この症状、副作用かも?」といった不安があるときは、薬剤師に相談してみましょう。薬剤師は薬の成分や体の中での働きに詳しいので、安心して相談できます。
実際にあった相談事例
普段からかかりつけの内科で睡眠薬(ベルソムラ)を処方されているAさん。鼻の調子が悪く、耳鼻科を受診したところ、抗生物質(クラリスロマイシン)が処方されました。
かかりつけの薬局に耳鼻科の処方箋を持参したところ、薬剤師が耳鼻科で処方された抗生物質と普段から服用している睡眠薬が併用できないお薬であることに気づきました。耳鼻科の医師に睡眠薬を服用中であることを報告したところ、飲み合わせが問題ない抗生物質に変更になりました。
このように複数の病院を受診する場合でもかかりつけの薬局に処方箋を持参することで、薬剤師が飲み合わせを確認し、必要であれば処方の変更を医師に提案します。不安なことがある時は、ぜひ薬剤師を頼ってみてください。
お薬の飲み合わせについて気軽に薬剤師に相談する手段として、「つながる薬局」のサービスもおすすめです。LINEで「つながる薬局」を友だち登録して、お好きな薬局をかかりつけ薬局として登録するだけで、気になる症状や服用中のお薬のことなどについてLINEで気軽に相談できます。薬局への処方箋送信やお薬手帳の管理などにも活用できるサービスなので、気になる方はぜひ登録して使ってみてください。
つながる薬局は、薬局への処方箋送信から健康・お薬相談、お薬手帳までLINEひとつでご利用いただけるサービスです!
つながる薬局を利用できる薬局はこちら!




