執筆者・監修者:薬剤師
「秋のアレルギーは花粉以外にも原因がある?」
「秋のアレルギー症状の特徴は?」
「秋のアレルギーを予防・対処する方法は?」
秋の不調に悩む方であれば、上記のように感じることが多いのではないでしょうか。秋のアレルギーは花粉だけでなく、ダニやハウスダスト、昆虫など多様な要因が関わります。当記事では、秋に増える代表的なアレルギーの原因物質、症状の特徴、生活の中でできる予防・対処法を解説します。
最後まで読めば、自分に合った対策が見つかり、快適な秋を過ごす一歩を踏み出せるでしょう。
花粉だけじゃない!秋のアレルギーを引き起こす物質
秋のアレルギーは花粉だけでなく、屋内にも原因があります。代表的な秋の花粉にはブタクサ・ヨモギ・カナムグラがあり、飛散時期は8月から10月に集中します。
一方、室内では夏に繁殖したダニの死骸やフン・ハウスダストが症状を悪化させる原因です。また、ゴキブリやガなど昆虫の死骸や鱗粉も刺激源になります。秋にアレルギーを引き起こす主な原因は、以下のとおりです。
● ブタクサ・ヨモギ・カナムグラの花粉
● ダニの死骸やフン・ハウスダスト
● 昆虫の死骸や鱗粉
複数の要因が重なるため、適切な対策には原因の特定が欠かせません。
秋にアレルギーが発症する原因
秋のアレルギーは生活環境に潜むさまざまな要因が関与し、体調に影響を及ぼします。症状を繰り返さないためには、どのような原因が潜んでいるのかを理解しておくことが重要です。ここからは、秋のアレルギー発症に関わる代表的な原因について掘り下げて見ていきましょう。
秋に飛散する花粉の影響
秋の花粉症は、ブタクサやヨモギ・カナムグラといった植物の花粉が大きな原因です。これらは身近な環境に多く、飛散時期も長いため注意が必要です。代表的な秋の花粉の種類と飛散時期を、以下にまとめました。
● ブタクサ:8月~10月
● ヨモギ:8月~10月
● カナムグラ:8月~9月
秋の花粉は粒子が小さいため、気管支まで到達して症状がひどく出る傾向があります。春のスギやヒノキよりも影響が強く出ることがあり、咳や喘鳴(ぜんめい)など呼吸器系の症状につながる恐れがあります。
ダニとハウスダストによる影響
夏に繁殖するダニは、秋のアレルギーに大きく影響を与える要因です。高温多湿の環境で繁殖したダニは夏の終わりから死滅し、死骸やフンが秋に乾燥して舞い上がります。これがハウスダストとなり、アレルギー症状として鼻炎・喘息・皮膚炎などの症状を悪化させやすくなります。
屋内では、以下のようなアレルゲンにも注意が必要です。
● ゴキブリの死骸やフン
● 蛾(ガ)の鱗粉・死骸
● カビの胞子
これらが混ざり合ってアレルギーを引き起こす可能性があります。複数の屋内アレルゲンが重なると症状がひどくなることが多いため、清掃と換気による原因除去が重要です。
秋のアレルギー症状とは?見逃せないチェックポイント
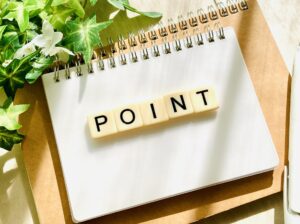 秋は気温や湿度の変化により体調が揺らぎやすく、健康を損ねるきっかけになります。症状の背景を知ることで早めの対応が可能となり、生活の質を保つことにつながります。ここでは、秋のアレルギー症状発症時に注目すべきチェックポイントについて確認していきましょう。
秋は気温や湿度の変化により体調が揺らぎやすく、健康を損ねるきっかけになります。症状の背景を知ることで早めの対応が可能となり、生活の質を保つことにつながります。ここでは、秋のアレルギー症状発症時に注目すべきチェックポイントについて確認していきましょう。
アレルギーによる症状
秋のアレルギーでは、鼻・目・喉・皮膚・呼吸器にさまざまな症状が現れます。代表的な症状は、以下のとおりです。
● 鼻:くしゃみ、透明でサラサラした鼻水、鼻づまり
● 目:かゆみ、充血、目やに(アレルギー性結膜炎)
● 喉・呼吸:喉の違和感、乾いた咳、喘息に類似した呼吸困難
● 皮膚:かゆみ、発疹、湿疹の悪化
これらの症状は、秋の花粉症だけでなくアレルギー性鼻炎や結膜炎、咳や喘息症状にもつながるため、早期の認識が重要です。症状が繰り返す場合は、医療機関での検査と対応を検討しましょう。
花粉?ダニ・ハウスダスト?の見分け方
秋のアレルギー症状では、症状の原因判断が重要です。屋外で過ごす際に症状が強まるようであれば、秋の花粉症が考えられます。一方で、室内でくしゃみや鼻づまりが繰り返される場合は、ダニ・ハウスダストによるアレルギーである可能性が高いです。
さらに、以下の視点で見分けられます。
● 花粉:季節性が明確で、天候変化や屋外滞在で反応しやすい
● ダニ・ハウスダスト:長引く症状で、掃除や換気後に悪化しやすい
症状が長時間続くようなら、具体的な原因を特定する診断を検討しましょう。
秋のアレルギーを予防する方法
 秋は気温差や生活環境の変化により、アレルギーを悪化させる要因が増えやすい季節です。日常生活の工夫によって症状の軽減が期待できるため、生活環境に応じた予防策を知ることが重要です。ここからは、秋のアレルギーを予防する実践しやすい方法を解説します。
秋は気温差や生活環境の変化により、アレルギーを悪化させる要因が増えやすい季節です。日常生活の工夫によって症状の軽減が期待できるため、生活環境に応じた予防策を知ることが重要です。ここからは、秋のアレルギーを予防する実践しやすい方法を解説します。
外出時の対策
秋の花粉やほこりは屋外活動に伴い体内に取り込まれやすいため、適切な対策が必要です。外出時の有効な対策を以下にまとめました。
● 外出時にはサージカルマスクやN95マスクなど高性能マスクを使用し、飛散粒子の侵入を抑制
● 花粉が付きにくい素材の服装を選び、帰宅後は衣服をはたいたり着替えたりして家に持ち込まない
● 手洗いとうがいを徹底し、目や鼻に触れる前に清潔を保つ
●外出前には花粉情報を確認し、飛散量が多い時間帯を避けて行動計画を立てる
これらの対策を組み合わせることで、外出時のアレルギー予防に役立ちます。
室内でのダニ・ハウスダスト対策
屋内ではダニやハウスダストがアレルギー症状を促進しやすいため、対策が重要です。具体的には、以下の対策が有効です。
● 布団やカーペット、ぬいぐるみなどをこまめに掃除機をかける
● 洗濯や天日干しでアレルゲンを減らす
● 湿度を30〜50%に保つために除湿器や換気を活用し、ダニの繁殖を抑制
● ベッドや枕は防ダニカバーで覆い、アレルゲンの侵入や拡散を防ぐ
● 空気清浄機(HEPAフィルター搭載)を使用して微粒子を除去
複数の対策を組み合わせることで、症状の軽減につながりやすくなります。
秋のアレルギーの適切な対処法
 秋のアレルギーは生活の質を下げやすく、早めの対処が欠かせません。症状を軽減するには適切な手段を知り、自分に合った方法を見極めることが大切です。ここからは、実際に取れる秋のアレルギーの適切な対処法について紹介します。
秋のアレルギーは生活の質を下げやすく、早めの対処が欠かせません。症状を軽減するには適切な手段を知り、自分に合った方法を見極めることが大切です。ここからは、実際に取れる秋のアレルギーの適切な対処法について紹介します。
市販薬で症状を抑える
秋のアレルギー症状を和らげる方法として、市販薬の使用は有効です。とくに抗ヒスタミン薬は鼻水やくしゃみを抑え、生活の質を維持しやすくなります。代表的な市販薬の有効成分および商品名は、以下のとおりです。
● フェキソフェナジン:アレグラFX
● ロラタジン:クラリチンEX
● エピナスチン:アレジオン20
これらは第2世代のアレルギー薬で眠気が少なく、安全性が高いとされた市販薬です。市販薬は症状緩和に役立ちますが、体質や持病により合わない場合もあるため、使用が長期に及ぶときは医師や薬剤師に相談すると安心につながるでしょう。
なお、市販薬を購入して使用するなら、「つながる薬局」のサービスの利用がおすすめです。「つながる薬局」であれば、LINEの友だち登録だけでサービスを利用開始することができ、お好きな薬局をかかりつけ薬局として登録すると、電子お薬手帳機能に市販薬の記録を残せるため便利です。
アレルギーの原因を診断してもらう
秋のアレルギーに対処するなら、アレルギーの原因を診断してもらうことも有効です。アレルギー源の特定には、以下の医学的な検査が有効です。
● 血液検査(特異的IgE抗体測定):採血だけで花粉・ダニなど複数のアレルゲンを同時判定、クラス0 〜 6の段階で感作の程度を評価
● 皮膚プリックテスト:前腕などにアレルゲン液を滴下し、専用の針で軽く刺して、約15~20分で赤みや膨疹(ぼうしん)の有無を確認、迅速な判定が可能
これらの検査結果を元に、症状を合わせて総合的に評価します。長引く症状や複数のアレルギーが疑われる場合は、専門医による診断と相談がおすすめです。
処方薬で対応する
処方薬を活用すれば、秋のアレルギー症状を効果的に抑えられます。アレルギー症状を抑えるのに使われる主な処方薬は、以下のとおりです。
● 抗ヒスタミン薬(内服):くしゃみ・鼻水などを緩和
● 点鼻・点眼薬:鼻づまりにはステロイド点鼻、目のかゆみには抗ヒスタミン点眼を使用
● 舌下免疫療法:スギなどのアレルギー源に対して体を慣らす根本治療。エキス錠を舌下に数年間継続投与し、症状の発生を抑制
これらの治療は併用によって相乗効果が期待でき、症状の重さ・ライフスタイルに合わせて選択することが重要です。
まとめ
秋のアレルギーは、ブタクサやヨモギなどの花粉だけでなく、ダニやハウスダスト・昆虫の死骸など多様な要因が関わります。鼻炎・咳・結膜炎といった症状は日常生活に影響を与えるため、適切な予防と対策が欠かせません。
マスクや掃除などの予防に加え、市販薬や処方薬・免疫療法など幅広い対応策を講じることも重要です。当記事を参考に、自身に合ったアレルギー対策を取り入れて、快適に過ごせる秋を実現してください。
「つながる薬局」のサービスであれば、電子お薬手帳機能で市販薬や処方薬の記録が残せます。秋のアレルギー対策で市販薬や処方薬を利用する方は、「つながる薬局」で記録を残しておきましょう。




