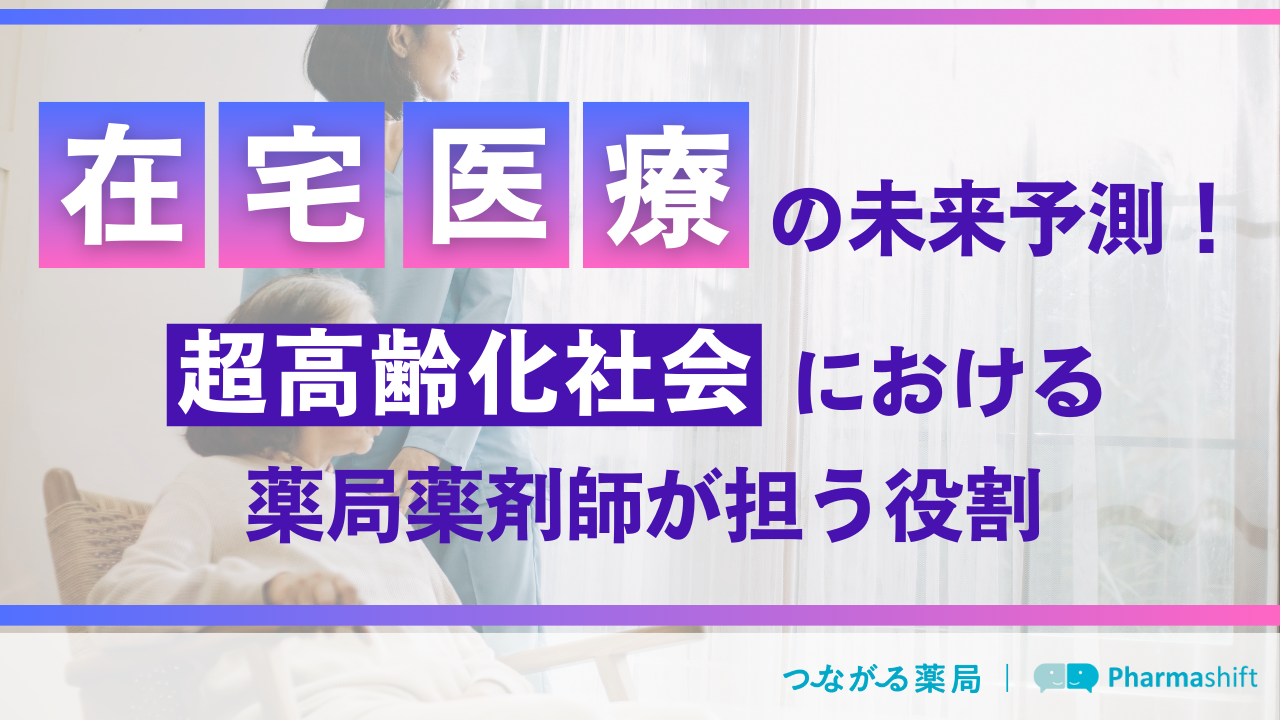「在宅医療は今後どうなる?」
「在宅医療に対応している薬局の状況は?」
「在宅医療において薬局に求められる役割は?」
上記のように考える薬剤師の方も多いのではないでしょうか?
高齢者人口の増加により、医療や介護の提供体制は大きな転換期を迎えています。地域での療養を支えるには、薬局薬剤師の関与がこれまで以上に重要となるでしょう。
本記事では、在宅医療を取り巻く最新動向や薬局の現状、今後の制度・役割の変化について解説します。薬局経営や地域医療に関心のある方は必見です。
目次
1.在宅医療の現状と今後の予測
日本の人口構造は大きく変化しており、特に高齢者の割合は年々増加しています。社会保障制度や地域医療体制にも影響をおよぼすこの人口動態は、医療提供のあり方にも直結しています。
ここでは、今後の在宅医療の動向について、詳しく見ていきましょう。
高齢者人口の増加は継続
高齢者人口の増加は今後も続き、2040年には約3,928万人に達すると見込まれています。※出典:厚生労働省「我が国の人口について」
これは総人口の約35%にあたり、過去に例のない水準です。背景には出生率の低下と平均寿命の延伸があり、医療や介護の需要もさらに高まります。高齢者人口の増加は、薬局薬剤師の在宅医療への関与を一層求める社会的変化を生み出す要因となるでしょう。
高齢者増にともなう在宅医療需要の増加
高齢者人口の増加にともない、在宅医療の需要も着実に増加しています。
厚生労働省の報告によれば、2023年の在宅医療を受けた患者数は約24万人に達し、2011年と比較して約13万人増加しています。※出典:厚生労働省「令和5年(2023)患者調査の概況」
さらに、2040年までには85歳以上の在宅医療需要が62%増加するとの推計も出されている状況です。※出展:厚生労働省「新たな地域医療構想の現時点の検討状況について(報告)」
これらのデータは、今後の在宅医療体制の強化が急務であることを示しているといえるでしょう。
2.在宅医療に対応する薬局の現状
地域医療の一端を担う薬局は、在宅医療の広がりに応じて役割を拡大しています。高齢化の進行とともに、患者のニーズも多様化しており、薬局の対応体制も変化を求められているのです。
ここでは、薬局の在宅対応に関する現状を詳しく見ていきましょう。
在宅医療へ対応している薬局の割合
在宅医療へ対応している薬局の割合は、2024年8月時点で全体の43.6%にとどまっています。※出典:日本保険薬局協会「調剤報酬等に係る届出の調査報告書」
半数以上の薬局が在宅医療に未対応であり、特に1店舗運営の薬局において届出率が低い傾向にあります。今後の需要増を考えると、対応薬局の割合拡大が急務といえる状況です。
在宅医療への対応が経営に与える影響
在宅医療への対応は、薬局経営において収益面での課題をともないます。個人宅を訪問する在宅患者訪問薬剤管理指導料では、1回あたり650点(6,500円)の報酬が得られます。しかし、移動時間や報告書作成などの業務負担を考慮すると、外来対応に比べて効率が悪いのが実情です。
また、在宅医療に対応するには、以下のような追加コストが発生します。
- 人件費の増加:24時間対応体制を整えるための人員確保が必要
- 設備投資:無菌調剤室の設置や緊急対応用の備品準備も検討
- 研修費用:在宅医療に対応できる薬剤師の育成や研修が必須
これらの要因により、在宅医療への対応は収益性の面で慎重な判断が求められます。しかし、地域包括ケアシステムの推進により、在宅医療の需要は今後も増加が見込まれます。薬局が地域医療に貢献するには、在宅医療への対応が不可欠であり、上記課題をふまえた経営戦略の一環として取り組む必要があるのです。
在宅医療に関する報酬の推移
在宅医療に関する報酬の推移を見てみると、介護保険制度における居宅療養管理指導費の単位数は、過去数回の改定でわずかな増加にとどまっています。たとえば、単一建物居住者が1人の場合の単位数は、平成30年度の507単位から令和3年度には517単位、令和6年度には518単位と、6年間で11単位の増加にとどまっています。このような推移から、今後も在宅医療に関わる大幅な報酬アップは見込めないでしょう。したがって、薬局が在宅医療に取り組む際には報酬面だけでなく、地域医療への貢献や患者満足度の向上といった非金銭的な価値も重視する必要があります。
3.在宅医療の未来を支えるために!薬局へ求められる役割
高齢化が進む社会において、在宅医療の安定的な提供は地域全体の課題となりつつあり、薬局には従来の役割を超えた新たな対応が期待されています。
ここでは、薬局が担うべき対応のあり方について解説します。
在宅医療に対応するための体制構築
在宅医療に対応するには、体制構築が必要です。まず必要な届出をおこない、薬剤師の人員配置を整えることが重要です。具体的には、在宅患者訪問薬剤管理指導の届出や、24時間対応体制の整備が求められます。また、訪問業務に対応できるよう薬剤師の教育や研修を実施し、スキルの向上を図ることも必要です。これらの取り組みにより、薬局が在宅医療に積極的に対応できる体制を構築し、地域医療に貢献することが期待されます。
多職種連携の推進
在宅医療では、薬局薬剤師が医師や看護師、介護職と連携し、チームの一員として動くことが求められます。患者の生活や病状に応じたきめ細かな支援をおこなうには、定期的な情報共有や役割分担が不可欠です。地域包括ケアシステムに積極的に参画することで、薬剤師は服薬支援だけでなく、地域全体の健康を支える存在として機能できます。今後は連携強化加算の届出やICTの活用も視野に入れた対応が求められます。
4.薬局の在宅医療推進に必須!ICT活用の重要性
在宅医療の担い手として薬局が機能するには、ICTの導入による業務効率化が不可欠です。
特に以下の点が経営面でも重要な役割を果たします。
- クラウド薬歴の活用
- 薬歴・報告書の作成を訪問先や移動中におこなえるため、時間の有効活用と業務量の平準化につながります。
- 多職種との情報共有
- 医師・看護師・ケアマネジャーとの連携において、リアルタイムでの情報共有が可能となり、対応力が向上します。
- 契約書作成~報告書提出までの総合支援サービスの利用
- つながる薬局が提供する「在宅サポート機能」は、契約書・計画書・報告書の作成を総合的に支援します。これにより患者ケアの充実と在宅対応の負担軽減が両立可能です。
- オンライン服薬指導や電子処方箋の導入
- 外出が難しい患者にも継続的な薬剤管理がおこなえ、地域の在宅医療体制の強化に寄与します。
ICTの導入は、薬局の在宅医療への参入・継続における重要な要素であり、持続可能な運営体制の確立に直結するでしょう。
5.在宅医療に携わる薬局薬剤師が備えるべき知識とスキル
在宅医療の現場では、薬剤師に求められる役割が拡大しており、患者の生活に深く関わる場面も増えています。変化する医療体制に対応するには備えるべき力があるため、その具体的なポイントについて詳しく見ていきましょう。
在宅医療に関する専門知識の習得
在宅医療において薬局薬剤師が果たす役割は多岐にわたります。患者の生活環境や健康状態を総合的に把握し、適切な薬物療法を提案するには、以下のような専門知識とスキルが求められます。
- 薬学的知識の深化
- 薬剤の効果・副作用・相互作用についての深い理解が必要です。特に在宅では、患者の生活習慣や他の治療との兼ね合いを考慮した薬物選択が求められます。
- 患者の生活環境を考慮した提案力
- 服薬アドヒアランスを高めるために、患者の生活リズムや嚥下能力、認知機能などをふまえた服薬方法の提案が重要です。
- 多職種との連携能力
- 医師・看護師・ケアマネージャーなど他の医療・介護職と情報を共有し、協働するスキルが求められます。
これらの知識とスキルを習得することで、薬局薬剤師は在宅医療の現場でより効果的に患者を支援することが可能となるでしょう。
コミュニケーション能力の向上
在宅医療では、薬局薬剤師が多職種と連携する場面が多く、円滑な連携には高いコミュニケーション能力が求められます。特に以下の力が重要です。
- 正確に伝える力
- 医師や看護師に薬剤の情報や患者の様子を的確に共有します。
- 傾聴と共感の姿勢
- 患者や家族の声を丁寧に受け止め、不安の軽減につなげます。
- 状況に応じた言葉選び
- 医療関係者・介護職・患者それぞれに適した伝え方が必要です。
こうした力を磨くことが、信頼され地域包括システムで活躍する薬剤師へとつながるでしょう。
6.まとめ
在宅医療の需要が増す中で、薬局薬剤師に求められる役割はより専門的かつ多様になっています。薬局においては、在宅医療に対応する体制整備やICTの活用、多職種連携を進めることで、地域医療に貢献する基盤を築けます。報酬だけにとらわれず、患者の生活を支えるという視点が今後ますます重要になるでしょう。変化する医療の現場に対応するためにも、在宅医療への一歩を踏み出し、実践に取り組んでみてください。