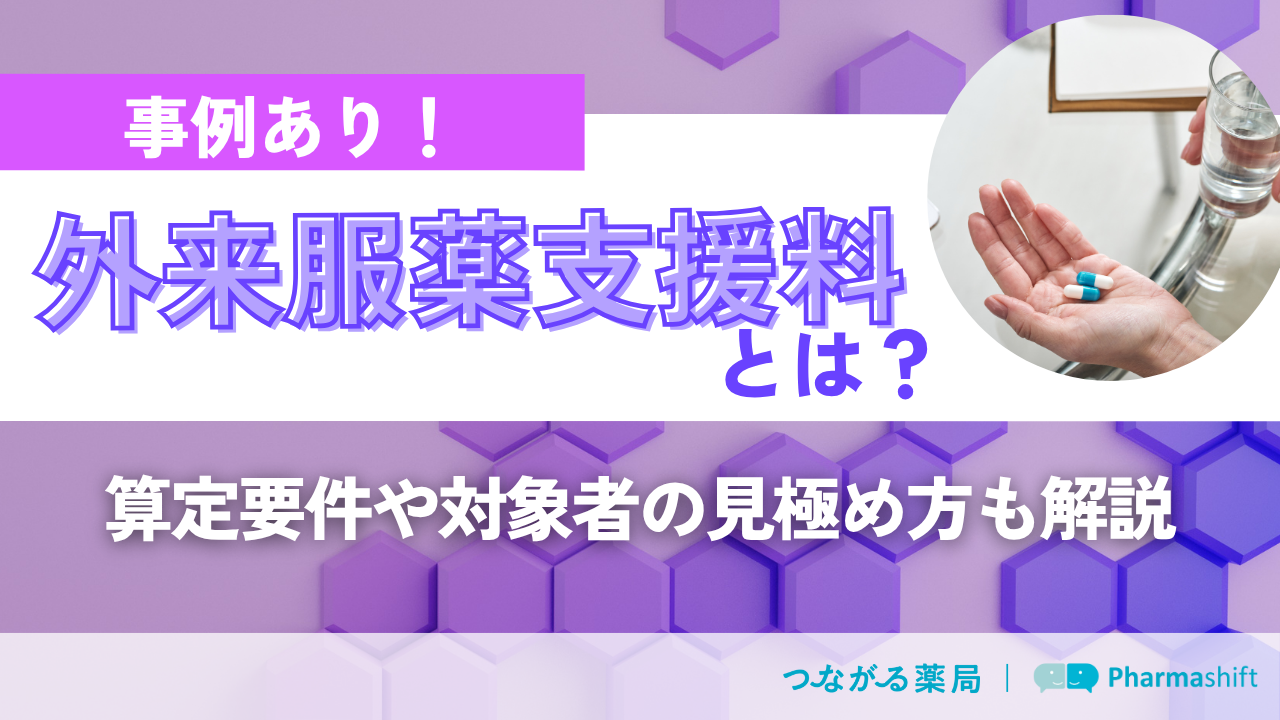執筆者・監修者:薬剤師
「外来服薬支援料ってどんなときに算定できるの?」
「支援料1と2の違いがいまいちわからない…」
「うちの薬局でも本当に算定できるのだろうか?」
薬局関係者のなかには、このような疑問や悩みを抱えている方もいるでしょう。
外来服薬支援料は、薬剤師が調剤後も継続的に患者さんをサポートする業務に対して評価される重要な点数です。当記事では、外来服薬支援料の概要と目的、1と2の違い、算定要件、具体的な算定事例、注意点などを解説します。最後まで読むことで、自薬局で適切に算定するための知識が身につき、薬剤師の専門性を活かした支援体制の構築に役立てられるでしょう。
目次
1.外来服薬支援料とは?
外来服薬支援料は、薬局における継続的な服薬支援の必要性を背景に2008年に設定された点数です。多剤服用や残薬がある方に対し、医師との連携を図りながら適切な服薬管理をおこなうことが求められています。医療資源の効率的活用と服薬アドヒアランス向上を目的とした制度といえるでしょう。
2.外来服薬支援料の点数・算定要件
外来服薬支援料には、患者さんの服薬状況や生活環境に応じて、異なる評価体系が設けられています。薬剤師による支援の内容や医師との連携体制により、求められる基準も変化します。
ここでは、算定要件や点数の仕組みについて見ていきましょう。
外来服薬支援料1
外来服薬支援料1は、服薬管理が困難な方を対象に、持参された医薬品や処方医の了解にもとづいて整理・一包化などの支援をおこなう点数です。上記支援に対し、月1回185点が算定できます。
算定要件は、以下のとおりです。
- 処方医の了解を得るか、支援後に医師へ情報提供
- 一包化や服薬カレンダーなどを用いて整理
- 薬歴には支援内容・理由・医療機関名などの記録が必要
なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している方や特別調剤基本料Bの算定薬局では算定できない点にご注意ください。
外来服薬支援料2
外来服薬支援料2は、服薬支援を必要とする方に対し、処方1回ごとに算定可能な点数です。一包化をはじめとした支援に対し、処方内容に応じて以下の点数が設定されています。
- 処方期間が42日以下:7日につき34点を加算
- 処方期間が43日以上:処方1回につき240点
対象となるのは、多剤併用や固形剤の服用が困難な方などで、薬剤師による一包化、服薬カレンダーの活用、服薬状況の継続的な確認が求められます。算定には、処方医の了解取得と、薬歴への支援記録が必須です。
なお、この点数は2022年度の診療報酬改定で廃止された「一包化加算」の後継として新設されました。従来の対物中心の加算から、患者さん支援に重点を置いた対人業務評価へと構造が見直されています。
3.外来服薬支援料1を算定する重要性
外来服薬支援料1の算定は、薬剤師が担う服薬支援の質を高め、患者さん対応の幅を広げるうえで重要です。加算取得によって業務の意義が可視化され、薬局全体の評価向上にもつながります。
ここでは、外来服薬支援料1を算定する重要性について解説します。
患者さんの安全な服薬をサポート
外来服薬支援料1では、一包化や服薬カレンダーでの支援により、患者さんの服薬ミスを減らし、安全性を高められます。この支援は、医薬品の整理だけでなく服用困難の原因を分析する対人業務でもあり、服薬管理の質を向上させるのに重要です。
また、算定要件として処方医の了解取得、または服薬支援後の情報提供が求められているため、医療連携を推進し、服薬事故防止にもつながります。
薬剤師の職能向上
外来服薬支援料1を算定する過程で薬剤師は、調剤後も服薬状況を継続的に観察し、問題解決を担う機会が得られます。このような実務経験は、薬剤師の臨床判断力や患者対応能力を高め、専門職としての職能向上につながります。
また、こうした支援を積み重ねることで、薬剤師の専門性が可視化され、職能が社会的に認知されていくでしょう。実績が蓄積されることで、将来的に薬剤師が担える業務の幅も広がる可能性があります。
地域支援体制加算への影響
外来服薬支援料1を算定すると、地域支援体制加算の実績要件の1つを満たせます。地域支援体制加算は、薬局が地域医療へ貢献する体制構築を評価するものであり、その重要な指標として組み込まれています。
地域支援体制加算の要件に必要な算定回数は、以下のとおりです。
- 地域支援体制加算1・2:1回/年間受付1万回
- 地域支援体制加算3・4:12回/年間受付1万回
算定に対して継続して取り組むことで薬局の地域評価が高まり、より幅広い支援提供の機会が得られるでしょう。
4.外来服薬支援料の算定事例紹介
外来服薬支援料は、患者さんの生活背景や服薬状況に応じて柔軟に対応できる点数です。薬剤師の判断と工夫によって多様なケースで算定できます。
ここでは、実際におこなわれた支援の具体的な事例を紹介します。
事例①|複数医療機関の処方薬を一包化して整理
複数の医療機関から処方された医薬品を一包化し、整理して算定したケースです。
患者さんが内科と整形外科で処方された医薬品を同時に持参され、医薬品が複数あるため飲み方がわからなくなることから、飲み忘れ防止のため一包化を実施しました。
算定には以下が要件となります。
- 他薬局が調剤した医薬品も対象とする整理
- 処方医の了解取得または服薬支援後に処方医へ情報提供
- 薬歴に支援内容・理由・処方医名・実施日を記録
このような介入により、多剤併用による服薬ミスのリスクを減らし、安全性の高い服薬が可能になります。
事例②|他薬局で調剤した医薬品をお薬カレンダーで整理
自薬局では調剤をおこなっていない患者さんが、他薬局で調剤された医薬品を持参した際に服薬支援をおこなったケースです。
認知機能が低下した高齢の方が、複数の薬局から交付された医薬品の管理に困って来局されました。すべての医薬品を確認し、朝・昼・夕・就寝前にあわせて一包化を実施したうえで、お薬カレンダーへセットしました。服薬のタイミングごとに色分けや位置分けをおこない、本人の理解度にあわせた工夫も取り入れた支援を実施しています。
この支援は、以下の条件を満たすことで算定が可能です。
- 他薬局で調剤された医薬品を含む整理をおこなったこと
- 一包化やお薬カレンダーを活用した服薬支援を実施したこと
- 処方医の了解取得、または支援内容の情報提供をおこなったこと
- 支援理由・内容・医療機関名・実施日などを薬歴に記録したこと
結果として、服薬ミスが減少し、服薬継続の安定性が確保されました。
5.外来服薬支援料算定時の注意点
外来服薬支援料は有用な加算である一方で、算定にはいくつかの制限や条件が設けられています。制度の理解が不十分なままでは、誤った算定や返戻のリスクも生じかねません。
ここでは、算定時に注意すべき要点を確認していきましょう。
処方医の了解、または情報提供が必要
外来服薬支援料1を算定するには、医師との適切な情報連携が不可欠です。制度上は、支援前に処方医の了解を得る、または支援後に情報提供をおこなういずれかの対応が要件とされています。
ただし、支援内容が処方薬の服薬方法や整理、一包化などに関わる場合は、原則として事前に処方医の了承を得ておく方が望ましいでしょう。あらかじめ意図を共有しておくことで、不要な誤解を避け、連携の信頼性を高める結果につながります。
在宅患者には算定できない
訪問薬剤管理指導を実施している場合、外来服薬支援料1は算定できません。訪問薬剤管理指導とは、定期的な在宅訪問において服薬状況の確認や薬学的管理をおこなうものであり、支援内容がすでに包括されています。また、他の薬局が訪問支援をおこなっている場合も同様に算定できません。算定前に患者さんの状態や他薬局の関わりを確認することが重要です。
特別調剤基本料を算定する薬局では算定できない場合がある
外来服薬支援料1は、調剤基本料の区分によって算定可否が異なります。特別調剤基本料Aを算定する薬局では、敷地内の医療機関が交付した処方箋にもとづき調剤した医薬品に対しては、原則として算定できません。また、特別調剤基本料Bを届け出ている薬局は、すべての方に対して算定が認められていません。上記のように、制度上の要件を満たしていない場合には誤算定となるため、自薬局の基本料を把握したうえで算定しましょう。
6.まとめ
外来服薬支援料は、薬剤師が調剤後も継続して患者さんを支える取り組みを評価する点数です。服薬アドヒアランスの向上や多剤併用によるリスク低減に直結し、安全な薬物療法の実現につながります。算定要件や留意点を正しく理解し、日常業務に支援を取り入れることで、地域医療に貢献する薬局づくりが進むでしょう。当記事の内容を参考に、現場での具体的な算定と支援に活かしてください。