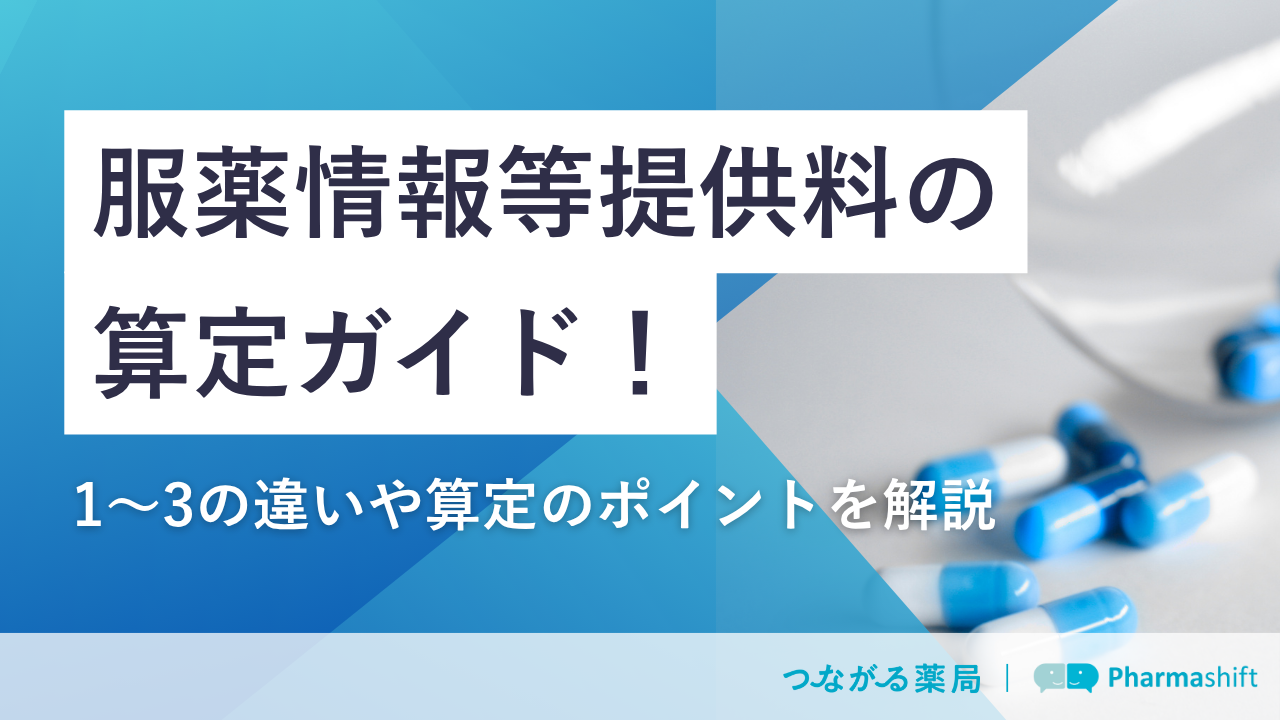執筆者・監修者:薬剤師
「服薬情報等提供料の算定要件は?」
「算定上の注意点は?」
「一緒に取れる点数はある?」
調剤報酬改定や業務の複雑化により、こうした疑問を抱く薬剤師も増えているでしょう。
服薬情報等提供料は、制度の理解と実務対応を両立させることで確実な算定が可能となり、薬局の価値向上につながる点数です。
当記事では、服薬情報等提供料の概要や1〜3区分の違い、2024年改定の内容を解説します。さらに、算定もれを防ぐ実務上の注意点や、他加算との併用による効率的な運用方法も紹介します。
最後まで読めば、制度を正しく理解でき、日々の薬局業務に組み込むことで、地域連携強化と薬剤師の専門性発揮につなげられるでしょう。
目次
1.服薬情報等提供料とは?概要と2024年改定のポイント
薬剤師による情報提供が医療の質向上につながる中、服薬情報等提供料の役割はますます重要になっています。正確な算定のためには、制度の目的や仕組みを理解することが欠かせません。
ここでは、制度の全体像と最新の改定内容を確認していきましょう。
服薬情報等提供料の概要
服薬情報等提供料は、薬局の“対人業務”を評価するために創設されました。
当制度は、患者さんの服薬継続や副作用対応等を支援し、文書提供により医師や介護職と薬剤師が連携することを促す仕組みです。設立目的は、医薬品適正使用の推進と薬局の専門性向上にあります。薬剤師が調剤後のフォローに注力しやすくする点数設定になっている点も特徴的です。
2024年調剤報酬改定のポイント
リフィル処方箋に対応した情報提供が可能となり、算定の対象が拡大しました。
服薬情報等提供料2は、従来の「薬剤師判断による医療機関への提供」(イ)に以下が加わり、細分化されています。
- 「リフィル調剤後の処方医への情報提供」(ロ)
- 「介護支援専門員への情報提供」(ハ)
これにより、薬剤師判断の幅が広がり、フォローアップ業務の質を対外的に明確化できるようになりました。
上記改定を活かすため、薬局の現場では各区分の業務フローを整理し、業務効率や算定精度を高めることが求められています。
2.服薬情報等提供料1~3の違いと算定要件
服薬情報等提供料は、以下のように区分ごとに算定の前提条件や報告対象、算定回数が区別されています。
| 服薬情報提供料区分 | 前提条件 | 報告対象 | 算定回数 |
| 1 | 医療機関の求め | 医療機関 | 月1回まで |
| 2 | 薬剤師判断・リフィル・介護支援 | 医療機関またはケアマネ | 月1回まで |
| 3 | 入院前の情報提供 | 入院予定先の医療機関 | 3か月に1回まで |
以下では、3つの区分ごとの要件や特徴について確認していきましょう。
服薬情報等提供料1の要件(医療機関の求め)
服薬情報等提供料1は、医師や医療機関の求めに応じて薬剤師が文書で情報提供をおこなう際に算定されます。この点数は、医師との連携を通じて処方の適正化や服薬支援を実現することを目的としています。
算定に必要な主な要件は以下のとおりです。
- 医療機関からの情報提供依頼があること
- 患者さんの同意を事前に得ていること
- トレーシングレポートなどの文書で報告すること
- 月1回を限度に30点を算定可能
明確な依頼に基づいていることが要件であり、薬剤師の判断だけでは算定できません。
服薬情報等提供料2の要件(薬剤師判断・リフィル・介護支援)
服薬情報等提供料2は、薬剤師の判断により必要性が認められた場合に、医療機関や介護支援専門員へ文書を用いて情報提供することで算定できます。2024年の改定で区分が細分化され、リフィル処方や介護連携にも対応可能となりました。
算定に必要な主な要件は、次のとおりです。
- 提供先が医師または介護支援専門員であること
- 情報提供の必要性を薬剤師が判断していること
- 患者さんの同意を取得していること
- 文書での情報提供がおこなわれていること
- 月1回を上限に20点が算定可能
薬剤師の介入が診療やケアに役立つよう、適切に点数を活用することが大切です。
服薬情報等提供料3の要件(入院予定患者向け)
服薬情報等提供料3は、入院予定の患者さんの医療連携を支援するために創設された算定項目です。保険医療機関からの依頼があった場合に限られ、薬剤師の判断だけでは算定できません。
主な算定要件は、以下のとおりです。
- 医療機関からの求めがあること
- 患者さんの同意を取得していること
- 患者さんの服用薬を他薬局や医療機関の情報も含め一元的に把握していること
- 必要に応じて持参薬整理をおこなっていること
- 文書で入院予定先に情報提供していること
- 3か月に1回を上限に50点が算定可能
医療機関との円滑な連携構築に役立つ点数であり、適切な対応が求められます。
3.服薬情報等提供料の算定もれを防ぐ!実務上のポイントと注意点
服薬情報等提供料を適切に算定するには、制度上のルールだけでなく、日々の業務における実務対応が不可欠です。見落としや誤算定を防ぐために、押さえておきたい基本事項を確認していきましょう。
同時算定のルール
服薬情報等提供料における同時算定のルールの把握は、正確な算定と算定もれ防止に直結します。
算定対象となる加算と併算定可否は、以下のとおりです。
- かかりつけ薬剤師指導料など一部薬学管理料とは併算定不可
- 他の薬学管理料(特定薬剤管理指導加算や乳幼児服薬指導加算など)との併算定は可能
同じ内容を同一医療機関へ提供した場合は併算定できませんが、異なる目的や相手先であれば月1回ずつ算定できます。適切な組み合わせを理解し、算定もれを防ぎましょう。
文書に記載することと保存方法
服薬情報等提供料の適正な算定には、文書作成と保存方法の厳守が欠かせません。
薬局では、以下の手順を整備する必要があります。
- 文書へ記載すべき内容を明確化(服用薬・服薬状況・副作用分析など)
- 薬剤服用歴に文書の写し等を添付し保存(電子・紙媒体問わず)
- 保存期間を制度にあわせて管理(算定の根拠として保持)
文書と保存体制を整えることで、算定もれや監査リスクを回避できます。
4.服薬情報等提供料の効率的な算定事例
服薬情報等提供料は、他の加算と組み合わせることで効率的な算定が可能です。薬局の業務に自然に組み込む工夫が求められるため、活用事例を通じて実践的な視点を確認していきましょう。
特定薬剤管理指導加算との併用
服薬情報等提供料は、特定薬剤管理指導加算と組み合わせて算定が可能です。両加算を算定するポイントを明確にすれば、併算定が可能になります。
明確化するポイントは、以下のとおりです。
- 特定薬剤管理指導加算で扱うのは「ハイリスク薬に対する専門的指導」
- 服薬情報等提供料では「服薬状況や副作用などを医師へ共有」
ハイリスク薬の副作用評価や服用継続支援を特定薬剤管理指導加算で、医薬品全体の服薬状況を文書により共有すれば服薬情報等提供料として算定できます。
服薬フォローアップとの併用
服薬フォローアップとの併用により、服薬情報等提供料の算定を自然に実現可能です。患者さんへのフォローアップ中に得られた有益な情報を文書化して医師へ報告すれば、薬局業務の流れに組み込めます。
算定に必要な流れは次のとおりです。
- フォローアップで服薬状況や体調変化を把握する(例:服薬継続、副作用の訴え)
- 記録内容を薬剤服用歴に詳細に記載する
- 得られた新情報を文書化し、処方医へ提供する
算定は月1回までのため、提供内容と時期の管理が重要です。
なお、「つながる薬局」であれば、患者さんへの服薬フォローをサポートする機能があります。メッセージのテンプレート登録や、患者さんがボタンをタップするだけで返信できる選択式の回答ボタンなど、充実したメッセージ機能を備えています。
LINEによる効率的な服薬フォローを取り入れたい方は、「つながる薬局」の「服薬フォロー機能」をご確認ください。
地域支援体制加算実績への反映
服薬情報等提供料は、地域支援体制加算の実績要件にも組み込まれており、薬局の地域医療への貢献度を数値で示す指標としても機能します。
令和6年度の調剤報酬改定では、地域支援体制加算に必要な服薬情報等提供料の算定実績が以下のように明文化されました。
- 地域支援体制加算1・2:30回以上/年間受付1万回
- 地域支援体制加算3・4:60回以上/年間受付1万回
これにより、適切に服薬情報等提供料の算定を継続すれば、地域支援体制加算の算定へとつながります。
5.まとめ
服薬情報等提供料は、薬剤師の専門性を活かし、医師や介護職との連携を強化するための重要な点数です。適切な区分選択と算定要件の理解により、業務効率と医療の質向上の両立が期待されます。また、他の加算との併用や記録の工夫を通じて、地域医療への貢献実績としても有効に反映されます。当記事を参考に、点数を正しく活用し、地域医療に貢献する薬局運営を目指してください。