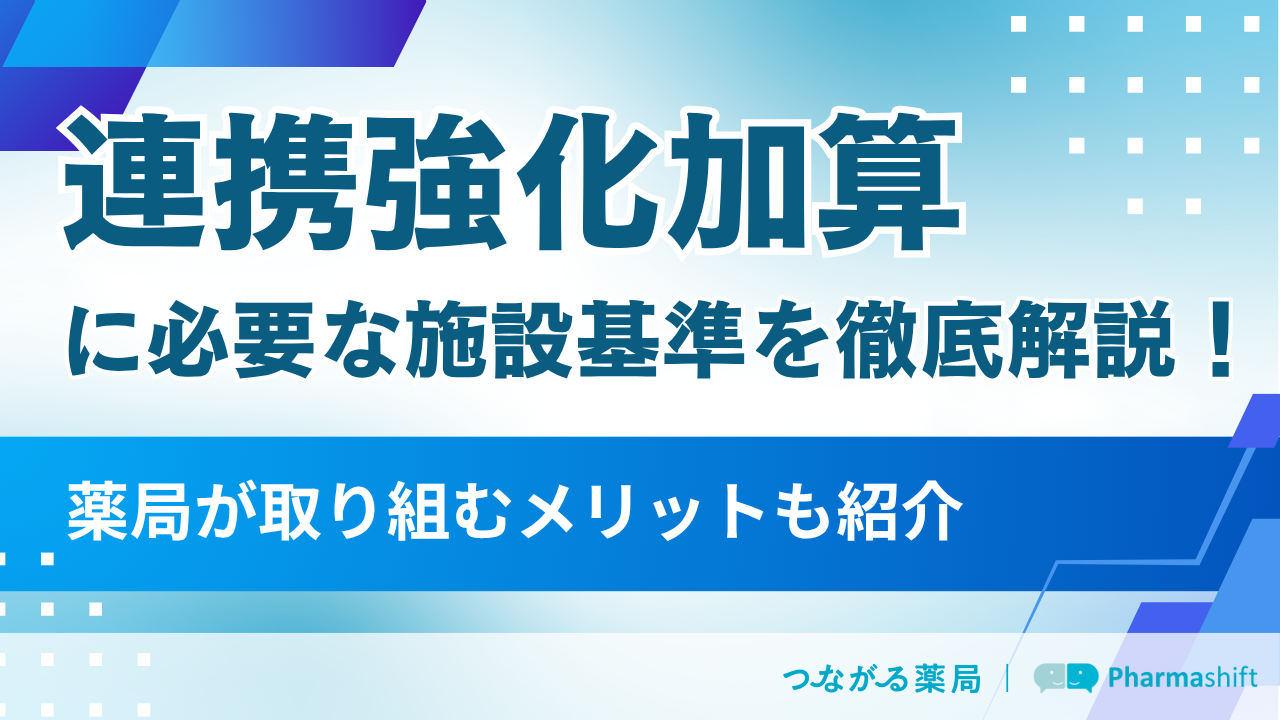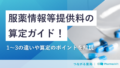執筆者・監修者:薬剤師
「連携強化加算ってなに?」
「何をすれば連携強化加算は算定できる?」
「連携強化加算を算定するメリットは?」
こうした疑問を抱える薬局経営者や薬剤師の方もいるでしょう。
連携強化加算は、災害や感染症拡大時にも医薬品を安定供給できる薬局を評価する制度です。2024年度の診療報酬改定により点数が引き上げられ、要件も見直されたことで、算定のハードルと意義が大きく変化しました。
当記事では、連携強化加算の仕組みから取得に必要な施設基準、取得によって得られるメリットを解説します。最後まで読めば、今後の薬局経営において連携強化加算をどのように活かすかの方向性が見えてくるでしょう。
目次
1.連携強化加算とは?薬局に求められる背景と目的
連携強化加算は、災害や感染症の拡大といった有事の際にも、医薬品の供給を安定的に維持できる薬局を評価する制度です。2022年度に創設され、2024年度の診療報酬改定では点数が2点から5点に引き上げられました。加算導入の背景には、新型コロナウイルスの感染拡大によって、地域医療の継続性が大きく揺らいだ経験があります。
特に次のような課題が明らかとなりました。
- 医療機関による外来・入院対応の大幅な制限
- 医薬品の供給が一部地域で滞った事例
- 高齢者施設や在宅患者への支援体制の不足
これらの課題をもとに、薬局は日常的に地域との連携を強化し、有事に備えた対応力を高める役割を期待されるようになりました。
2.連携強化加算における2024年調剤報酬改定での変更点
2024年の調剤報酬改定で、連携強化加算は大きく見直されました。
加算点数が従来の2点から5点へと引き上げられ、評価の重みが強まりました。
改定内容には次のようなポイントがあります。
- 点数が2点→5点に増額
- 地域支援体制加算の届出不要となり、算定ハードルが低くなる
- オンライン服薬指導の体制整備が新たな要件として加わる
これにより、薬局は非常時だけでなく平時からICTを活用した対応力整備が重要となっています。調剤報酬改定による変更は、薬局が地域医療の中核的存在として継続的に役割を果たすための仕組み強化といえます。
3.連携強化加算の施設基準①|感染症発生時に備えた体制
感染症が拡大した際にも地域での医薬品供給を維持するには、薬局自らが対応力を高めることが求められます。継続的に医療を提供できる体制を整えるには、平時からの備えが不可欠です。
ここでは、感染症発生時に備えた体制構築のポイントについて解説します。
第二種協定指定医療機関の指定
第二種協定指定医療機関は、感染症法改正に基づく医療措置協定で、薬局が都道府県知事から「自宅療養者等への医療の提供」を担う役割を正式に認められる制度です。指定の目的は、感染症発生時に薬局が公費負担の医療提供をおこなえる体制を整えることにあります。
指定までの流れは、以下のとおりです。
- 都道府県による協定締結協議を実施
- 協定書に押印し、正式に協定を結ぶ
- 指定書を受領し、薬局名が公表
これにより薬局は、地域の感染対応拠点として機能することが可能になります。
研修・訓練体制の整備
連携強化加算の施設基準では、薬局職員の実務対応力を高める研修・訓練の実施が義務付けられています。
対象となる研修・訓練は、以下のとおりです。
- 感染症に関する最新の科学的知見に基づいた研修を年1回以上実施
- 新型インフルエンザ等感染症等に備えた訓練を年1回以上実施
計画的な実施により、薬局は非常時にも地域医療の一端を担える体制を確立できます。
感染症発生時に備えた備蓄・提供体制
感染症発生時に備え、薬局は必要な物資をあらかじめ備蓄し、提供体制を整えておく必要があります。
対象となる資材や医薬品は、以下のとおりです。
- 個人防護具(ガウン・手袋・フェイスシールドなど)
- マスクや消毒液などの感染防止用品
- 要指導医薬品および一般用医薬品
- 体外診断用医薬品(抗原検査キットなど)
これらは発生時だけでなく、平時から安定して提供できる体制を構築することが求められます。
4.連携強化加算の施設基準②|災害発生時に備えた体制
大規模な自然災害が発生すると、医療提供体制の継続が困難になる恐れがあります。地域の薬局が機能を保ち続けるには、事前の備えと役割の明確化が欠かせません。
ここでは、災害時に備えるために薬局が整えるべき体制について見ていきましょう。
医薬品供給および薬局機能を維持する体制の整備
災害時においても薬局が医薬品供給の拠点として機能し続けるため、平時から体制整備が求められます。
具体的な取り組みは、以下のとおりです。
- 自治体の要請に応じて避難所や救護所へ医薬品を供給する体制を構築
- 調剤所設置のための人員派遣や設備準備の計画を策定
- 夜間・休日など開局時間外も含め、在宅・調剤対応が可能な体制を地域と協議して確保
こうした備えが薬局の社会的信頼を高め、連携強化加算の評価にもつながります。
災害対応訓練の計画策定と実施
災害時に薬局が役割を果たすには、平時から状況に応じた対応訓練を計画・実施する必要があります。
具体的な対策は、以下のとおりです。
- 被災状況に応じた応急対応を学ぶ社内研修を実施
- 地域の協議会や災害訓練に年1回程度参加する計画を立案
- 薬剤師会や行政と連携し、実践的な訓練を実施する体制を確保
このような計画的な訓練は、災害発生時の薬局機能の維持に直結するでしょう。
5.連携強化加算の施設基準③|災害・新興感染症に対する体制整備の周知
連携強化加算の施設基準では、構築した体制を薬局内だけでなく、地域に向けて明示することが求められます。
体制整備の内容は、以下の方法で広く周知します。
- 保険薬局や同一グループの公式ウェブサイトに掲載
- 地域の行政機関が管理する防災・感染対策ページへの情報提供
- 薬剤師会のポータルサイト等における公開
周知の徹底により、住民の安心感と行政との信頼関係を高める効果が期待されます。
6.連携強化加算の施設基準④|災害・新興感染症に対する手順書の作成
連携強化加算の施設基準では、災害や新興感染症発生時に備え、薬局ごとに状況別の対応手順書を整備することが求められます。
手順書には、緊急時に職員が迷わず行動できるよう、以下のような判断基準を含めておく必要があります。
- 対面困難時にオンラインや電話で服薬指導をおこなう条件
- 患者の状態に応じた医薬品の配送対応可否の基準
- 医薬品の優先対応が必要な患者の見極め方
全職員が内容を把握し、平時から共有体制を整備することが重要です。
7.連携強化加算の施設基準⑤|オンライン服薬指導の体制整備
オンライン服薬指導を適切におこなうには、制度に準拠した体制整備が不可欠です。
厚生労働省の実施要領や通知に基づき、以下の対応が求められます。
- 通信環境やカメラ・音声の安定性を確保する設備整備
- 保険薬剤師に対する操作研修や実務対応の教育実施
- 最新ガイドラインを踏まえたセキュリティ対策の実施
これらを講じることで、安全かつ継続的なオンライン服薬指導が可能となります。
オンライン服薬指導を手軽に実施したいなら、「つながる薬局」が便利です。
「つながる薬局」のオンライン服薬指導機能は、予約の管理から服薬指導後の決済機能まで備えています。患者さんはLINEを通じて利用できるため、特別なアプリのダウンロードは不要です。
詳しくは「薬局経営者・薬剤師が知っておきたいオンライン服薬指導」をご確認ください。
8.連携強化加算の施設基準⑥|要指導医薬品・一般用医薬品の販売
連携強化加算では、新型インフルエンザ等感染症の発生時に備え、薬局で必要な医薬品を販売できる体制が求められます。
対応すべき医薬品や検査キットの種類は、以下のように多岐にわたります。
- 要指導医薬品および一般用医薬品
- 発熱や咳など症状別に対応可能な市販薬
- 感染症対応用の体外診断用医薬品(抗原検査キットなど)
健康サポート薬局の48薬効群を参考に、必要に応じた品目を取りそろえる姿勢が評価されます。
9.薬局が連携強化加算を取得するメリット
連携強化加算の取得は、単なる点数加算にとどまらず、薬局が担う地域医療の価値を高める取り組みです。
薬局が連携強化加算を取得する主なメリットは、次のとおりです。
- 災害時や感染症流行時における対応力の強化
- 行政・医療機関との信頼関係の構築
- 地域住民からの認知度や信頼性の向上
収益向上とともに、薬局の社会的意義を再定義する契機となるでしょう。
10.まとめ
連携強化加算を取得することで、薬局は災害や感染症拡大時にも医薬品を安定供給できる体制を整え、地域の安心を支える存在となれます。ICT活用や医薬品の備蓄・販売体制、災害時対応まで幅広く求められるため、算定に向けた取り組みは薬局の機能強化にも直結します。加算の取得は点数向上だけでなく、地域との信頼構築や社会的価値の向上にもつながる重要な取り組みです。当記事を参考に、今後の薬局経営に活かしてください。