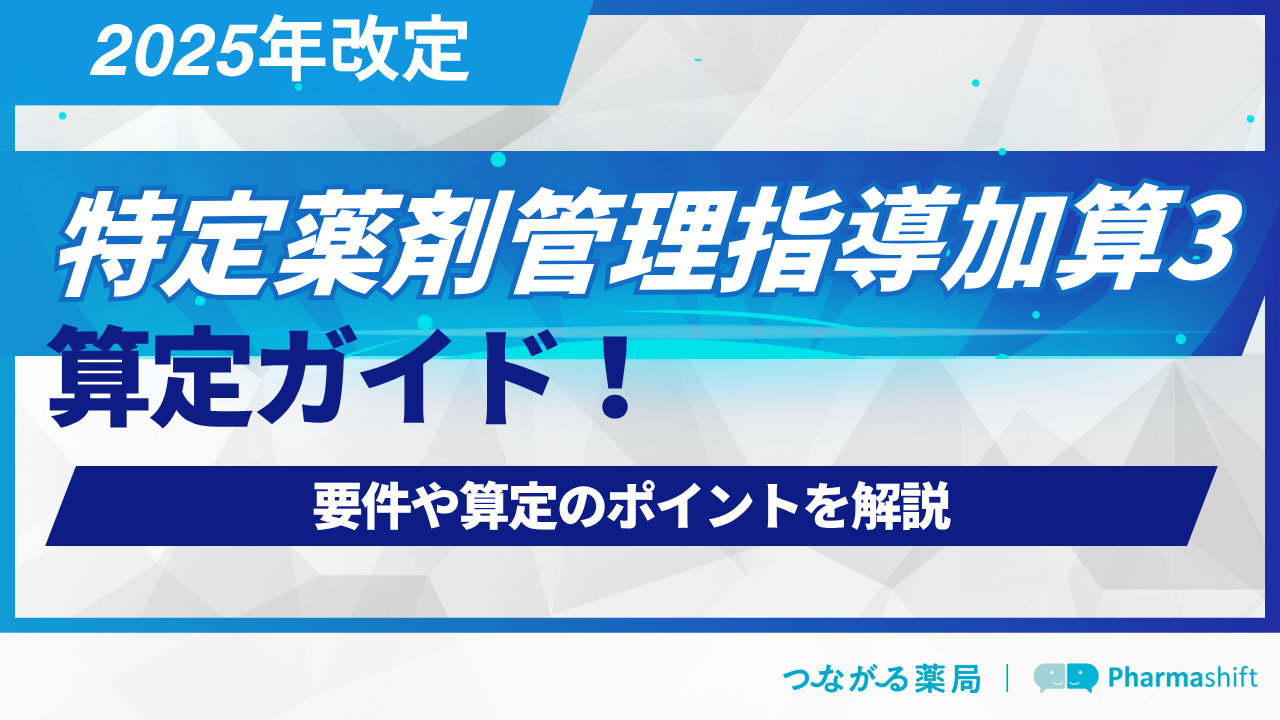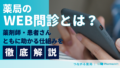執筆者・監修者:薬剤師
特定薬剤管理指導加算3は、2024年度改定で新設された薬局向けの加算制度です。
薬剤師の対人業務の質を評価する制度として注目を集めています。
しかし、以下のように感じている方もいらっしゃるでしょう。
「特定薬剤管理指導加算3の算定要件は?」
「2025年改定で何が変わった?」
「算定する際の注意点は?」
当記事では、制度の概要から「イ」「ロ」それぞれの算定要件、薬歴・レセプトの記載内容、対象医薬品の確認方法まで網羅的に解説します。
2025年中間改定での点数見直しや併算定時の注意点も整理し、薬局業務に役立つ情報を紹介しています。最後まで読めば、加算の理解が深まり、薬局での算定判断や対応に自信を持って取り組めるようになるでしょう。
目次
1.特定薬剤管理指導加算3とは?目的と仕組みの基本を解説
特定薬剤管理指導加算3は、薬剤師が特定薬剤の適正使用に向けた指導をおこなった際に評価される加算です。
制度創設の背景には、対物業務から対人業務への転換と、高リスク薬に対する説明責任の明確化があります。
対象となるのは、RMP資材を活用した副作用リスクなどの説明をおこなう場合(イ)と、選定療養や供給不足による薬剤変更時に情報提供をおこなう場合(ロ)です。2025年改定では「ロ」の点数が5点から10点に増え、薬剤師の負担と専門性に見合った評価が実現しました。服薬指導の質を高め、患者さんの安心と安全を支える制度として、薬局現場での意義は大きいといえるでしょう。
2.特定薬剤管理指導加算3の算定要件
薬剤師による服薬指導の重要性が高まるなか、特定薬剤管理指導加算3は業務内容に応じて異なる評価が設けられています。適切に算定するには、各区分に定められた要件を正しく理解する必要があります。
ここでは、加算の区分ごとの要件を詳しく見ていきましょう。
イ(5点)の算定要件
特定薬剤管理指導加算3の「イ」は、RMP(Risk Management Plan)資材などを用いて、安全性に関する指導をおこなった場合に評価される加算です。
制度上の算定要件は、以下のとおりです。
- 医薬品の初回処方時に、患者さん向けRMP資材を用いて副作用や注意点などの情報提供をおこなうこと
- または、緊急安全性情報や安全性速報が発出された医薬品について、安全管理上の必要な情報を対面で説明すること
- 服薬指導の記録として、薬歴に使用資材や説明内容の要点を明記していること
- 同一薬剤については初回算定1回限りであること
上記の条件を満たすことで、薬剤師による安全性確保の取り組みが報酬として認められる仕組みとなっています。
ロ(10点)の算定要件
特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は、薬剤師が医薬品の選択または供給不安定に関する説明・指導をおこなった場合に評価されます。制度の意義は、患者さんが適切に薬剤を選び、安全な薬物治療を継続するために必要な情報提供を促す点にあります。
算定要件は、以下のとおりです。
- 後発医薬品がある先発品(選定療養対象)を患者が選ぼうとする際、先発・後発の違いや負担内容を調剤前に説明していること
- または、医薬品供給が安定せず、前回と異なる銘柄に変更する必要がある際、変更理由や影響を患者に伝えていること
- 算定は、当該医薬品が最初に処方された1回に限り1回のみ
- 薬歴には説明内容の要点を明記し、レセプト摘要欄には供給理由や変更銘柄名を記載
これらの条件を満たすことで、薬剤師による情報提供が正しく評価され、10点の算定が可能となります。
3.2025年中間改定で特定薬剤管理指導加算3はどう変わった?
2025年4月の中間改定では、加算3「ロ」の点数が5点から10点に引き上げられました。
見直しの背景には、2024年10月より始まった長期収載品の選定療養制度により、薬局における説明業務の負担が大きくなったことがあります。
とくに薬剤変更時の患者対応や記録作業が煩雑化した現場の実態をふまえ、評価の強化が求められました。なお、算定要件自体に変更はなく、引き続き適切な説明と記録の徹底が求められます。
点数増加の背景を理解し、対応の質を見直す契機とすることが重要です。
4.特定薬剤管理指導加算3を算定する際の注意点
特定薬剤管理指導加算3は、条件を満たせば他の加算と併算定が可能です。たとえば、同一処方内で「イ」と「ロ」の両方の要件を満たす場合、同時に算定できます。また、加算1や2との併算定も可能です。
算定時には、以下の点に注意して対応しましょう。
- 併算定する加算に対応した指導を実施し、薬歴に記録を残すこと
- レセプト摘要欄に、変更薬剤の名称や供給困難の理由など具体的な内容を記載すること
- 初回のみ算定可能であるため、同一薬剤で繰り返し算定できない
上記ルールを正確に理解し、薬局での適切な対応につなげることが重要です。
5.特定薬剤管理指導加算を算定した際の薬歴記載要件
特定薬剤管理指導加算を算定する際は、薬歴への適切な記録が必須です。
記載要件は以下のように「イ」と「ロ」で異なるため、それぞれの条件に従って正確に対応する必要があります。
■加算「イ」(5点)の薬歴記載要件
- RMP資材を活用したことを明記する
- 説明内容の要点を簡潔に記録する
- 資材名や写しの添付は不要とされている
■加算「ロ」(10点)の薬歴記載要件
- 選定療養対象薬剤名を記録する
- 供給困難による変更時は、変更後薬剤名を記録する
- レセプト摘要欄に、確保できなかった薬剤名を明記する必要がある
初回処方時のみ算定可能である点も含め、記載ルールの徹底が重要です。
6.特定薬剤管理指導加算3の対象医薬品はどう探す?RMP資材と長期収載品の確認方法
加算対象となる医薬品を把握するには、制度上の定義に沿って情報源を適切に活用する必要があります。正確に確認することで、薬歴やレセプト対応のミスを防ぐことも可能です。
ここからは、対象医薬品を調べるための基本的な手順を紹介します。
RMP資材一覧を確認する方法
RMP資材の確認には、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)公式サイトの活用が不可欠です。安定した情報入手と適切な服薬指導の基盤構築に役立ちます。
- PMDAのトップページから安全対策業務>情報提供業務>医薬品に関する情報>医薬品リスク管理計画(RMP)へアクセス
- 「RMP提出品目一覧」へアクセスし、対象薬品名を確認
- 医療用医薬品 情報検索ページより、「RMP資材」にチェックが入った状態で上記医薬品を検索
- 検索結果では「医療従事者向け」「患者向け」などの資材種別が明示されるため、該当リンクからPDFなどのデータを入手
定期的なチェックが算定漏れ防止に有効であり、自社のマイリスト作成やシステム連携もおすすめです。これらの手順でRMP資材一覧を効率的に把握し、薬局業務に活かしていきましょう。
長期収載品の確認方法
長期収載品の確認は、特定薬剤管理指導加算3「ロ」の対象薬剤を把握するうえで不可欠です。正確な確認手順を理解することで、算定ミスや説明不足を防げます。厚生労働省のホームページには、対象となる長期収載品の一覧がPDFやExcel形式で掲載されているため、以下の手順で確認しましょう。
- 厚生労働省の対象ページにアクセスする
- ページ下にある「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」を選択
- 公開されているPDFまたはExcelを開き、対象薬品名・成分名・薬価基準収載医薬品コードなどで検索
定期的な確認で現場対応の精度向上につなげましょう。
7.まとめ
特定薬剤管理指導加算3は、薬剤師がリスクの高い医薬品に対し、的確な情報提供をおこなった際に評価される仕組みです。算定区分ごとの要件や記録内容を正確に把握し、現場での対応力を高めることが求められます。対象医薬品の確認や薬歴記載のポイントを押さえることで、服薬支援の質がさらに向上するでしょう。当記事を参考に、制度の理解を深め、加算の適正な算定に役立ててください。