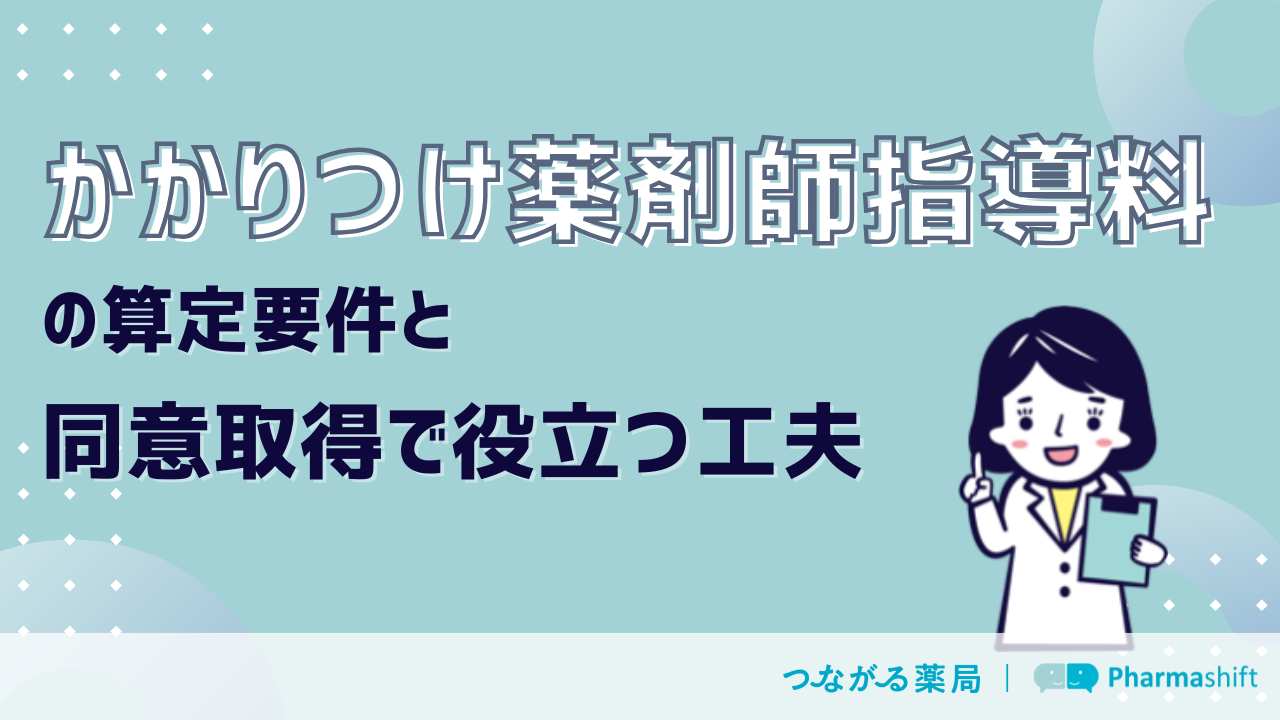執筆者・監修者:薬剤師
かかりつけ薬剤師指導料は、薬剤師が患者さんに継続的な服薬支援をおこなう仕組みを評価する制度であり、薬局経営にも大きな影響を与える重要な点数です。地域包括ケアの推進や薬剤師の対人業務強化を目的に導入されており、実務での理解が欠かせません。
しかし、日常業務の中で次のような疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
「かかりつけ薬剤師指導料がある目的は?」
「かかりつけ薬剤師指導料の算定要件は?」
「かかりつけ薬剤師指導料の同意を取得するうえでのポイントは?」
当記事では、制度が設けられた背景や改定による変化、薬局・薬剤師側の算定要件、患者さんから同意を得るための実務上の工夫までを体系的に解説します。さらに、現場での算定に必要な対応や患者さん対応の工夫も具体的に整理します。
最後まで読むことで、算定誤りを防ぎつつ患者さんとの信頼関係を深めるための実践的な知識が得られるでしょう。
目次
1.かかりつけ薬剤師指導料とは?設定された背景と今までの変化
薬局の役割が拡大する中、かかりつけ薬剤師指導料は地域医療の一翼を担う制度として位置づけられました。制度が導入された経緯や、導入後の変遷を把握することは現場の実務にも直結します。
ここでは制度の成立背景と改定に伴う変化について確認していきましょう。
かかりつけ薬剤師指導料が創設された背景
平成28年(2016年)の診療報酬改定で「かかりつけ薬剤師指導料」は新設されました。薬局が処方箋を調剤する「対物業務」から、患者さんの服薬状況を継続的に把握・指導する「対人業務」への転換を図るためです。政府が策定した「患者のための薬局ビジョン」によると、全国の薬局が「門前型薬局」中心から地域に根ざしたかかりつけ薬局へ役割を変えることが求められました。調剤報酬の評価の仕組みに、服薬管理・継続的フォロー・医師との連携などを含めることで薬剤師機能を強化する意図が明確です。
過去の報酬改定による主な変更
2024年度の診療報酬改定では、かかりつけ薬剤師が休日・夜間の問い合わせに対応できない場合でも、薬局単位で対応可能とするなど夜間・休日対応体制の柔軟化が図られました。
たとえば、患者さんからの相談に対してかかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が対応することが前もって説明されていれば、算定要件を満たすケースがあります。
また、併算定可能な点数が拡大されています。吸入薬指導加算や調剤後薬剤管理指導料 1・2が、かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者さんに対しても併算定できるようになりました。これにより薬剤師業務の評価幅が広がり、実務の柔軟性が向上しています。
上記の変更は、薬局での負担軽減と患者サービスの向上を両立させる意図を持って実施されています。
2.かかりつけ薬剤師指導料の算定要件
かかりつけ薬剤師指導料を正しく算定するには、薬局側の体制や薬剤師の条件に加えて、患者さんとの合意形成や運用時の留意点を整理しておく必要があります。制度を理解し円滑に実務へ取り入れるため、かかりつけ薬剤師指導料の算定要件や手順を確認していきましょう。
かかりつけ薬剤師の施設基準と薬剤師要件
かかりつけ薬剤師指導料を算定するには、薬局の体制と薬剤師の要件を満たすことが必須です。要件を満たした薬局・薬剤師が対応することで、制度の目的である継続的な服薬支援が実現します。
主な条件は、以下のとおりです。
- 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験を有すること
- 週32時間以上の勤務が基本(短時間勤務は週24時間以上かつ週4日以上で可)
- 現在の薬局に継続して1年以上在籍していること
- 研修認定薬剤師の資格を保持していること
- 地域医療活動や在宅業務に積極的に参加していること
- プライバシーに配慮した相談スペースを薬局内に設置していること
これらを満たすことで、薬局は制度上の評価を受けると同時に、患者さんに安心感を提供できるでしょう。基準が厳格に設定されている背景には、かかりつけ薬剤師としての信頼性を確保する狙いがあります。薬局では条件を確認し、体制を整備することが求められます。
算定対象となる患者条件と同意取得の必要性
かかりつけ薬剤師指導料は、対象となる患者さんの条件を満たし、かつ同意を得ることが前提です。制度を適正に運用するには、条件を理解したうえで丁寧な説明と合意形成が欠かせません。
算定に必要な主な要件は、以下のとおりです。
- 同一薬局に複数回来局している患者さんであること
- 患者さん本人から署名付きの同意書を取得すること
- 同意を得た当日は算定不可で、次回来局時から算定可能であること
- 1人の患者さんにつき1薬局・1人の薬剤師のみが担当できること
- 同一月内での薬剤師変更は不可であること
患者さんに対して、かかりつけ薬剤師の役割や得られるメリットを具体的に説明することが求められます。同意を得た記録は薬歴にも残す必要があり、算定の適否を左右する重要な要件です。条件を正確に把握し、誤りなく対応することが薬局での信頼構築につながるでしょう。
算定するうえで必要な対応
かかりつけ薬剤師指導料を正しく算定するには、服薬指導や薬歴記録を徹底する必要があります。患者さんに対して安全で一貫した支援をおこなうために、実務上の対応は明確に整理しておく必要があります。算定時に求められる主な対応は、以下のとおりです。
- 服薬状況を一元的に把握し、残薬や副作用の有無を確認する
- 手帳や薬歴に記録し、同意取得の有無や指導内容を明記する
- 24時間相談可能な連絡体制を整備し、患者さんからの問い合わせに応じる
- 医師や他の医療職と連携し、必要に応じて処方提案や情報共有をおこなう
- 患者さんへの説明で費用や役割を明確化し、同意取得後は継続的に服薬指導を実施する
これらを丁寧に実践することで、算定要件を満たすだけでなく、患者さんとの信頼関係を強化できるでしょう。日常業務に組み込む工夫が、制度を安定的に運用するために重要です。
3.かかりつけ薬剤師指導料の同意取得と説明ポイント
かかりつけ薬剤師指導料を算定するには、患者さんに理解と納得を得るための正しい手順を踏むことが欠かせません。制度を適切に運用するには、必要な文書や説明内容を整理し、算定に関わる留意点を明確に把握しておく必要があります。
ここでは、かかりつけ薬剤師指導料の同意取得と説明のポイントについて確認していきましょう。
同意書の位置づけと説明必須項目
かかりつけ薬剤師指導料を算定するには、患者さんに制度を理解してもらい、署名を伴う同意書を薬局で保管することが求められます。説明の際には基準に沿った内容を網羅し、患者さんが納得できる形で伝えることが重要です。
説明に含めるべき事項は、以下のとおりです。
- 薬剤師が担う具体的な業務内容
- かかりつけ薬剤師を持つ意義や役割
- かかりつけ薬剤師指導料の費用
- 薬剤師がかかりつけ薬剤師指導料を必要と判断した理由
これらを的確に伝えたうえで署名を得た同意書は、薬局で保管し薬歴に記録する必要があります。説明は形式的な手続きではなく、信頼関係を築く第一歩となるため、薬局では丁寧な対応が欠かせません。
服薬管理指導料との関係と算定上の注意点
かかりつけ薬剤師指導料は、服薬管理指導料と同時に算定できない点に注意が必要です。両者は患者さんへの服薬支援を評価する点で重複するため、同意取得後は服薬管理指導料からかかりつけ薬剤師指導料へ切り替えて算定します。切り替え時に混同すると算定誤りにつながるため、薬歴やレセプト上での管理を徹底することが求められます。実務では算定ルールを職員間で共有し、日常業務に組み込むことが欠かせません。
4.かかりつけ薬剤師指導料の同意取得で役立つ工夫
かかりつけ薬剤師指導料を算定するには、患者さんに提案を自然に受け入れてもらえる工夫が必要です。制度の価値を伝えるには、状況に応じた声かけや継続的な働きかけが欠かせません。
ここからは、かかりつけ薬剤師指導料の効果的な提案方法や信頼関係づくりのポイントを確認していきましょう。
POINT1:本当に必要とする患者に絞って声かけする
かかりつけ薬剤師指導料の必要性が高い患者さんに優先して提案すると効果的です。とくに、多剤服用で管理が複雑な患者さんや複数の医療機関を受診している患者さんは対象として適しています。全員に一律で声かけすると負担が大きくなるため、重点的に案内すべき患者さんを見極めることが大切です。対象を絞ることで、薬剤師側も効率的に対応でき、患者さんにとっても納得感のある説明につながります。
POINT2:価値を実感したタイミングで提案する
患者さんが薬剤師の介入で効果を感じた瞬間を逃さず提案することも有効です。たとえば、残薬調整で服薬管理が楽になった場面や医師への処方提案で治療が改善した場面であれば、患者さんも有効性を感じやすいでしょう。患者さん自身が支援の価値を体験した直後に案内することで、追加費用への理解も得やすく、納得感を持って同意につながる可能性が高まります。
POINT3:日頃から患者との信頼関係を築く
日常的に信頼を積み重ねる姿勢も不可欠です。患者さんに安心して任せてもらうには、継続的な声かけや誠実な対応を意識し、服薬や生活面の相談に親身に応じることが重要です。さらに、顔なじみの患者さんに対しては薬歴だけに頼らず状況を把握し、初めての患者さんにも丁寧に接することで信頼感をおぼえてもらえるでしょう。こうした関わりが結果的に同意取得につながりやすくなります。
POINT4:複数回にわたり継続して案内する
かかりつけ薬剤師指導料の同意は、1回の説明で得られるとは限りません。患者さんが迷った場合は無理に迫らず、再来局時に改めて案内する姿勢が有効です。さらに、薬局内にポスター掲示やチラシ配布をおこない、制度の内容を繰り返し目に触れてもらうことも効果的です。継続的な周知により患者さんが必要性を理解しやすくなり、結果として納得感を持った同意につながります。
POINT5:抽象的な説明ではなく具体的なメリットを伝える
抽象的な説明よりも、患者さんが納得できる具体例を提示すると効果的です。たとえば、服薬管理指導料との差額が3割負担で約90円程度であることを明示し、どのようなサポートを受けられるかを伝えることが大切です。具体的には、残薬調整による服薬負担の軽減や複数医療機関での処方薬の一元管理などを示すと理解が進むでしょう。明確なメリットを示すことで制度の意義が伝わりやすくなり、同意取得につながります。
5.まとめ
かかりつけ薬剤師指導料を活用することで、患者さんは継続的な服薬支援や医師との連携を受けられる体制が整います。算定要件を理解し、適切に同意を得ることは薬局にとって信頼構築の第一歩となります。さらに、背景や改定内容を踏まえて体制を整えることで、業務効率化と患者満足度の両立が可能です。当記事を参考に、制度の正しい運用と実務に活かせる工夫を取り入れ、薬局経営や現場対応の質を高めてください。
「つながる薬局」なら、処方箋送信受付からオンライン服薬指導、服薬フォローなどの機能をオールインワンで備えており、かかりつけ薬局化をトータルサポートします。