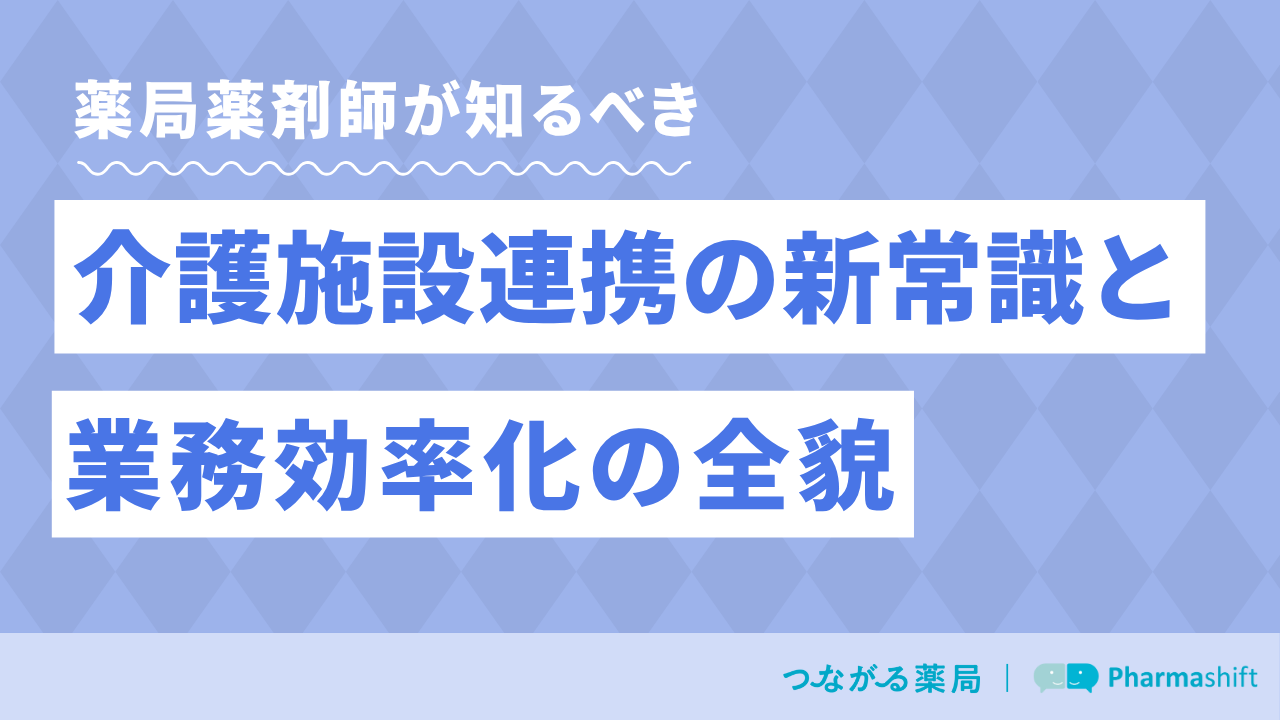執筆者・監修者:薬剤師
薬局と介護施設の連携は、超高齢社会を支える地域包括ケアの中で欠かせない要素です。薬剤師が在宅や施設の現場に深く関わることで、医療と介護をつなぐ新たな役割が求められています。
しかし、次のように感じている薬剤師も多いのではないでしょうか。
「薬局と介護施設が連携する意義とは?」
「薬局と介護施設が連携するうえでの課題は?」
「連携業務をどのように収益につなげたらよい?」
当記事では、地域連携薬局の機能や多職種連携の実践例、現場で生じる課題と解決策、施設連携加算やICT導入など、経営に活かせる内容を解説します。最後まで読めば、薬局と介護施設との連携業務を効率化しながら、収益性も高める道筋が明確になるでしょう。
目次
1.地域包括ケアで変わる薬局と介護施設が連携する社会的意義
高齢化の進展により、薬局と介護施設の連携は地域包括ケアを支える重要な要素となっています。薬剤師が在宅や施設の現場に関わる機会が増え、医療と介護を一体的に支援する仕組みづくりが求められています。
ここでは、地域連携薬局の機能と多職種連携の在り方を詳しく見ていきましょう。
「地域連携薬局」に求められる機能とは
「地域連携薬局」には、地域包括ケアを支える拠点としての機能が求められています。認定要件は、構造設備・情報共有・薬剤供給・在宅医療体制などが求められ、それぞれに明確な基準があります。
具体的には、以下のとおりです。
- 構造設備:バリアフリー対応や相談スペースの設置、個人情報保護への配慮が必須
- 情報共有:医療機関への情報提供を月平均30回以上おこなう実績が必要
- 薬剤供給:地域における薬剤の安定供給、夜間・休日対応、無菌調製などを実施
- 在宅医療体制:在宅訪問や服薬管理を通じ、在宅療養支援に貢献
上記を総合的に整備することで、薬局は医療と介護をつなぐ中核としての信頼を確立できます。地域の患者さんが安心して暮らせる環境づくりを支えるため、地域連携薬局の要件を満たす取り組みが重要です。
医療と介護をつなぐハブとしての多職種連携
薬剤師は、医療と介護をつなぐ中核として、多職種連携の現場で重要な役割を担っています。
とくに、チーム医療の中では、以下のような場面で専門性を発揮します。
- 医師の往診同行により、服薬状況や副作用の有無を現場で共有
- ポリファーマシーの解消に向けた重複処方・相互作用の確認
- 介護スタッフへの服薬指導や残薬管理による誤薬防止
- 管理栄養士・看護師との情報共有による服薬支援と生活習慣改善の提案
- 在宅療養者への訪問服薬指導による継続的モニタリング
上記の取り組みにより、薬剤師は医療・介護・生活支援を横断するハブとして機能します。結果として、患者さんの安全性向上と医療資源の最適化に貢献できる体制を築けます。
2.薬局と介護施設が連携するうえでの課題
薬局と介護施設との連携が進む一方で、薬局の現場では業務の複雑化が進んでいます。情報共有や調剤方法の違いによって、薬剤師が抱える負担は少なくありません。業務の非効率化は安全な薬物療法にも影響を及ぼすため、課題を整理して対策を考えることが重要です。
ここでは、薬局と介護施設との連携時に生じやすい課題を掘り下げていきましょう。
ポリファーマシーと膨大な調剤準備時間
薬剤師が介護施設を訪問する際、調剤準備や服薬管理、情報共有まで幅広い業務を担うため、訪問1回あたりの負担が大きくなっています。さらに、野村総合研究所の調査では、介護施設訪問時の薬剤師の患者さんへの対応時間が5分以内にとどまるケースが多いことが明らかになっています。
※参考:野村総合研究所「介護施設における服薬支援の実態」
そのため、薬剤師は限られた時間の中で安全性と効率性の両立を求められているのが現状です。
とくに、複数の医師から処方を受ける高齢者では、ポリファーマシーの対応が必要不可欠のため、現場では以下のような作業が重なっています。
- 訪問前の薬歴確認と処方内容の突き合わせ
- 相互作用や重複投薬の確認作業
- 医師・看護師・介護職との情報共有・調整
上記の業務が調剤準備時間の増大を招き、薬剤師が患者さんと向き合う時間を圧迫しています。結果として、服薬適正化や副作用防止といった専門性が十分に発揮されにくい状況が続いています。
電話やFAXなどのアナログ業務が引き起こす情報伝達リスク
電話やFAXといったアナログの連絡手段に依存すると、情報伝達の効率が著しく低下します。
たとえば、薬局や介護施設とのやりとりでは、以下の問題が生じがちです。
- 電話がつながらず折り返し連絡が必要になる反復作業
- FAX番号の誤入力による誤送信や紙資料の紛失
- 音声だけでは詳細な状況が伝わらず、記録が曖昧になりやすい
上記のような非効率な情報共有は、薬剤師が迅速かつ正確に服薬支援をおこなう妨げとなります。結果として、言い間違いや記録漏れといったリスクが増大し、薬局と介護施設の円滑な連携に影響を及ぼします。情報の一元化と共有手段の見直しが急務といえるでしょう。
他科受診による服薬情報一元化の負担
複数の医療機関からの処方箋を一元管理する業務は、情報管理するうえで負担となっています。
複数科の処方により、ポリファーマシーのリスクが高まるため、以下のような調整作業が必要です。
- 医療機関ごとの処方内容を比較・照合する作業
- 重複投与や薬物相互作用の有無を確認・対応する工程
- 複数処方情報から介護施設・在宅支援者へ適切に服薬情報を共有する連携業務
上記の一元化作業により、薬剤師の調剤準備時間が増大し、対人支援や服薬指導に充てる時間が削られやすくなります。結果として、薬剤師の専門性である薬物療法の支援が十分に機能しない可能性もあるため、服薬情報の集約体制や効率化手法の整備が必要だといえます。
3.薬局と介護施設の連携業務を経営に活かす新戦略
薬局と介護施設の連携は、地域医療に欠かせない経営戦略の1つです。現場での情報共有や服薬支援の仕組みを整えることが、業務効率と収益の両立につながります。制度やICTをうまく活用することで、薬局経営に新たな価値を生み出すことが可能です。
ここからは、薬局と介護施設の連携業務を経営に活かす実践的な活用策を紹介します。
【制度活用】2024年新設「施設連携加算」を算定
2024年度から新設された施設連携加算(50点)は、薬局が介護施設との連携支援をおこなううえで、重要な収益機会です。
算定の前提条件として、以下を満たす必要があります。
- 算定対象患者が、特別養護老人ホーム等に入所していること
- 薬剤師が訪問し、療養生活の状態・医薬品保管状況・残薬・服薬状況・併用薬・副作用・相互作用などを確認し、施設職員と協働して服薬管理を実施すること
また、算定にあたっては以下のような専門的判断が求められます。
- 入所時に薬剤数が多く、明らかに支援が必要と薬剤師が認めた場合
- 新たな薬剤処方または用法・用量変更後に、従来とは異なる服薬支援が必要と判断された場合
- 施設職員からの相談(副作用や体調変化)を受けて、薬剤師が服薬状況を確認し、支援実施が必要と判断された場合
上記の要件を丁寧に満たすことで、薬局は専門性を活かしながら介護施設連携の中で収益を確保できるようになるでしょう。
【ICT活用】「つながる薬局」など活用による連携業務のDX
介護施設との情報共有を効率化するには、ICTの導入が不可欠です。
たとえば、「つながる薬局」では薬剤師の訪問調剤業務をデジタル化し、アナログ中心の業務を大幅に改善しています。主な機能と効果は、以下のとおりです。
- 入居者全員のお薬手帳を一括管理:Web上で薬剤情報を確認でき、紛失リスクを回避
- 薬局・介護施設間のリアルタイム連携:同一の管理画面で入居者データを共有し、情報伝達のズレを防止
- メッセージ機能による双方向連絡:LINEを活用し、業務の合間でも迅速なやりとりが可能
- 処方箋送信のデータ化:FAX送信を不要とし、通信コストと手間を削減
上記の仕組みにより、情報伝達の精度が高まり、服薬ミスや記録漏れの防止につながります。結果として、薬局と介護施設の信頼関係が強化され、服薬支援の質が向上するでしょう。さらに、効率的な情報共有により在宅支援の体制が整い、施設側からの処方箋依頼が増えるケースも見られるなど、経営面にも好影響をもたらします。
4.まとめ
薬局と介護施設の連携を強化することで、薬剤師は医療と介護の橋渡しとして真価を発揮できます。情報共有の効率化や服薬管理の精度向上は、入居者の安全確保と業務負担の軽減の両立につながります。さらに、施設連携加算やICT導入を活用すれば、業務改善だけでなく経営的メリットも得ることが可能です。当記事を参考に、介護施設との連携体制の見直しとDX推進を進め、地域包括ケアを支える薬局経営を実現してください。