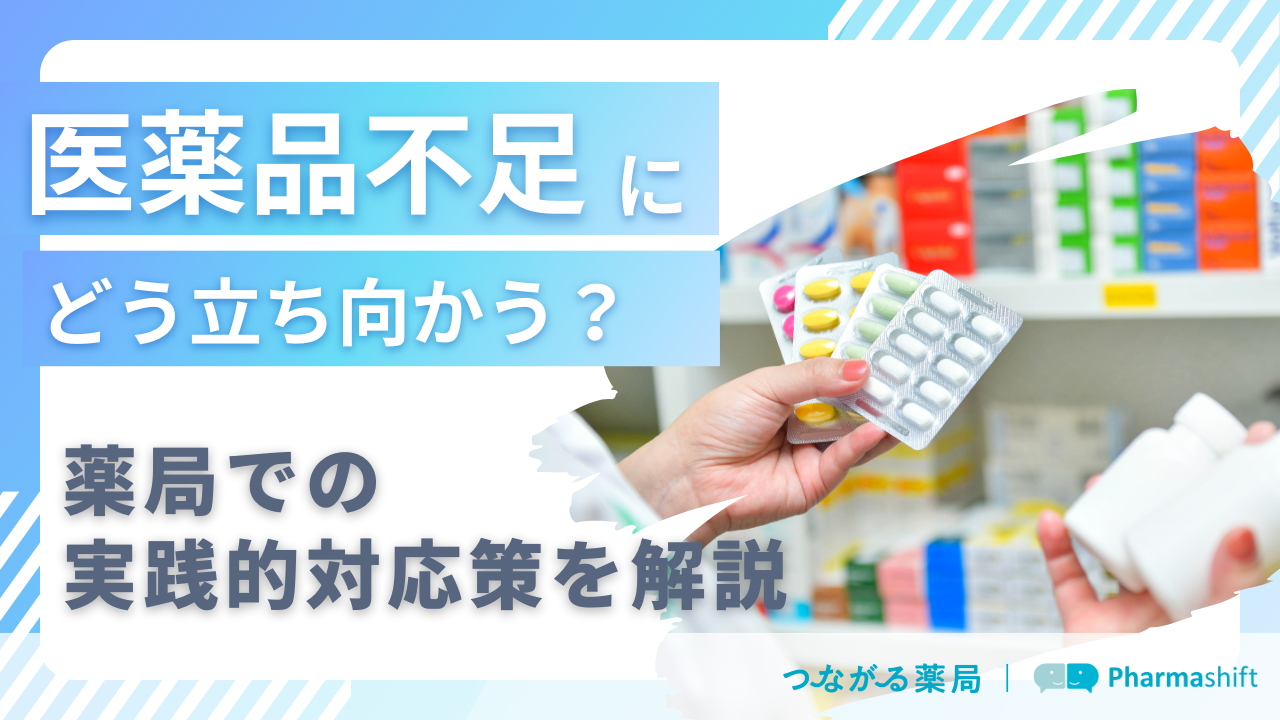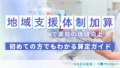薬局では、近年深刻化する医薬品不足への対応が大きな課題となっています。供給遅延や生産中止、海外原料への依存や価格抑制政策などが複雑に絡み合い、現場で混乱を招いています。そのような中、次のように感じている方も多いのではないでしょうか。
「医薬品はどれくらい不足しているの?」
「医薬品が不足しているのはなぜ?」
「医薬品不足に備えた対応策は?」
本記事では、医薬品不足に関する現状の課題と原因を解説し、薬局で実践できる在庫管理や地域連携の方法、業務改善策まで詳しく紹介します。最後まで読むことで、医薬品不足に強い薬局づくりに必要な知識が身につくでしょう。
目次
1.近年深刻化する医薬品不足の現状
供給遅延や生産中止が続くことによる医薬品不足は、薬局や医療現場に深刻な影響をおよぼしています。そのような状況の中、安定した調剤をおこなうには、現状や背景を正しく知ることが大切です。ここでは、医薬品不足の現状について解説します。
日本国内における医薬品不足の実態
日本国内における医薬品不足は深刻化しています。厚生労働省の公表データによると、2024年10月時点で医療用医薬品の約5分の1が限定出荷・供給停止の状況になっています。現時点でも、約3,500品目の医薬品が限定出荷・供給停止の状況です。
※参考:厚生労働省「医療用医薬品供給状況」
医薬品不足は患者さんの治療に支障をきたす問題であり、現場での対応力がますます重要になっています。
不足している主な医薬品の種類
実際に限定出荷・供給停止により不足している代表的な医薬品は、以下のとおりです。
- 抗生物質
- 鎮咳薬・去痰薬
- 点眼薬
- 小児用医薬品
- 解熱鎮痛薬
- 漢方製剤
- 精神神経用剤
- 降圧薬
- 抗ウイルス薬
- 止血剤
これらの医薬品不足は、患者さんの治療に影響をおよぼしており、早急な対応が求められています。
2.医薬品不足が発生する原因と背景
医薬品不足は突然発生するものではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こります。安定供給を維持するには、何が背景にあるのかを理解しておくことも重要です。ここでは、医薬品不足が起こっている原因について解説します。
品質問題による製造中止・出荷停止
医薬品の供給不足は、品質問題による製造中止や出荷停止が大きな要因となっています。具体的な事例として、以下のようなケースが報告されています。
- 製造工程上のトラブル:2020年、爪白癬治療薬の製造過程で睡眠導入剤の成分が混入し、副作用が発生
- 品質管理の不備:2021年以降、小林化工や日医工など21社で品質不正が発覚し、業務停止などの行政処分が発生
- 承認書と異なる製造:ジェネリック医薬品を扱う全172社の自主点検で、8,734品目中3,796品目で製造販売承認書と異なる製造が判明
これらの品質問題が供給不足を招き、医療現場や患者さんに影響をおよぼしています。
海外依存度の高い原料供給
医薬品の原料供給における海外依存度の高さは、供給不足の一因となっています。日本では、ジェネリック医薬品の原薬の約60%を輸入に頼っており、主な供給元は中国やインドです。この依存構造により、世界的な物流の遅延や生産国での規制強化が直接的に影響をおよぼし、原材料の調達が困難になるケースが増えています。結果として、製薬会社は必要な原料を確保できず、医薬品の製造が滞る状況が生じています。これらの要因が重なり、医薬品の供給不足が深刻化しているのです。
価格抑制政策による製薬業界の生産縮小
医薬品不足の一因として、価格抑制政策による製薬業界の生産縮小が挙げられます。日本では、薬価改定が原則として2年に1回実施され、市場実勢価格に合わせて薬価が引き下げられます。これにより、製薬企業の利益率が低下し、特に収益性の低い医薬品の生産が縮小されている状況です。その結果、供給不足が生じ、患者さんや医療現場に影響をおよぼしています。
3.医薬品不足に備えた対応策
医薬品不足は突然発生することがあり、患者さんへの安定供給のためには事前の備えが必要です。薬局としてできる対策を理解し、日々の業務に取り入れることが大切です。ここでは、医薬品不足に備えた対応策について詳しく見ていきましょう。
適切な在庫管理を徹底する
医薬品不足に対応するには、薬局における適切な在庫管理が重要です。過不足のない在庫を維持するためにも、以下の対策を講じましょう。
- 複数の卸との連携:一つの卸に依存せず、複数の卸と取引をおこなうことで、供給リスクを分散可能
- システムの活用:在庫状況をリアルタイムで把握して適切な発注をおこなうため、在庫管理システムの導入を推奨
これらの取り組みにより、薬局は安定した医薬品供給を維持し、患者さんへの影響を最小限に抑えることが可能となります。
地域の薬局と連携する
医薬品不足に対応するには、地域の薬局同士の連携が重要です。具体的には、地域の薬剤師会や地域連携薬局などと協力し、必要時に医薬品を相互に供給し合える体制を構築することが効果的です。地域連携薬局は、他の薬局からの求めに応じて医薬品を提供できる体制を備えることが求められています。また、地域支援体制加算の要件には、薬局間連携による医薬品の融通が含まれており、地域の医薬品供給体制の確保が期待されています。これらの連携体制を通じて、地域全体で医薬品の安定供給を図ることが可能になるでしょう。
4.医薬品が不足したときの対応のポイント
医薬品が不足した場合、薬局では柔軟で迅速な対応が求められます。医療現場や患者さんへの影響を最小限に抑えるため、正しい行動を知ることが大切です。ここでは、医薬品不足時の対応のポイントについて解説します。
医師へ代替医薬品や日数調整などを提案する
医薬品が不足した際、薬局は医師と連携し、代替医薬品の提案や処方日数の調整をおこなうことが重要です。具体的には、以下の対応を検討しましょう。
- 代替医薬品の提案:不足している医薬品と同じ有効成分を含む他製薬会社の製品や、同等の効果を持つ別の医薬品を医師に提案
- 処方日数の調整:代替医薬品が入手困難な場合、患者さんの手持ちにある医薬品の残量を確認し、医師に処方日数の短縮などを提案
これらの対応を通じて、薬局は医師と協力し、患者さんへの影響を最小限に抑えることが求められます。
患者さんへ適切な説明と対応策を提示する
医薬品が不足した際、患者さんへの適切な説明と対応策の提示が求められます。患者さんの不安を軽減し、信頼関係を維持するため、以下の対応が効果的です。
- 丁寧な状況説明:製薬会社の供給問題や全国的な品薄状況を簡潔に伝え、必要に応じて謝罪し、患者さんの理解を促す
- 代替医薬品の提案:同じ有効成分を持つ他製薬会社の医薬品や、同等の効果を持つ別の医薬品への変更を提案し、患者さんの治療を継続できるよう努める
- 処方日数の調整:在庫状況に応じて処方日数の短縮や分割調剤を提案し、患者さんへの影響を最小限に抑える
- 他の薬局の紹介:在庫がある近隣の薬局を探して紹介することで、患者さんが必要な医薬品を入手できるようサポート
これらの対応を通じて、薬局は患者さんの安心と信頼を確保し、医薬品不足の状況下でも適切な医療提供を目指すことが求められます。
5.医薬品不足に関する今後の見通し
医薬品不足に関する今後の見通しとして、厚生労働省は供給安定化に向けて有識者検討会を設置し、企業ごとの安定供給計画の提出義務や進捗管理を徹底する方針を示しています。製造工程や品質管理の体制強化に対しても指導をおこない、不備が見つかれば改善報告を求めています。
※参考:厚生労働省「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」
※参考:厚生労働省「医薬品等の供給不安への対応について」
加えて、製薬会社に対する現場視察を通じて、生産効率化に必要な設備投資状況や作業改善の取り組みを確認し、支援策も検討中です。これにより、生産能力向上と供給安定化の実現を目指しています。
また、インフルエンザなどの感染症流行期に備え、対症療法薬については在庫放出や優先供給を企業に要請しています。あわせて、医療機関や薬局に対しても、必要量のみの発注を求めるなど需給バランスを調整中です。
※参考:厚生労働省「福岡大臣会見概要(高田製薬株式会社視察後)」
このような一連の施策により、医薬品不足は徐々に改善へ向かうと考えられています。
6.まとめ
医薬品不足は、医療現場や薬局に大きな影響を与える重要な問題です。適切な在庫管理や地域薬局との連携を通じて、安定した供給を維持する取り組みが求められます。さらに、医師への提案や患者さんへの丁寧な説明をおこなうことで、信頼関係を築くことも大切です。当記事を参考に、医薬品不足に備えた対策を実践し、薬局として安心できる調剤体制づくりに役立ててください。