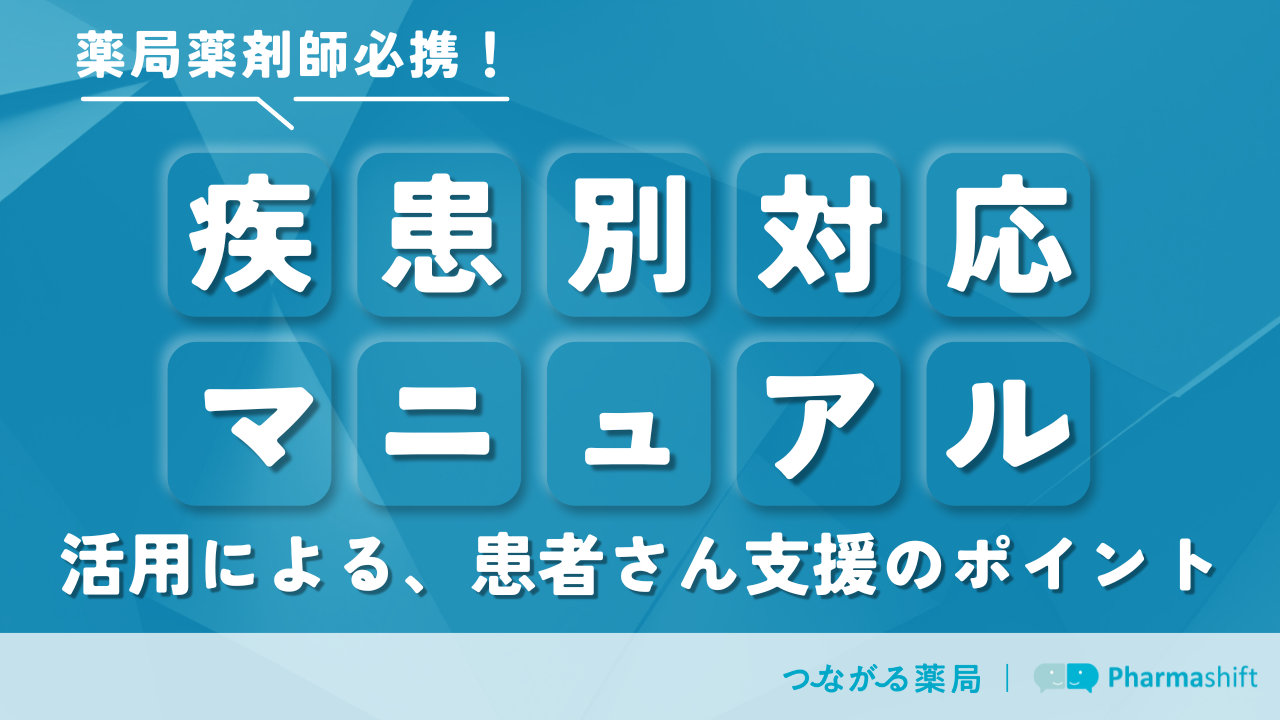2025年2月に厚生労働省から公表された「薬局における疾患別対応マニュアル」。
公表されたばかりで、以下のように感じる薬剤師も多いでしょう。
「疾患別対応マニュアルってなに?」
「疾患別対応マニュアルにはどんなことが記載されているの?」
「薬剤師に対応が求められる疾患別のポイントは?」
今後の薬局薬剤師において、疾患別対応マニュアルの理解は、患者さんからの信頼を得るために不可欠だといえるでしょう。
本記事では、疾患別対応マニュアルの対象疾患や基本対応、服薬フォロー、多職種連携の重要性まで体系的に解説します。
最後まで読むことで、実務に直結する支援のコツが得られるでしょう。
目次
1.「薬局における疾患別対応マニュアル」とは?
「薬局における疾患別対応マニュアル」とは、薬局の薬剤師が地域で信頼されるために不可欠な指針です。
※参考:厚生労働省「薬局における疾患別対応マニュアル ~患者支援の更なる充実に向けて~」
高齢化や生活習慣病の増加にともない、薬剤師にもがん・脳卒中・心筋梗塞・糖尿病・精神疾患に対して適切な対応が求められています。
薬局では患者さんに調剤したお薬の正しい使い方や副作用の注意点を伝える役割があります。また、服薬状況を確認し、必要に応じて医療機関へ情報提供・連携して対応することも重要です。
このように、薬剤師が患者さん一人ひとりの健康を支える専門家として、疾患に応じて行動するための基盤となるのが、「薬局における疾患別対応マニュアル」なのです。
2.疾患別対応マニュアルの概要
薬剤師には、患者さんの状態に合わせた適切な支援が求められています。
医療の現場では、多様な疾患に対応する知識と対応力が必要です。
まずは、どのような疾患がマニュアルの対象となるのかを把握し、薬剤師として意識すべき基本を確認することが大切です。
ここでは、疾患別対応マニュアルの概要について詳しく見ていきましょう。
対象となる5つの疾患
疾患別対応マニュアルでは、以下の5つの疾患が対象となっています。
- がん
- 脳卒中
- 心筋梗塞などの心血管疾患
- 糖尿病
- 精神疾患(気分障害・統合失調症・睡眠障害・認知症)
これらの疾患は重症化や再発のリスクが高いため、薬剤師は日々の業務で正しい知識をもとに支援することが大切です。
各疾患における薬剤師の基本的対応
各疾患における薬剤師の基本的対応は、患者さんの安心と治療効果の向上に欠かせません。
薬剤師が各疾患において共通しておこなうべき対応は次のとおりです。
- 患者さんの情報を正確に把握する
- 調剤した医薬品の効果や副作用をわかりやすく説明する
- 服薬状況や生活習慣を定期的に確認する
- 必要に応じて医師や医療機関に情報提供をおこなう
疾患別対応マニュアルを活用し、信頼される薬剤師として支援を続けることが重要です。
3.疾患別対応マニュアルが提示する各疾患の対応ポイント
疾患別対応マニュアルは、薬剤師が患者さんに寄り添い支援するための大切な手引きです。
疾患ごとに異なる特徴を理解して適切に対応する姿勢が求められるため、対象となる疾患を知り、基本を押さえることが必要です。
ここでは、各疾患の対応ポイントについて詳しく見ていきましょう。
がん
がん治療は副作用や長期療養にともなう不安が大きいため、薬局薬剤師の支援が欠かせません。
疾患別対応マニュアルでは、がんに対する対応のポイントとして、次のようなポイントが示されています。
- 個々の患者さんに適したがん薬物療法を理解して説明する
- 抗がん薬や治療計画(レジメン)を確認し、正確な服薬指導をおこなう
- 重篤な副作用の兆候を早期に把握し、対応策を事前に伝える
- 副作用発現時の受診目安や対処法をわかりやすく説明する
- 服薬状況や生活環境、心身状態を定期的に確認する
- 治療中の心理面や不安に配慮し、患者さんや家族の気持ちに寄り添う
- 緊急安全情報や必要な情報を迅速に提供する
- 高齢者やAYA世代などライフステージに応じた配慮をおこなう
- 医師や医療機関と積極的に連携し、情報共有をおこなう
- お薬手帳や服薬記録を活用して継続的なフォローアップをおこなう
これらにより、薬剤師はがん患者さんに安心を届ける役割を果たせるでしょう。
脳卒中
脳卒中は再発や重い後遺症をともないやすく、薬剤師の継続した支援が必要です。
疾患別対応マニュアルでは、脳卒中に対する対応のポイントとして以下が挙げられています。
- 脳卒中再発予防の重要性を説明し、薬物療法継続の必要性を伝える
- 生活習慣改善(食事・運動・禁煙・節酒)の指導を実施する
- 血圧、血糖、脂質管理について患者さんの情報を収集し、確認する
- 食事とお薬の相互作用を説明し、注意喚起をおこなう
- 抗血小板薬や抗凝固薬の服用状況を確認し、副作用の有無を聴取する
- 多剤併用による副作用や相互作用リスクを評価し、必要時は医師に提案する
- 再発予防薬の中断を防ぐため、アドヒアランスを確認して対策を立てる
- 在宅療養患者や家族に対して心理的サポートや情報提供をおこなう
- 地域の医療機関や多職種と連携し、フォローアップ体制を整える
- 災害時の継続的な服薬支援についても考慮し指導する
これらの対応を通じて、薬剤師は脳卒中の患者さんを支える存在になれるでしょう。
心血管疾患
心血管疾患は再発や合併症のリスクが高く、薬剤師の支援が重要です。
疾患別対応マニュアルでは、心血管疾患に対する対応のポイントとして以下が示されています。
- 高血圧や糖尿病など併発する疾患の管理を支援し、患者さんに病気予防の重要性を説明する
- 心筋梗塞や狭心症の再発防止のため、生活習慣改善を具体的に提案する
- 処方薬だけでなく、市販薬やサプリメントの併用確認をおこない、リスクを把握する
- 血圧や体重、服薬状況を継続して記録するよう促し、自己管理をサポートする
- 症状悪化時や発作時の行動(救急要請など)について事前に指導する
- 禁煙や節酒を促し、必要に応じて禁煙補助薬の活用を提案する
- 睡眠障害の有無を確認し、医師受診を勧める場合もある
- 副作用早期発見のため、出血や浮腫など身体変化について患者さんと情報共有する
- 多職種や医療機関との連携を積極的におこない、お薬手帳を活用して情報共有をおこなう
- 退院後や在宅療養患者に対しても継続したフォローアップをおこなう
これらを実行することで、薬剤師は心血管疾患の患者さんを支える役割を果たします。
糖尿病
糖尿病は進行すると合併症を引き起こすため、薬局薬剤師の支援が重要です。
疾患別対応マニュアルでは、糖尿病への対応ポイントとして以下が示されています。
- 治療方針やHbA1c値などの目標を確認し、継続支援をおこなう
- 低血糖症状やシックデイへの対応方法を患者に説明する
- インスリン自己注射の手技を継続的に確認・評価する
- 合併症や併存症の有無を定期的に把握して管理する
- 食事療法や運動療法に対する理解と実践状況を確認する
- SMBGやCGM等の機器使用状況と正しい活用を確認する
- 長期的な体重変化、生活環境の変化にともなう影響を把握する
- 残薬確認や服薬状況を定期的にチェックし、改善を提案する
- 高齢者や妊婦、小児の患者さんには特に個別の配慮をおこなう
- 多職種との情報共有をおこない、多面的な支援体制を作る
- 災害時におけるお薬や治療継続の備えについて指導する
これらを実践し、薬局薬剤師は糖尿病患者の健康維持に貢献します。
精神疾患
精神疾患は症状の変動が大きく、継続的な支援が必要です。
薬剤師は患者さんに寄り添い、適切な対応をおこなうことが重要です。
疾患別対応マニュアルでは、精神疾患への対応ポイントとして以下が示されています。
【精神疾患における共通対応事項】
- 服薬継続の重要性を繰り返し伝え、不安や疑問に丁寧に対応する
- 副作用や離脱症状について事前に説明し、安心感を与える
- 残薬や服薬状況を定期的に確認し、問題があれば対応する
- 患者さんの生活状況や心理状態を把握し、支援に役立てる
- 自殺兆候や症状悪化のサインを早期に発見し、医療機関と連携する
- 家族や支援者にも情報を共有し、接し方やサポート方法を助言する
- お薬手帳やマイナ保険証を活用し、重複処方や併用薬を確認する
- 医療機関や多職種と密に連携して支援体制を構築する
【気分障害】
- Yes・Noで答えやすい質問で情報収集をおこなう
- 初回治療では数日以内にフォローし、継続服薬を促す
- 躁転の兆候や急な気分変動を観察し、医師に報告する
- 若年者には自殺リスクについて家族へも説明し注意を促す
- 減薬時や服用中止希望時には離脱症状を丁寧に説明する
【統合失調症】
- 病識や治療理解度を確認し、無理なく説明する
- 幻聴や妄想が強い場合は環境調整や配慮を提案する
- 副作用歴や検査値を確認し、処方内容を評価して提案する
- 混乱や拒薬時は冷静に対応し、落ち着かせる声かけをおこなう
【睡眠障害】
- 睡眠薬依存や不安について事前に説明し安心感を与える
- 睡眠衛生指導をおこない、生活改善を支援する
- 副作用(眠気持ち越し・転倒リスク)を説明し注意喚起する
- 自殺念慮や過量服薬の兆候を把握し、早急に連携する
【認知症】
- 説明時はゆっくりと簡潔に伝え、視覚補助を活用する
- 服薬しやすい剤形や一包化を医師に提案する
- 認知機能低下のサインを観察し、適切な対応を取る
- BPSD対応時は抗精神病薬の適正使用と注意点を説明する
これらを実践することで、薬剤師は精神疾患患者さんの生活を支える役割を果たすでしょう。
4.疾患別対応マニュアルにおける服薬フォローアップの重要性
服薬フォローは、疾患別対応マニュアルにおいて薬剤師に求められる重要な役割です。
なぜなら、調剤した以降も継続して飲めているか、副作用はないかを薬剤師が見守ることが、治療成功に直結するからです。
たとえば、副作用が心配で勝手に服薬をやめてしまう患者さんは少なくありませんが、薬剤師の定期的なフォローにより、早期対応や生活指導が可能になります。
薬剤師による服薬フォローの徹底が、患者さん支援と治療継続の大きな鍵となるのです。
なお、服薬フォローについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
▶ 服薬フォローで薬局の評価アップ!実践のポイントと具体例
5.疾患別対応マニュアルを活かすために!多職種連携の推進
疾患別対応マニュアルを活かすには、多職種連携が欠かせません。
薬剤師だけでなく、医師や看護師、ケアマネージャーと情報を共有することで患者さん支援はより充実します。
生活面や治療状況を互いに理解し合うことで、的確な助言や早期対応が可能となります。
多職種連携を進めることで、疾患別対応マニュアルの活用効果をさらに高め、患者さんに安心と継続的な支援を提供できるでしょう。
6.まとめ
疾患別対応マニュアルを活用すれば、薬剤師は患者さんに合わせた情報提供や支援がおこなえます。多職種と連携することで、地域全体で患者さんを見守る環境も整います。
また、薬剤師による服薬フォローを徹底することで、治療継続や再発予防に大きく寄与することも可能です。
当記事を参考に、疾患別対応マニュアルについて理解し、実践的な患者さんへの対応力を高め、信頼される薬剤師としての業務に活かしてください。