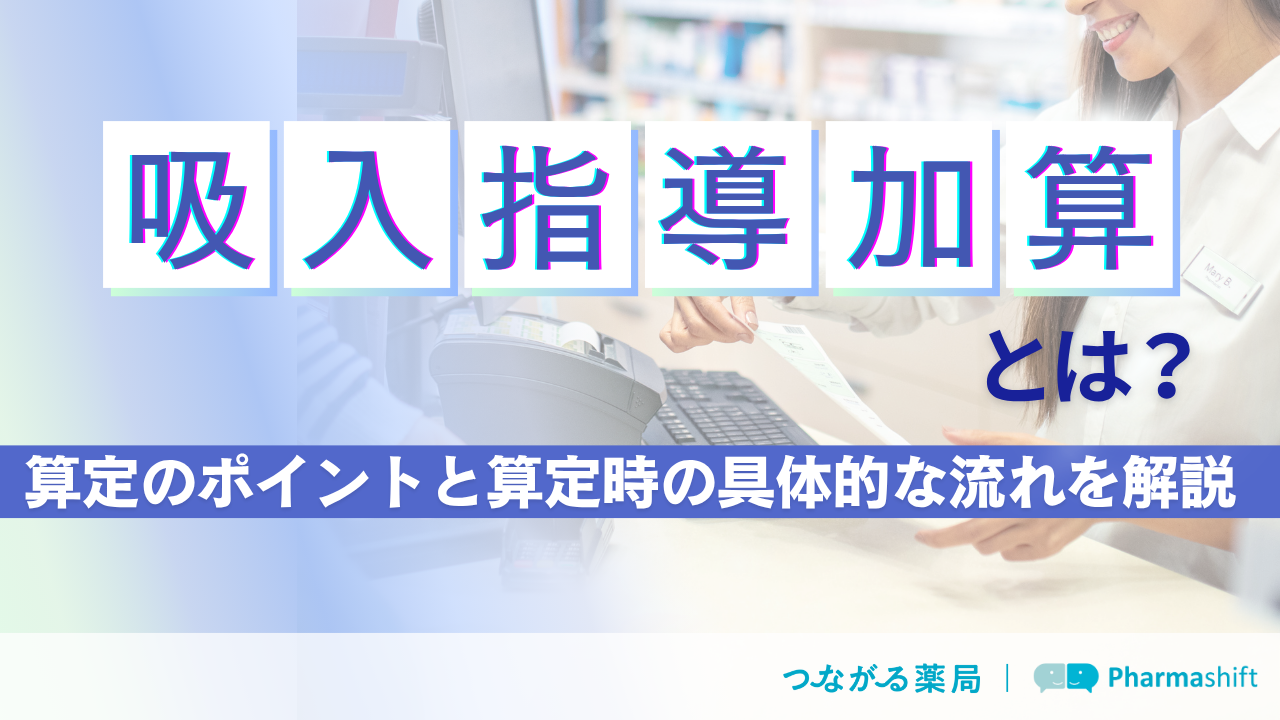執筆者・監修者:薬剤師
吸入指導加算について、以下のような疑問や悩みを感じていませんか?
「吸入指導加算ってどんなときに算定できる?」
「手順や注意点がいまいちわからない」
「算定要件を満たすには何に気をつければよい?」
吸入指導加算は、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の治療効果向上を目的に設定された点数です。
当記事では、吸入指導加算の概要から、算定の要件・具体的な手順・注意すべきポイントなどを解説します。制度の基本をおさえつつ、2024年度診療報酬改定で変わった点や、フォローアップの必要性なども交えて解説しています。最後まで読むことで、吸入指導加算の知識が得られ、薬剤師としての専門性を活かした服薬指導が実践できるようになるでしょう。
目次
1.吸入指導加算とは?
吸入指導加算は、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の治療効果向上を目的に、2020年度診療報酬改定で新設された点数です。薬剤師が文書と練習用吸入器を用いた実技指導をおこない、手技の習得を確認することが求められています。さらに、指導内容を医療機関へ文書で提供して連携することも、評価の対象とされています。なお、2024年度改定では、かかりつけ薬剤師指導料と併算定可能となりました。
2.吸入指導加算の算定要件
吸入指導加算の算定には、以下の要件を満たす必要があります。
- 対象疾患:喘息または慢性閉塞性肺疾患(COPD)で吸入薬が処方されている患者
- 医師の指示:①保険医療機関からの求め、または②患者・ご家族からの求めがあった場合には医師の了解、いずれかが必要
- 患者の同意:上記①②いずれかにあわせて同意が必要
- 指導内容:説明文書と練習用吸入器を活用して、吸入手技の実技指導と正確な使用確認を実施
- 情報提供:指導結果を文書またはお薬手帳で保険医療機関へ報告
- 算定頻度:基本的に3か月に1回算定可能、ただし前回とは異なる吸入薬で新たな指導をおこなった場合は3か月以内でも算定可能
以上の算定要件を満たすことで、30点が算定できます。
3.吸入指導加算算定時のポイント
吸入指導加算を適切に算定するには、いくつかの重要なポイントをおさえる必要があります。制度の趣旨を理解せずに対応すると、要件を満たさず算定できないケースにつながりかねません。
ここでは、吸入指導加算算定時に確認すべき基本的なポイントについて解説します。
算定対象は喘息・COPDの吸入薬
吸入指導加算は、喘息およびCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の治療目的で処方された吸入薬が対象です。
対象となる医薬品の具体例は、以下のとおりです
| 分類 | 医薬品名(一般名) |
| 吸入ステロイド薬 | フルタイド(フルチカゾンプロピオン酸エステル) パルミコート(ブデソニド) |
| 長時間作用性β2刺激薬 | セレベント(サルメテロールキシナホ酸塩) オンブレス(インダカテロールマレイン酸塩) |
| 長時間作用性抗コリン薬 | スピリーバ(チオトロピウム臭化物水和物) エンクラッセ(ウメクリジニウム臭化物) |
| 配合剤 | アドエア(サルメテロールキシナホ酸塩+フルチカゾンプロピオン酸エステル) レルベア(ビランテロールトリフェニル酢酸塩+フルチカゾンフランカルボン酸エステル) アノーロ(ウメクリジニウム臭化物+ビランテロールトリフェニル酢酸塩) ビベスピ(グリコピロニウム臭化物+ホルモテロールフマル酸塩水和物製剤) |
吸入薬ごとに特徴があるため、指導前に吸入薬の使い方を確認しておきましょう。
患者さんの同意が必要
吸入指導加算の算定には、患者さんの明確な同意を得る必要があります。
同意取得のポイントは、次のとおりです。
- 医療機関からの依頼に基づく場合は、指導に先立ち患者さんへ説明して納得を得る
- 患者さんやご家族からの希望に応じる際は、同意を得たうえで医師の了解を得る
状況に応じて明確に同意を得ることが算定につながります。同意は文書で取る必要はないものの、同意取得の事実は、指導内容とともに薬歴に記録しておくことが重要です。
医療機関へ文書で情報提供
指導結果を保険医療機関へ文書またはお薬手帳で情報提供することも算定する際は求められます。
情報提供すべき内容は、以下のとおりです。
- 吸入指導の内容
- 患者さんの吸入手技の理解度など
また、情報提供の方法は、以下が認められています。
- 書面による報告書
- お薬手帳への記載
上記手段を活用して医師へ情報連携することで、チーム医療と算定が両立可能です。
算定は3か月に1回
吸入指導加算は、基本的に3か月に1回のみ算定が可能です。頻度制限がある理由は、指導後の定着状況を踏まえて継続的な評価が必要なためです。
ただし、前回とは異なる吸入薬が処方され、必要な指導を別途おこなった場合は、3か月以内でも再度算定できます。薬剤師は前回の算定日や薬剤名を薬歴で確認しつつ、新たな吸入薬の指導が必要であれば、再算定が可能です。
4.吸入指導加算算定時の具体的な流れ
吸入薬を安全かつ効果的に使ってもらうには、薬剤師による一連の対応が欠かせません。制度に基づいて適切に算定するには、各ステップの役割や流れを明確に理解しておく必要があります。
ここでは、吸入指導加算を算定する際の具体的な手順について解説します。
同意取得
患者さんからの同意取得は、吸入指導加算を算定するうえで不可欠です。医療機関からの要請がある場合は、その依頼内容を説明し、患者さんやご家族の理解を得ることが必要です。
一方、薬剤師から介入が必要と判断した場合は、患者さんやご家族へのヒアリングを実施し、吸入指導加算に関する同意を得てから、医師に疑義照会で了解を得ます。薬剤師であれば同意の取得有無にかかわらず必要な指導をおこないますが、同意が取得できれば算定につながります。
服薬指導
薬剤師は練習用吸入器を用いて、患者さんへ吸入手技を実技を交えて指導します。また、吸入薬の効果を十分に得るためにも、患者さんの正しい吸入手技に関する理解度の確認も欠かせません。具体的には、デモ機器(練習用吸入器)で吸入する動作を示し、患者さんに同様の動作をしてもらいながら、手技を確認します。口頭説明や説明文書だけでなく、練習用吸入器の併用が重要です。
医師へ情報提供
吸入指導加算の算定には、薬剤師が指導を終えたあとに医師へ情報提供をおこなうことが必須条件です。情報提供する内容は、以下のとおりです。
- 吸入指導の内容
- 吸入手技の理解度など
お薬手帳での情報提供でも算定要件を満たせるものの、文書提供がチーム医療や地域支援体制加算の観点でおすすめです。
服薬指導後のサポート
吸入指導加算算定後、日常的に吸入が問題なくおこなえているかのフォローアップも重要です。算定要件に服薬後のフォローアップは含まれていないものの、適切な治療効果と副作用防止の観点で、薬剤師のサポートは欠かせません。具体的には、1週間~2週間後に電話などで、吸入手技や効果、副作用などを確認し、必要に応じて医師に報告するとよいでしょう。安全性と治療効果の確保のため、服薬フォローアップを積極的に実施する姿勢が薬剤師には求められます。
なお、「つながる薬局」を利用すれば、服薬指導後のフォローをLINEで実施できます。
メッセージ数の上限なく、送信予約やテンプレート登録で効率よく患者さんとのやりとりができるため、吸入指導加算算定後のフォローに「つながる薬局」をぜひご活用ください。
▶メッセージ機能が充実!LINEで服薬フォローができる「つながる薬局」
5.吸入指導加算算定時の注意点
吸入指導加算は他の薬学管理料との併算定が限定的なため注意が必要です。2024年度改定まではかかりつけ薬剤師指導料と併算定できませんでしたが、現行ではかかりつけ薬剤師指導料との併用が可能となりました。ただし、服薬管理指導料の特例に該当する場合やかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している場合には算定できず、服薬情報等提供料も併算定不可です。吸入指導加算をする際は、現在の調剤報酬点数や自薬局の状況を確認し、併算定可否を正確に把握することが重要です。
6.まとめ
吸入指導加算は、吸入療法の効果を最大限に引き出すために薬剤師の専門性が求められる重要な点数です。算定要件や手順を正しく理解し、患者さんの同意取得や情報提供を適切におこなうことで、点数を確実に活用できます。服薬後のフォローも含めた継続支援を意識することで、薬局としての信頼性と患者満足度の向上にもつながります。当記事の内容を参考に、日々の業務で吸入指導加算を有効に活用し、より質の高い薬学的ケアを提供してください。