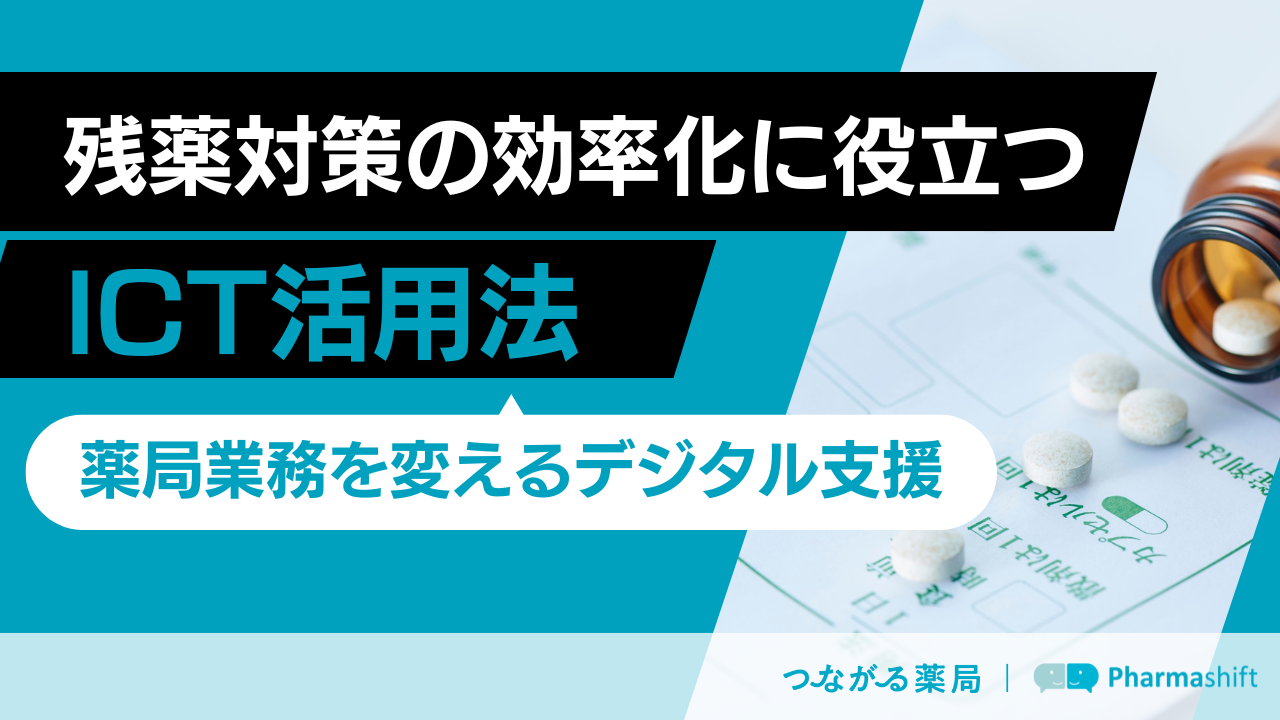執筆者・監修者:薬剤師
残薬対策は薬局にとって医療の質と経営改善の両面で重要な課題です。ICTを導入すれば、服薬状況の把握や残薬確認を効率化でき、薬剤師が対人業務に集中できる環境が整います。
しかし、現場では以下のような疑問もあるでしょう。
「残薬対策はなぜ必要?」
「残薬対策にICTは活用できる?」
「在宅でもICTは残薬対策に有効?」
当記事では、ICTを活用した残薬管理の最新動向や薬局で実践できる取り組みを解説します。
最後まで読めば、薬局経営の改善と患者さんの安全性向上を両立させる具体的なヒントを得られるでしょう。
目次
1.残薬の現状と薬局における対策の必要性
日本において、余った薬である「残薬」は薬局利用者の約9割に見られます。患者さん側の飲み忘れ・重複処方・自己判断による中断などが、残薬が発生する主な原因です。厚生労働省の調査によれば、在宅患者訪問薬剤管理指導などで改善可能な残薬に関連する薬剤費は、年間約500億円と推計されています。薬剤師が残薬を確認し、処方薬の処方日数を調整したり患者さんとの服薬フォローを強化したりできれば、膨大な無駄を削減可能です。残薬をそのまま放置すると治療効果が低下し、患者さんの健康が損なわれる恐れがあるため、薬局にとっては医療の質と経営双方から対策が不可欠です。
2.残薬対策におけるICT活用の現状
ICTの活用は残薬管理を効率化し、薬局業務を変える重要な手段となっています。オンライン服薬指導により、薬剤師は患者さんの自宅にある残薬を確認でき、飲み忘れや重複投与の把握が容易になりました。
また、電子お薬手帳では調剤情報が共有され、複数の医療機関で処方された薬を一元的に記録できるため、重複処方や相互作用、残薬リスクを早期に把握できます。
さらに、AI薬歴支援ツールを導入すれば、残薬情報の入力や整理が迅速化され、対人業務への時間を確保可能です。これらの仕組みによって、薬局は残薬削減と業務効率化を同時に実現できる段階に入っています。
3.薬局におけるデジタルツール活用による残薬対策
薬局業務の効率化には、デジタルツールの活用が欠かせません。患者さんの服薬状況や残薬を把握しやすくなる仕組みを導入することで、薬剤師の負担を軽減しつつ支援の質を高められます。
ここからは、薬局で活用できる具体的なデジタルツールについて掘り下げていきましょう。
オンライン服薬指導を活用した状況確認
オンライン服薬指導は遠隔で残薬把握を可能にし、薬局の残薬対策を飛躍的に効率化しています。法律の改正により令和元年から制度が整備され、実施要領を改めながら、薬剤師が映像・音声を用いて服薬指導を実施できるようになりました。
オンライン服薬指導を用いると、患者さん宅にある医薬品の種類・残量・服薬状況などを画面越しに確認でき、飲み忘れ・重複処方等の問題を早期発見できるメリットがあります。
さらに、オンライン服薬指導を導入した薬局は、対面での確認が難しい時間帯や遠隔地に住む患者さんのケアを強化でき、残薬発生を抑制しながら業務効率向上が図れています。
電子お薬手帳をリマインドツールとして飲み忘れ防止
電子お薬手帳アプリは、飲み忘れ防止に向けて活用できる手段であり、残薬対策に有効です。
電子お薬手帳の機能には、服薬時間ごとに通知するアラーム機能が備わり、ユーザーが服薬スケジュールを確実に守れる仕組みが提供されているものがあります。また、処方薬の情報をアプリ内に登録し、自動的に通知を出せる機能が搭載されているものや、いつ医薬品を使い切るかといった日数予測が可能なものもあります。これにより、患者さんは飲み忘れを自ら防げるようになり、残薬発生の要請が可能です。さらに、家族など介助者の設定ができるアプリであれば、フォロー体制も強くなるため、安心感が増すでしょう。
LINEなどアプリによるコミュニケーションで残薬対策
薬局と患者さんがアプリを通じて日常的に連絡を取り合える仕組みは、残薬対策に有効です。
患者さんはLINEなどを通じてチャット形式で気軽に相談でき、薬剤師は服薬状況や残薬の有無を把握しやすくなります。たとえば、服薬開始日や服薬中にメッセージを送信すれば、飲み忘れや残薬発生を早期に確認できます。さらに、通知機能やアンケート機能を組み合わせることで、患者自身の意識を高め、服薬遵守を促すことも可能です。薬局側では、受け取った情報を一覧化して残薬リスクの高い患者さんを優先的に支援できるため、効率的に介入がおこなえます。結果として、アプリを介した双方向のやり取りは、残薬削減と患者満足度向上の双方に寄与する方法といえます。
4.在宅における多職種連携ICTツールを活用した残薬対策
在宅医療の現場では、薬局だけでなく医師や看護師との連携が不可欠です。ICTツールを活用することで、多職種が患者さんの服薬情報を共有しやすくなり、残薬に関する対応も効率的に進められます。
ここからは、多職種連携による効果と在宅患者支援におけるメリットや課題について見ていきましょう。
ICTツール導入による残薬管理の効率化と連携効果
ICTツールを導入すると、薬局は在宅患者さんの残薬管理を効率化でき、医師・看護師などとの連携も強化できます。
長崎県の「おくすりネット長崎」では、調剤情報共有システムにより薬局間で処方情報が一元化され、重複投与・相互作用のチェックが容易になりました。また、多職種連携ツールを使うことも残薬管理に効果的です。薬剤師は訪問記録や服薬状況を医師や看護師と共有することで、処方の柔軟性や対応の迅速化につなげられます。
こうした仕組みを導入することで、薬局は残薬削減だけでなく、患者さんの安全性向上や業務の効率化を実現できるでしょう。
在宅患者フォローにおけるICTのメリットと課題
ICTを活用すれば、在宅患者さんの残薬や服薬状況を遠隔で把握でき、早期に飲み忘れや過剰在庫を発見可能です。たとえば、情報共有システム経由で処方データ・記録が見られれば、医師・看護師との処方調整が円滑になります。
一方で、通信回線の不安定さや受信環境の差、住環境による電波遮断などにより遠隔確認が困難となるケースもあります。さらに、高齢者や通信機器操作に不慣れな利用者が多いため、ツールの使い勝手・支援体制が重要です。
ICT活用のメリットと課題を比較検討しながらの導入検討が欠かせません。
5.残薬対策につながる業務効率化と対人業務シフトにおけるICTの役割
ICTを導入すれば、薬局は調剤・薬歴記録など対物業務の負担を軽減し、薬剤師が患者さんとの服薬指導や残薬確認など対人業務に時間を割けるようになります。電子薬歴システムでは、処方履歴・服用歴を瞬時に表示できるため、手書きの薬歴の検索や必要な情報を探す時間が省けます。さらに、自動調剤ロボットや分包機・錠剤ピッキング装置を用いることで、調剤作業や医薬品の取り揃えの時間が短縮し、ヒューマンエラーの削減も可能です。また、薬歴作成支援AIや音声入力機能を備える電子薬歴であれば、薬歴記載時間を大幅に削減し、指導に注力できる体制を整えられます。こうした効率化は残薬発生の抑制にもつながり、薬局経営と患者さんの安全の両方に寄与します。
6.残薬対策には「つながる薬局」がおすすめ!
「つながる薬局」は、LINE公式アカウントを活用してオンライン服薬指導・電子お薬手帳・服薬フォローなどを一元的に提供するサービスであり、残薬対策にもおすすめです。LINEアカウント上で処方箋送信からオンライン服薬指導・決済まで完結でき、患者さんが薬局に来局できない場合でも服薬状況や残薬の有無を薬剤師が確認できます。
電子お薬手帳機能では、過去の処方薬履歴を一元的に確認でき、・重複投与リスクや相互作用の把握にも役立ちますを薬局画面で確認可能です。
服薬フォロー機能は、メッセージ送信予約・テンプレート作成利用・選択式の回答ボタン等を備えており、飲み忘れ防止や残薬発生の早期検知を支援します。
「つながる薬局」を導入すれば、薬局薬剤師は残薬管理業務を効率化でき、患者さんの安全性を向上させられるでしょう。
▶患者さんはLINEの友だち登録のみで簡単利用開始!「つながる薬局」
7.まとめ
残薬は医療費の無駄や治療効果低下につながるため、薬局での対策が不可欠です。ICTを活用すれば、オンライン服薬指導による残薬確認、電子お薬手帳での飲み忘れ防止、アプリでの服薬フォロー、多職種連携ツールでの情報共有が可能になります。さらに、電子薬歴や自動化機器の導入は対物業務を効率化し、残薬調整などの対人業務に時間を充てられる効果があります。当記事を参考に、薬局経営や実務にICTを積極的に取り入れ、患者さんのための残薬対応を進めてください。