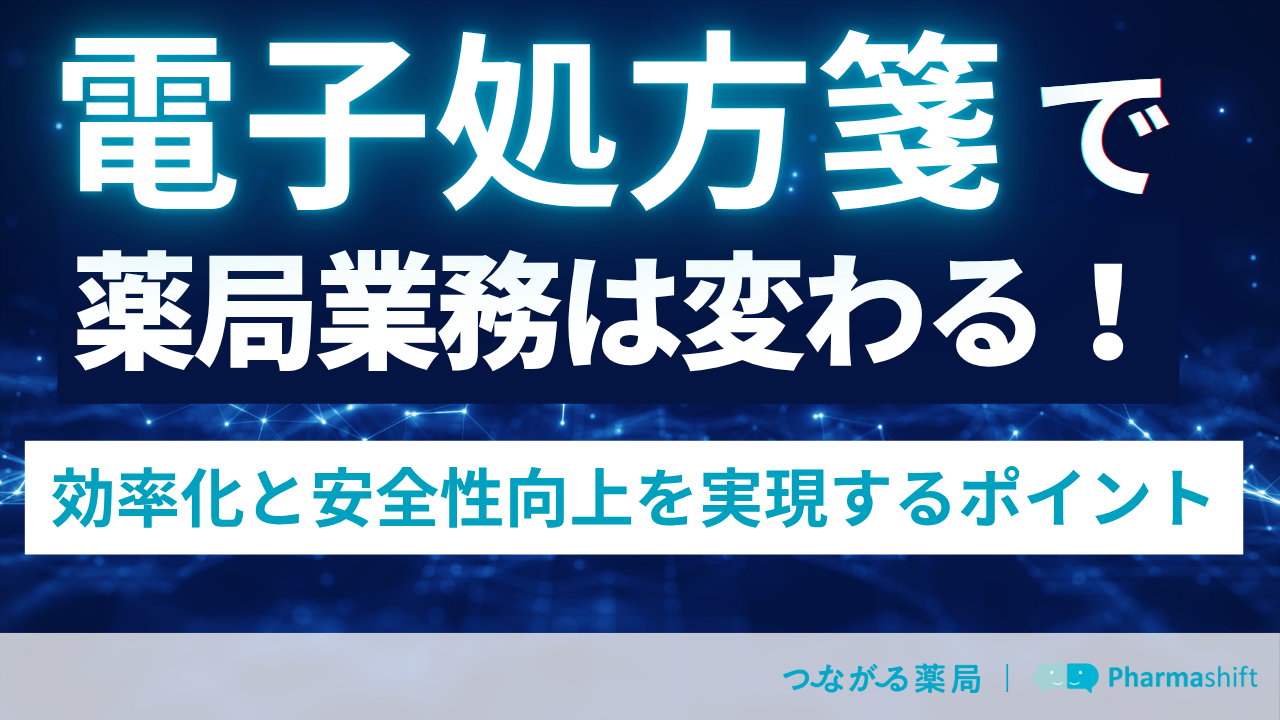執筆者・監修者:薬剤師
電子処方箋は、薬局業務の効率化と安全性向上を実現する重要な仕組みです。
しかし、以下のような疑問を抱く薬剤師や薬局関係者も多いでしょう。
「電子処方箋で薬局業務はどのように変わる?」
「電子処方箋は効率化や安全性向上につながる?」
「電子処方箋導入時のポイントは?」
当記事では、電子処方箋の普及状況や導入による業務効率化、安全性確保の具体的効果を解説します。さらに、入力作業削減や疑義照会の負担軽減、重複投薬防止など、現場で押さえておきたい要点を整理しています。最後まで読めば、電子処方箋を活用して薬局業務を最適化し、患者さんへ提供するサービスの質を高めるための実践的な視点を得られるでしょう。
目次
1.薬局業務に関わる電子処方箋の普及・発行状況
令和7年2月23日の時点では、日本全国で電子処方箋サービスを運用開始している医療機関・薬局は52,854施設に達し、普及率は約24.9%です。
(参照:厚生労働省「電子処方箋の現況と令和7年度の対応」)
種類別で見ると、薬局の普及率が67.9%と最も高く、医科診療所が12.1%、病院が5.2%、歯科診療所が2.2%となっています。電子処方箋対応薬局の数は41,030施設であり、全国の薬局の大多数にあたる導入が進行中です。
一方、医療機関側の導入率が低いため、発行される電子処方箋の件数は対応している施設数に比べ、まだ限定的な状況です。
2.電子処方箋で薬局業務はどう変わる?
電子処方箋は、薬局業務の効率化と待ち時間短縮を大きく促進するでしょう。処方情報が医療機関から電子的に共有されることで、電子処方箋の引換番号が薬局に事前に送信されている場合は、薬剤師は患者さんの来局前から調剤準備を進められます。
たとえば、入力作業の削減、医薬品の事前確保、手書き処方箋の読み取りミス防止といった具体的な効果が見込めます。実際、引換番号を用いた事前送信が可能になり、受付後の待機時間が短縮可能です。
これらの仕組みにより、薬剤師は服薬指導や患者さん対応へより多くの時間を充てられます。
3.電子処方箋による薬局業務効率化のポイント
薬局における業務効率化は、限られた人員と時間の中でより多くの患者さんに質の高いサービスを提供するために欠かせません。電子処方箋の導入は、日常業務の流れを大きく変える仕組みとして期待されています。
業務の最適化を実現するために押さえておきたい具体的な要素について、詳しく見ていきましょう。
処方箋データの自動取込で入力作業を削減
処方箋データを自動で取り込む仕組みは、薬局業務において大きな効率化を実現します。
従来は紙処方箋を確認してシステムに転記する必要があり、入力作業に時間がかかるうえ、誤入力のリスクも伴いました。電子処方箋では処方情報がデータとして直接取り込めるため、入力時間の削減とヒューマンエラーの低減が可能です。入力作業の短縮や転記ミスの防止、業務負担の軽減といった効果が期待でき、結果として患者さん対応に充てられる時間を増やせるでしょう。
紙の処方箋の保存業務が不要に
紙の処方箋保管が不要になることも、薬局業務の効率化に直結します。
従来は処方箋をファイリングし、保存期限まで倉庫や書庫で管理する手間が発生していました。電子処方箋では処方内容がシステム上に保存されるため、紙媒体の整理や保管スペースが不要になります。保管棚や倉庫の削減、整理時間の短縮、紛失リスクの解消といったメリットがあるため、結果として書類管理にかけていた労力を患者さん対応に振り向けられるでしょう。
情報共有の促進で疑義照会の負担軽減
情報共有が円滑になることで、疑義照会の負担は大幅に軽減されます。
電子処方箋では処方情報が統一されたデータ形式で共有されるため、医師と薬剤師の間で内容の解釈に差が生じにくくなります。結果として、電話やFAXによる確認回数が減少し、日常業務の効率化に直結するでしょう。処方意図の明確化や連絡手段の簡略化、確認時間の短縮といった効果が期待されるため、薬剤師は本来の専門業務に集中しやすくなります。
オンライン連携により患者待ち時間が短縮
オンライン連携の仕組みは、患者さんの待ち時間短縮に寄与します。
電子処方箋では処方情報を取得するための引換番号が事前に薬局へ送信できるため、薬剤師は患者さんの来局前から調剤準備を進められます。これにより、受付後に発生していた入力作業や薬の取り寄せ時間が短縮できるでしょう。来局前の調剤開始や在庫確認の迅速化、引換番号による処方情報共有といった改善により、結果的に患者さんへのサービス向上と業務効率化の両立を可能にします。
4.電子処方箋による薬局業務の安全性向上のポイント
電子処方箋の導入は、調剤業務における安全性を高める要因となります。従来の紙媒体の処方箋に比べて誤りのリスクを減らし、正確性を確保する仕組みが整えられています。
安全な調剤業務をおこなうために押さえておきたいポイントについて、詳しく見ていきましょう。
過去の処方・調剤履歴共有で重複投薬を防止
過去の処方や調剤履歴を共有できることは、薬局業務の安全性を高める重要な仕組みです。
電子処方箋では、患者さんごとに直近から数年分の履歴を参照でき、薬剤師は重複投薬や相互作用のリスクを事前に把握できます。同一成分の重複投与防止や相互作用の早期発見、処方内容の適正化といった効果が得られるため、調剤過誤を防ぎ、より安心できる薬物治療を提供できるでしょう。
重複投与・併用禁忌の自動チェックが可能
重複投与や併用禁忌を自動で検出できる仕組みは、薬局業務の安全性を高める要です。
電子処方箋では処方内容が入力される段階でシステムによるチェックがおこなわれるため、薬剤師は瞬時にリスク情報を把握できます。たとえば、同一成分の重複や作用機序が重なる医薬品、禁忌組み合わせといった事例が自動的に警告されます。結果として調剤過誤の防止につながり、患者さんにより安心できる薬物療法を提供できるでしょう。
手書き処方箋の読み間違い・転記ミス防止
手書き処方箋に伴う読み間違いや転記ミスを防ぐことは、薬局業務の安全性を高める重要な要素です。
電子処方箋では処方内容がデジタルデータとして統一されるため、文字の判読間違いやシステムへの入力誤りを大幅に減らせます。たとえば、判読困難な筆跡による誤読防止や転記作業の不要化、調剤内容の正確性確保といった効果があります。結果として調剤過誤のリスクが抑えられ、患者さんに安心して医薬品を提供できる体制が整うでしょう。
処方箋紛失・偽造リスクの低減
処方箋を電子化することで、紛失や偽造のリスクを大幅に低減できます。
紙の処方箋は患者さんが持参する過程で紛失する可能性があり、改ざんや不正利用の懸念も存在しました。電子処方箋では処方情報がシステムで一元管理され、データ通信によって正規の薬局にのみ送信されます。そのため、紛失による再発行の回避や改ざん防止、不正利用の抑止といった効果が期待できます。結果として、安全で信頼性の高い調剤環境を提供できるようになるでしょう。
5.電子処方箋導入で押さえておきたい薬局業務上のポイント
電子処方箋を円滑に運用するには、導入前から業務体制の整備が欠かせません。効率化や安全性の恩恵を最大化するには、環境構築や人材育成、現場の運用体制を多角的に検討する必要があります。
ここから、導入時に重要となる実務上のポイントについて解説します。
システム環境と必要機器の準備
電子処方箋を導入する際には、システム環境と必要機器の整備が欠かせません。
オンライン資格確認システムに対応した環境を整え、処方情報を安全に受け取れるようにする必要があります。
さらに、薬剤師の身元確認にはHPKIカードが必須であり、読み取りに対応したICカードリーダーの準備も求められます。加えて、電子処方箋に対応する調剤システムの更新も重要です。
オンライン資格確認システムの導入・HPKIカードの配備・ICカードリーダーの設置といった具体的対応をおこなうことで、安定した運用が可能になるでしょう。
スタッフへの操作研修と習熟期間の確保
電子処方箋を円滑に活用するには、スタッフへの操作研修と習熟期間の確保が重要です。
新しいシステムは便利であっても、導入初期は操作に戸惑う場面が想定されます。事前にマニュアル整備やシミュレーションをおこない、段階的に実務へ取り入れることで不安を軽減できるでしょう。
たとえば、基礎研修の実施やトライアル期間の設定、操作フォロー体制の構築といった取り組みが効果的です。結果として、スタッフ全員が自信を持って運用できる体制が整います。
紙処方箋との併用運用への対応
紙処方箋との併用運用に対応することは、薬局業務の安定化に欠かせません。
電子処方箋は全国で普及が進んでいますが、すべての医療機関が導入しているわけではなく、紙と電子が並行して扱われる場面が続きます。現場では、電子処方箋の受付や紙処方箋の管理、双方の運用を含めた業務フロー構築といった体制が必要です。両方を適切に運用することで、患者さんに滞りないサービスを提供できるようになるでしょう。
6.まとめ
電子処方箋の普及は、薬局業務を効率化し患者さんへのサービスを向上させる大きな契機となります。入力作業や保存管理の削減により業務負担を減らし、待ち時間短縮によって利便性を高められます。さらに、過去の処方履歴の参照や自動チェック機能が安全性を確保し、誤投薬のリスクを抑制可能です。スタッフ教育や併用運用への対応を整えることで安定した導入ができるでしょう。当記事を参考に、電子処方箋を実務改善に向けて活用してください。
「つながる薬局」では、処方箋送信機能により電子処方箋の引換番号を事前に受け付けられます。また、電子処方箋利用時のオンライン服薬指導もスムーズに受付可能です。