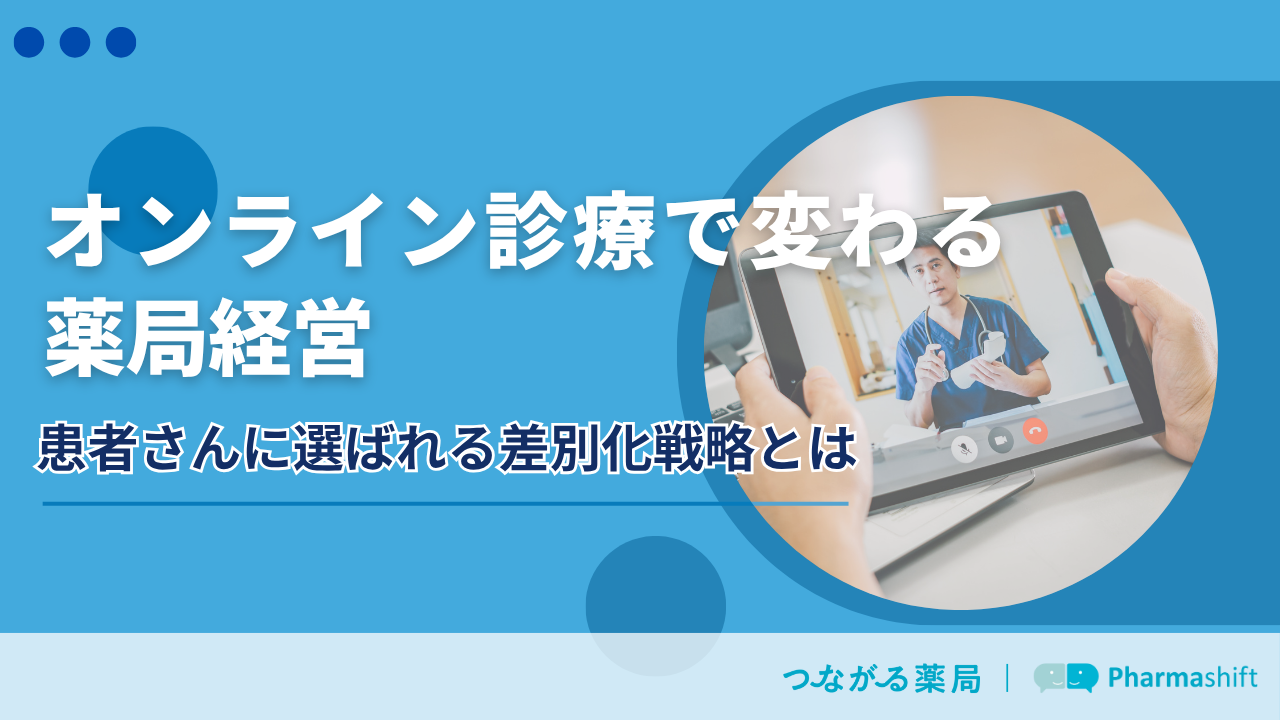執筆者・監修者:薬剤師
オンライン診療・服薬指導の拡大は、薬局経営のあり方を大きく変える転換点です。国の医療DX推進や報酬制度の見直しにより、オンライン対応が薬局の経営戦略として不可欠になりました。
しかし、次のように感じている方もいるのではないでしょうか。
「オンライン診療・服薬指導の現状は?」
「今後オンライン診療・服薬指導は拡大する?」
「オンライン診療・服薬指導に対応するメリットは?」
当記事では、オンライン診療・服薬指導の現状と課題、国の方針、薬局経営に与える影響について解説します。また、オンライン服薬指導の対応拡大によるメリットや、差別化を実現する実践的な戦略まで紹介します。最後まで読めば、デジタル時代に薬局が選ばれ続けるための方向性が明確になるでしょう。
目次
1.オンライン診療・服薬指導の現状|導入率8割でも実績1割の壁とは?
オンライン診療・服薬指導の制度が拡大する一方で、薬局・患者さん・医療機関の間には依然として温度差があります。オンライン診療・服薬指導の導入率が高くても、実際の利用につながらない背景には、それぞれの立場に特有の課題が存在します。
ここでは、薬局・患者さん・医療機関の三者が直面する現状を詳しく見ていきましょう。
薬局の現状|2024年調剤報酬改定でオンライン対応は必須要件に
2024年度の調剤報酬改定では、連携強化加算の施設基準に「オンライン服薬指導体制の整備」が新たに追加されました。これにより、薬局が連携強化加算を算定するには、通信機器を活用できる環境の整備が必須となりました。
また、同加算の評価は従来の2点から5点へ引き上げられ、オンライン対応による地域連携の強化が明確に評価されるように変更されています。
上記の背景をふまえると、薬局はICTを活用した服薬指導体制を整備し、継続的な収益確保を目指す必要があります。
患者さんの現状|スマホ操作への不安と利用までの煩雑さ
高齢の患者さんでは、スマートフォンの操作に対して不安を感じる方も多く、オンライン診療・服薬指導をためらう要因の一つとなっています。また、受診前にアプリのインストール・問診入力・決済など複数の手続きが必要で、こうした工程が利用を難しくしているケースも見られます。さらに、対面で顔をあわせて相談したいという希望も根強く、オンラインの利便性だけでは十分な利用につながらない場合もあります。
上記の理由により、スマホ操作への不安や追加費用、対面希望という3つの壁が、オンライン診療・服薬指導の普及に影響を与えていると考えられます。
医師・医療機関の現状|オンライン診療への消極性と薬局との連携不足
医師・医療機関では、オンライン診療の導入に慎重な姿勢が目立ちます。診療報酬が対面診療に比べて低く設定されており、収益性に対するインセンティブが乏しい状況です。
また、診察時に触診や検査が必要となるケースではオンライン診療が難しいと判断されるため、医師は対面を優先しがちです。加えて、薬局と医療機関との間でシステム的・運用的な連携が十分に整っておらず、処方箋の送付や情報共有で業務負担が増えるという声も上がっています。
上記の要因が相まって、オンライン診療と薬局との協働が進みにくい現状にあります。
2.オンライン診療・服薬指導の今後の展望|国が推進する医療DXと法整備の動き
オンライン診療・服薬指導の普及を支えるには、制度的な整備と医療DXの加速が欠かせません。国はデジタル技術を活用した医療体制の確立を目指しており、政策としても明確な方向性を打ち出しています。
ここでは、国が定めた医療DXの基本方針や法整備の動きを解説します。
厚生労働省の「基本方針」策定と具体的な推進策
厚生労働省は、「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」を策定し、公的な方針として位置付けました。
※参考:厚生労働省「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」
この基本方針では、遠隔医療・オンライン診療の実施形態を整理し、導入・運用上の課題を明らかにしています。
また、以下のような推進策を挙げています。
- 好事例集の公開
- 都道府県・市町村レベルでの周知・支援体制構築
- 医療機関・薬局等を対象にICT利活用促進
上記によって、薬局を含む医療提供機関はオンライン対応体制を整備する動機が強まりました。
医療DXの一環としての法制化と診療報酬による後押し
医療法における遠隔医療の位置付けを含む法制度整備が進展しています。さらに、報酬制度においても医療DX推進体制整備加算の創設によって、オンライン診療や電子処方箋・電子カルテの導入体制が実質的に評価対象となりました。具体的には、オンライン資格確認を活用した診療情報・薬剤情報の取得と活用、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの導入が施設基準として設定されています。
これにより、診療報酬上のメリットを得る仕組みの整備により、薬局を含む医療提供体制のデジタル化対応が後押しされています。
3.オンライン診療・服薬指導が薬局経営にもたらすメリットと今後の可能性
オンライン診療・服薬指導の普及は、薬局経営のあり方を大きく変える契機となっています。デジタル技術を活用することで、患者さん対応や経営戦略に新たな可能性が生まれています。
ここでは、オンライン診療・服薬指導により薬局が得られるメリットと今後の展開について、詳しく見ていきましょう。
患者さんの満足度向上|待ち時間ゼロと感染症リスクの低減
患者さんは服薬指導を自宅で受けられることで、薬局まで移動する時間や待ち時間を大幅に削減できます。オンライン服薬指導の導入によって、薬局の来局回数や滞在時間を抑えることが可能になり、感染症の流行期には対面での接触リスクを下げるメリットが生まれています。
こうした利便性と安心感が薬局に対する評価向上につながり、薬局経営にとって重要な差別化要素につながるでしょう。
商圏の拡大とデータに基づいた新たな薬局経営が可能
オンライン診療・服薬指導の導入により、薬局は地理的な制約を超えて遠隔地の患者さんにサービスを提供できるようになりました。これにより、都市部と地方の双方で新たな商圏が形成され、経営基盤の拡大が期待できます。また、患者データを活用することで、在庫管理や服薬フォローの最適化、個別提案などデータ駆動型の経営判断が可能になります。
上記の取り組みは、薬局の持続的な成長と競争力強化に直結するでしょう。
薬剤師の業務効率化と働き方改革の推進
オンライン診療・服薬指導の拡大は、薬剤師の業務効率化と働き方改革を両立させる転機です。とくに在宅医療において、訪問せずに服薬指導を実施できる仕組みが整ったことで、移動負担や時間的制約が軽減されています。また、リモートワークの導入が進めば、子育てや介護と両立しながら専門性を発揮できる働き方も現実的になります。オンライン服薬指導の活用は、薬剤師の生産性向上と働きがいの両立を支える重要な手段といえるでしょう。
4.オンライン診療・服薬指導で差別化する薬局経営|患者さんに選ばれ続けるための戦略とは
オンライン診療や服薬指導を導入しただけでは、薬局の成長は限られます。患者満足度を高め、継続的に選ばれるには、地域医療との連携やデジタルツールの活用、利用促進の工夫が欠かせません。
ここでは、オンライン診療・服薬指導で差別化し、患者さんから選ばれる薬局を実現するための方法を解説します。
近隣の医療機関との連携を強化して紹介を増やす
薬局がオンライン診療・服薬指導の流れに参画するには、近隣の医療機関との信頼構築が欠かせません。まず、オンライン服薬指導や電子処方箋への対応状況をまとめた案内文書を医療機関に共有し、対応可能な体制を丁寧に周知します。
また、患者さん本人が希望する薬局を指定できるよう、診察時に渡せる案内チラシやQRコード付きの申込カードなどを設置してもらうことも効果的です。さらに、オンライン診療・服薬指導システムを提供する会社を通じて導入医療機関と情報共有を進めれば、紹介が増える可能性が高まり、持続的な連携体制を築けるでしょう。
電子お薬手帳の活用で「かかりつけ機能」をオンラインで実現する
電子お薬手帳を活用すれば、薬局はオンライン上でも「かかりつけ機能」を発揮できます。患者さんが電子お薬手帳に処方薬や服薬履歴を自身で登録、または薬局で自動登録されることで、薬剤情報を医療機関と共有可能です。薬局は手帳を通じて処方履歴や重複投薬リスクを確認し、オンラインでの服薬指導やフォローアップをおこなえます。
また、チャット機能や電子処方箋連携機能を備えたサービスを導入すれば、患者さんはスマホ1台で薬局とのつながりを持ち続けられます。
こうした体制を整えることで、薬局は地域における安心のかかりつけ拠点として選ばれ続ける基盤を築けるでしょう。
なお、「つながる薬局」であれば、電子お薬手帳機能だけでなく、オンライン服薬指導やLINEでのチャットも活用可能です。患者さんはLINEの友だち登録だけで簡単に利用が開始でき、新たなアプリのダウンロードなどの手間もかからないため、ぜひ「つながる薬局」の利用をご検討ください。
LINEの友だち登録だけで利用開始可能!オンライン服薬指導も可能な「つながる薬局」
患者さんへの積極的な周知・提案と利用サポートで利用率を向上させる
オンライン服薬指導の利用率を高めるには、薬局からの積極的な提案と支援が欠かせません。
まず、店頭での声かけやチラシ配布を通じて、オンライン診療・服薬指導のサービス内容を伝えましょう。オンライン診療・服薬指導に関して伝えたら終わりではなく、「オンラインでの服薬指導を利用してみませんか」などの提案も必要です。さらに、スマホ操作に不安を抱く方には、スタッフが予約や接続の設定を丁寧にサポートすることにより、安心して利用を始められるようになります。
提案とサポートを組み合わせることで、患者満足度を高めながら利用率の向上を実現できるでしょう。
5.まとめ
オンライン診療や服薬指導の拡大は、薬局経営に新たな成長機会をもたらしています。医療DXの推進により、オンライン対応は今後の必須条件となり、患者満足度向上や商圏拡大にもつながります。電子お薬手帳やシステム連携を活用すれば、地域とオンラインをつなぐ新しい「かかりつけ薬局」として差別化が可能です。当記事を参考に、時代の変化を見据えたデジタル戦略を取り入れ、選ばれる薬局経営を実現してください。