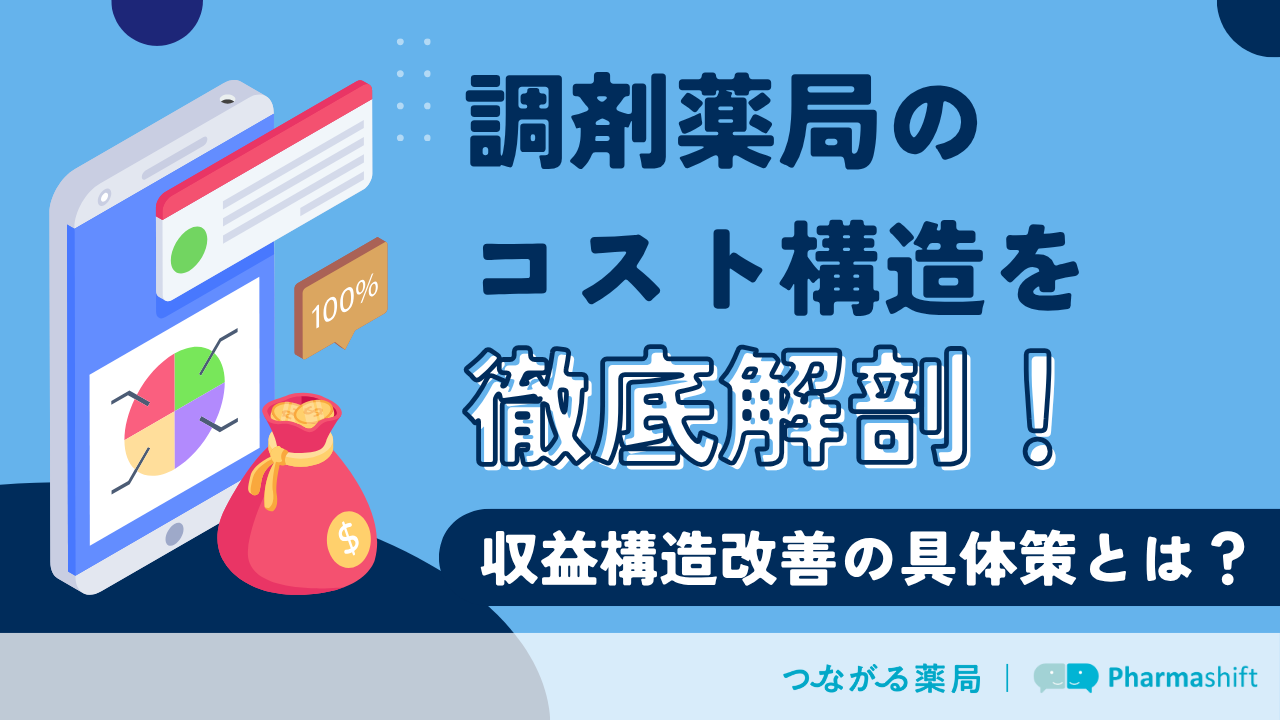執筆者・監修者:薬剤師
調剤薬局の経営は、薬価改定や人件費の上昇など外部要因により収益性の確保が難しくなっています。限られた調剤報酬のなかで安定した経営を実現するには、収益とコストの構造を正確に把握し、効率的な改善策を講じることが不可欠です。
しかし、経営改善を考えている方のなかには、以下のように感じる方もいるでしょう。
「調剤薬局の収益・コスト構造とは?」
「調剤薬局のコスト増につながる要因は?」
「収益構造改善につながる対策はある」
当記事では、調剤薬局の収益とコストの内訳から、外部環境による影響、収益改善のための具体的な取り組みについて解説します。最後まで読めば、自店舗の経営課題を整理し、利益率向上に直結する実践策を見つけられるでしょう。
1.調剤薬局の収益とコストの基本構造
調剤薬局の経営を安定させるには、収益とコストの的確な把握が欠かせません。限られた調剤報酬のなかで利益を確保するには、費用構造を理解したうえで改善の方向性を見極める必要があります。
ここでは、調剤薬局の収益とコストの内訳について解説します。
収益の内訳|調剤技術料と薬剤料
薬局の収益は、調剤技術料と薬剤料の2つの柱で構成されています。調剤技術料は薬剤師の専門知識や管理業務に対する報酬であり、薬剤料は処方された医薬品の価格に基づく収入です。かつては薬剤料から得られる薬価差益の割合が大きい傾向にありましたが、薬価引き下げやジェネリック普及によって利益率が低下しています。国の政策では、薬剤師の専門性を評価する方向へと転換が進み、技術料の比重が高まっています。持続的な薬局経営を実現するには、調剤報酬による収益構造の変化を的確に捉えることが重要です。
コストの内訳①|医薬品購入費
調剤薬局では、医薬品購入費がコスト構造のなかで大きな比重を占めています。売上のうち、薬剤料では「医薬品購入費+薬価差益」の関係が粗利益を決定します。ここでの医薬品購入費は仕入れ価格、薬価差益は薬価と仕入れ価格の差額であり、医薬品を調剤したときに得られる利益です。医薬品購入費を適切に管理することが、経営効率と利益確保の両立に直結します。
コストの内訳②|人件費
薬剤師や事務員の人件費は、調剤薬局の販管費のなかでも大きな固定費に位置づけられます。とくに薬剤師の人件費は専門職としての待遇や人手不足の影響を受けやすく、経営を圧迫する要因です。人件費の主な構成は、基本給・賞与・社会保険料・福利厚生費などであり、支出全体のバランスに直結します。効率的な人員配置や業務分担の見直し、シフト調整による稼働率の最適化などを進めることで、健全な経営の維持が可能です。
コストの内訳③|賃料・システム利用料・水道光熱費など
調剤薬局において、賃料・システム利用料・水道光熱費なども費用構造の重要な部分を占めます。店舗の賃料は毎月継続的に発生し、変動費として水道・電気・ガスの光熱費が加わります。さらに電子薬歴システムやレセコン利用料などのシステム利用料も定期的な支払いが必要なコストです。
上記のような項目を整理・可視化し、契約条件や使用量の見直しをおこなうことが、経営改善を実行するうえで重要です。
2.調剤薬局のコスト増に影響する外部環境の変化
調剤薬局を取り巻く経営環境は、近年大きく変化しています。政策改定や社会情勢の影響によって、コスト構造が複雑化し、収益の安定性にも影響を及ぼしています。持続的な経営を実現するには、外部環境の変化を正確に把握し、対応策を講じることが不可欠です。
ここでは、調剤薬局の主なコスト増要因について詳しく見ていきましょう。
継続的な薬価改定による薬価差益の圧縮
国の医療費抑制政策によって、薬価は毎年の改定で引き下げられています。継続的な薬価改定により、薬局が仕入れ値との差額として得ていた薬価差益は縮小し、従来の利益構造が成り立ちにくくなっています。薬価改定は医薬品費用の適正化を目的としていますが、薬局側から見ると経営基盤を直撃する要因です。薬価差益への依存度が高い経営モデルでは、安定的な利益確保がますます困難になっています。
薬剤師不足と人件費の高騰
薬剤師の採用競争が激化することで、薬局における人件費が顕著に高まっています。地方や中小規模の調剤薬局では、十分な人材確保のために賃金水準を引き上げざるを得ず、人件費の高騰が加速しています。労働市場の逼迫に伴い、常勤薬剤師・非常勤薬剤師のどちらにも影響が波及し、雇用管理の難易度が高まっているのが現状です。薬剤師不足と人件費の高騰が経営圧迫の要因となっています。
エネルギー価格高騰に伴う水道光熱費の増加
世界的な燃料・天然ガス価格の上昇は、国内の電気・ガス料金にも直結しています。調剤薬局の運営に欠かせない水道光熱費が高騰しており、固定費の増加リスクが高まっています。以前は小規模だった費用の割合が、賃貸店舗の賃料やシステム利用料と並び無視できない水準に達している状況です。調剤薬局経営では、光熱費を含めたコストの見える化と管理も求められます。
3.調剤薬局の収益構造を改善する具体的なコスト削減策
調剤薬局の経営効率を高めるには、固定費や変動費を見直すだけでなく、業務体制や仕入構造の最適化も欠かせません。限られた資源を有効に活用し、無駄のない運営を実現することが利益率を改善するうえで重要です。
ここでは、調剤薬局のコスト削減に直結する実践的な取り組みについて解説します。
共同購入サービス活用による医薬品仕入価格の適正化
薬局経営では、仕入れコストの抑制が収益改善につながります。そこで注目されるのが、スケールメリットを活かした共同購入サービスの活用です。複数店舗による一括発注・交渉代行を通じて、医薬品仕入れの価格を適正化できます。
具体的には、次のような方法により、コストの適正化が可能です。
- 複数薬局がグループ化して大量購入を実施
- 価格交渉を専門の代行サービスに任せることで交渉力を強化
- 在庫共有・デッドストック削減によって余剰仕入れや廃棄を防止
上記の取り組みにより、仕入れコスト低減を通じた薬価差益の確保が可能になります。
タスクシフトによる人的資源の最適化
人件費の高い薬剤師が実施している業務を、他職種や補助スタッフへ移管するタスクシフトは、人的資源の最適化を促します。
たとえば、以下のような方法を通じて、人件費の適正化が期待できます。
- 薬剤師以外が可能な医薬品の棚入れ・備品の発注・在庫確認などを明確に分類して移管
- 薬剤師は服薬指導や疑義照会、処方提案など専門性の高い対人業務に集中
上記の仕組みを構築することで、薬剤師の生産性が高まり、人的コストの適正化が期待できるでしょう。
4.DX活用による調剤薬局の収益構造改革
調剤薬局の経営環境は、デジタル技術の導入によって大きく変化しています。業務の効率化だけでなく、患者さんとの新しい関わり方を生み出す手段としてもDXは注目されています。
収益性と生産性の両立を図るために、どのようなデジタル化が有効なのか、詳しく見ていきましょう。
電子薬歴・電子処方箋導入による業務効率化とペーパーレス化
電子薬歴や電子処方箋の導入は、調剤薬局の業務効率化に直結します。紙媒体でおこなっていた記録・確認・保管作業をデジタル化することで、入力の重複やヒューマンエラーを減らせます。さらに、印刷費・保管スペース・事務作業時間の削減により、間接コストの抑制も可能です。薬歴や処方箋の電子化対応によって、薬剤師が本来の専門業務に集中できる環境を整えられるでしょう。
オンライン服薬指導がもたらす新たな可能性と課題
オンライン服薬指導は、調剤薬局に新たな成長機会をもたらす取り組みです。対面が難しい患者さんにも服薬支援を提供でき、商圏拡大や在宅医療との連携強化につながります。また、移動が困難な高齢者や地方在住者への対応を通じて、地域包括ケアの一翼を担うことも可能です。
一方で、通信環境の整備、服薬指導の記録管理、配送コストや人員配置などの課題も残ります。オンライン服薬指導を活用するには、利便性と効率性を両立する仕組みを整えることが重要です。
なお、オンライン服薬指導の実施には、LINE公式アカウント「つながる薬局」が便利です。
予約管理から服薬指導後の決済までを備えているほか、電子処方箋に対応した「患者さん起点のオンライン服薬指導」機能も追加され、より柔軟で利便性の高いオンライン服薬指導が可能になっています。
電子処方箋にも対応!オンライン服薬指導もできる「つながる薬局」
5.まとめ
調剤薬局の経営を安定させるには、収益構造とコスト構造を正確に理解し、改善策を継続的に実行することが重要です。医薬品仕入れや人件費の最適化、DX推進による業務効率化など、実践できる手段は多岐にわたります。外部環境の変化を見据えた柔軟な経営判断が、今後の薬局運営を左右します。当記事の内容を参考に、利益率の向上と持続的な成長を目指しましょう。