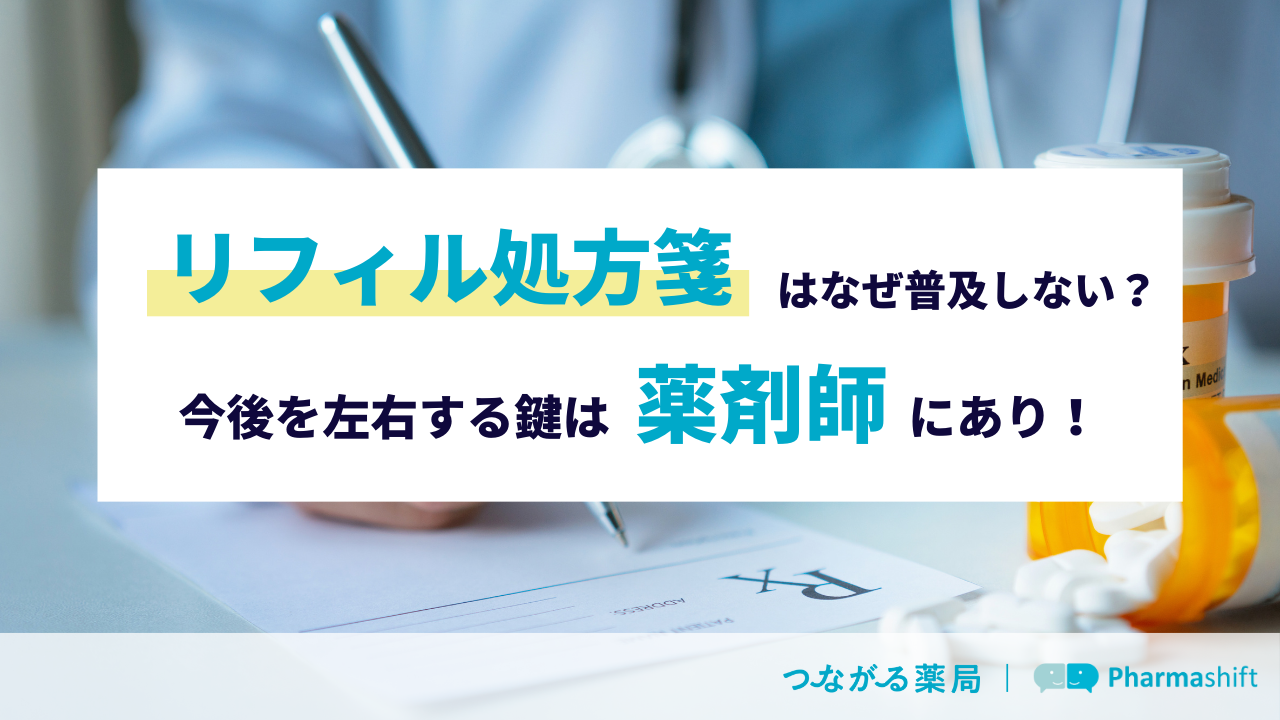リフィル処方箋は、患者さんが一定期間内に同じ処方薬で繰り返しお薬をもらえる新しい形式の処方箋です。患者さんの通院負担を軽減し、医療費削減や医療リソースの効率化を目的に導入されましたが、その普及状況には課題があります。
たとえば、以下のように疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
「リフィル処方箋の現在の発行状況は?」
「リフィル処方箋普及にはどんな課題がある?」
「リフィル処方箋の今後はどうなる?」
本記事では、リフィル処方箋の現状や課題、普及に向けた取り組みについて、薬剤師の役割を軸にわかりやすく解説します。最後まで読むことで、リフィル処方箋が日本の医療に与える可能性と、今後の展望が明確になるでしょう。
目次
1.リフィル処方箋とは?通常の処方箋との違いと導入背景
リフィル処方箋は、患者さんが一定期間内に同じ処方薬の再受け取りを可能にする新しい形式の処方箋です。通常の処方箋と異なり、医師の再診をともなわずに薬局でお薬を受け取れる点が特徴です。
ここから、通常の処方箋との違いや導入の経緯について詳しく見ていきます。
通常の処方箋との違い
リフィル処方箋は、通常の処方箋と異なり、1枚の処方箋で最大3回までお薬の受け取りが可能です。これにより、患者さんは医師の診察を受けることなく、薬局でお薬を受け取れます。一方、通常の処方箋では、1回の診察ごとに1回分のお薬しか受け取れません。
以下の表に、両処方箋の主な違いをまとめました。
| 項目 | 通常の処方箋 | リフィル処方箋 |
| 有効期間 | 発行日を含めて4日以内 | ・初回は発行日を含めて4日以内 ・2回目以降は前回調剤日から投薬期間終了日の前後7日以内 |
| 受け取り回数 | 1回 | 最大3回 |
| 医師の診察 | 毎回必要 | 初回のみ必要 |
| 対象医薬品 | 制限なし | 新薬、湿布薬、向精神薬など一部の薬剤は対象外 |
上記のように、リフィル処方箋は患者さんの通院負担を軽減する一方、適用には医師の判断や薬剤師との連携が重要です。
リフィル処方箋導入の背景
リフィル処方箋は、医療リソースの効率化と患者さんの利便性向上を目的に導入されました。高齢化社会の進行にともない、慢性疾患の患者さんが増加し、医療機関の負担が増大しています。リフィル処方箋により、症状が安定している患者さんは医師の診察なしでお薬を薬局で受け取ることが可能となるため、通院回数の減少や医療費の削減が期待されています。リフィル処方箋の制度は、医師と薬剤師の連携を強化することで、医療提供体制の効率化を実現する仕組みなのです。
2.リフィル処方箋の発行・受付状況
リフィル処方箋は、医療機関での発行状況と薬局での受付体制に影響を受けています。導入率には地域差があり、医師や薬剤師の理解や取り組みが鍵となっています。ここからは、医療機関での発行状況と薬局での調剤実態について詳しく見ていきましょう。
医療機関の発行状況
リフィル処方箋を発行している医療機関数は、以下のように推移しています。
| 区分 | 令和4年5月 | 令和4年11月 | 令和5年3月 |
| 病院 | 910 | 937 | 981 |
| 診療所 | 2,368 | 2,463 | 2,583 |
※引用元:厚生労働省公式サイト「中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第69回) 議事次第」より
令和5年3月時点のリフィル処方箋発行医療機関の割合は、病院で約12%、診療所で約2%です。
また、全体の処方箋枚数に対するリフィル処方箋の枚数および割合は、以下のように推移しています。
| 区分 | 令和4年5月 | 令和4年11月 | 令和5年3月 |
| 病院 | 6267 (0.05%) |
14436 (0.10%) |
17060 (0.11%) |
| 診療所 | 14750 (0.03%) |
16133 (0.03%) |
18854 (0.03%) |
| 合計 | 21,025 (0.04%) |
30,569 (0.05%) |
35,914 (0.05%) |
※引用元:厚生労働省公式サイト「中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第69回) 議事次第」より
全体的に、リフィル処方箋の発行は進んでいない状況といえます。
薬局での調剤状況
薬局での調剤状況は、以下のとおりです。
| リフィル処方箋 | 受付回数 |
| リフィル1回目/2回目 | 8,776 |
| リフィル2回目/2回目 | 6,316 |
| リフィル1回目/3回目 | 5,811 |
| リフィル2回目/3回目 | 7,743 |
| リフィル3回目/3回目 | 1,304 |
※引用元:厚生労働省公式サイト「中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第69回) 議事次第」令和4年11月診療分より
平成4年11月診療分の処方箋発行枚数は約6,700万枚のため、薬局でのリフィル処方箋の対応も極めて少ないことがわかります。
3.リフィル処方箋普及に向けた課題
ここまでに提示した状況のとおり、リフィル処方箋は現状普及しているとはいえません。リフィル処方箋が普及しない背景には、患者さんの理解不足や薬剤師の対応体制などの課題があります。
認知向上や連携実績の重要性について詳しく見ていきましょう。
患者さんの認知向上
リフィル処方箋の普及には、患者さんの認知向上が不可欠です。厚生労働省の報告資料では、リフィル処方箋の利用率は令和5年3月時点で0.05%と低迷しています。
※引用元:厚生労働省公式サイト「中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第69回) 議事次第」より
医師がリフィル処方箋を発行しなかった理由で一番多いのが「患者からの求めがないから」であり、約半数の医師がそのように回答しています。
※引用元:厚生労働省公式サイト「中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第69回) 議事次第」より
また、リフィル処方箋の制度まで知っている患者さんを年代別に見ると、以下の表のとおりです。
| 年代 | 制度まで知っている割合 |
| 10代以下 | 25.0% |
| 20代 | 35.6% |
| 30代 | 44.1% |
| 40代 | 33.6% |
| 50代 | 32.4% |
| 60代 | 23.7% |
| 70代 | 14.4% |
| 80代以上 | 13.9% |
※引用元:厚生労働省公式サイト「中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第69回) 議事次第」令和5年度調査より
これらのことから、患者さん自身がリフィル処方箋を理解し、医師へ相談することが制度の普及に直結すると考えられます。
薬剤師による多職種連携実績の積み上げ
リフィル処方箋の普及には、薬剤師による医師を含む多職種連携実績の積み上げが重要です。医師の中には、薬剤師に任せることへの不安を抱く方もいるでしょう。
たとえば、リフィル処方箋の活用に消極的な医療機関の半数以上が、以下の理由を挙げていることからも推察できます。
- 医師が患者の症状の変化に気付きにくくなるから
- 薬を処方する際には医師の判断が毎回必須と考えるから
このような懸念を解消するには、薬剤師が医師や看護師など他の医療専門職と連携し、実績を示しながら信頼関係を築くことが必要です。患者さんの状態変化を共有し、適切な対応を医師と協議することで信頼関係を構築できれば、リフィル処方箋の活用が促進されると考えられます。
4.リフィル処方箋の今後を左右する鍵が「薬剤師」である理由
リフィル処方箋の普及には薬剤師の役割が重要です。患者さんに寄り添い状況を把握する力や、医師との連携を支える存在として期待されています。
ここからは、薬剤師が果たすべき役割について詳しく見ていきましょう。
医師より患者さんに近い立場で状況把握がしやすい
薬剤師は、医師よりも患者さんに近い立場で接する機会が多く、親しみやすい存在として信頼を得ています。薬剤師は薬の専門家として、患者さんの薬物療法をサポートし、服薬指導や副作用の確認などをおこなう存在です。患者さんの生活習慣や体調変化などリアルな状況を把握しやすい関係性が活かせるため、リフィル処方箋の安全運用に、薬剤師の関わりが期待されています。
患者さんと医師をつなぐ役目を担っている
薬剤師は、患者さんと医師をつなぐ重要な役割を担っています。2019年の改正薬機法では、薬剤師が調剤後も患者さんの薬の使用状況を継続的に把握し、必要に応じて医師に情報提供することが義務化されました。調剤報酬点数表においても、服薬情報等提供料などの項目で、薬剤師が患者さんの服薬状況を医師に報告することが評価されています。これらの制度により、薬剤師は患者さんのフォローアップをおこない、医師と連携する役割を公式に担っていることこそ、リフィル処方箋を推進する基盤になっているのです。
病気だけでなく健康全般でサポートできる
薬剤師は、病気の治療だけでなく、予防や健康増進など健康全般にわたるサポートを提供できます。薬剤師法第1条では、薬剤師の任務として「公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民の健康な生活を確保する」と定められています。これにより、薬剤師は薬の提供だけでなく、生活習慣の改善や健康相談など、総合的な健康支援をおこなう責務を担っているのです。そのため、リフィル処方箋の活用を通じて、患者さんの継続的な健康管理や予防医療の推進に貢献できると考えられます。
5.リフィル処方箋が日本の医療に与える可能性
リフィル処方箋は、医療費削減や医療の質向上、患者さんの利便性向上など、多くの可能性を秘めています。
ここからは、リフィル処方箋の効果について詳しく見ていきましょう。
医療費削減の期待
リフィル処方箋の導入により、診療回数の減少から医療費削減が期待されています。3回利用できるリフィル処方箋が発行されれば、2回分の診察代がかからなくなります。そのため、全体の医療費を抑制できるだけでなく、患者さんの自己負担も軽減できるのです。このように、リフィル処方箋は医療費削減に寄与すると期待されています。
薬剤師の役割拡大による医療の質向上
リフィル処方箋の導入により、症状が安定している患者さんの薬に関する管理を薬剤師が担うことで、医療の質向上が期待できます。薬剤師は、患者さんの服薬状況や副作用の有無を継続的に確認し、適切な薬物療法を支援できます。これにより、医師はより専門的な診療に集中でき、医療全体の効率化と質の向上が図れるでしょう。
患者さんの利便性と自己管理力の向上
リフィル処方箋の導入により、患者さんの通院回数が減り、医療機関にかかる時間が短縮されるため利便性が向上します。さらに、医療機関にかかる回数が減ることにより、医師に頼り切ることなく、自身の健康を管理する意識の向上にもつながるでしょう。これらの結果、患者さんの自己管理力が高まり、健康維持に役立つことも期待されています。
6.まとめ
リフィル処方箋は、患者さんの通院負担を軽減し、医療費削減や自己管理力向上が期待できる制度です。一方で、医師や薬剤師の理解不足、患者さんの認知の低さなど、普及に向けた課題も存在します。薬剤師は患者さんと医師をつなぐ役割を果たし、リフィル処方箋の促進による医療の質向上と健康全般のサポートを担う重要な存在です。そのため、薬剤師は今後さらなる実績を積み重ねることにより、医師を含めた多職種との信頼関係構築が求められるでしょう。当記事を参考に、リフィル処方箋の可能性と課題を把握し、より良い医療と健康管理を実現するための一歩を踏み出してください。
なお、以下の「つながる薬局 導入店舗の声」ページにて、リフィル処方箋とオンライン服薬指導を活用したことで患者さんの負担が軽減された事例をご紹介しています。ぜひご覧ください。
導入店舗の声「リフィル処方箋とオンライン服薬指導を組み合わせて患者さんの来局負担を軽減することができています。」